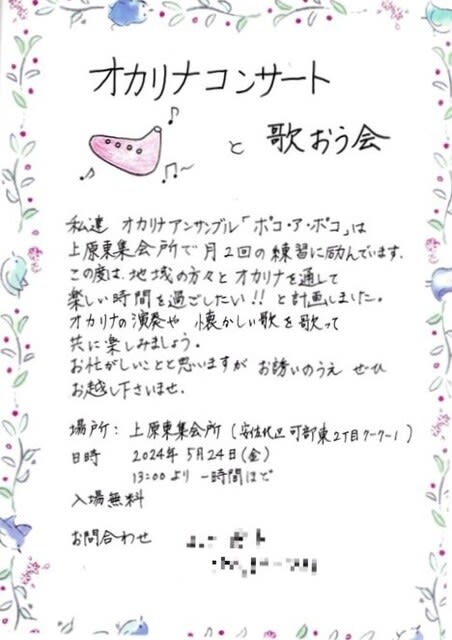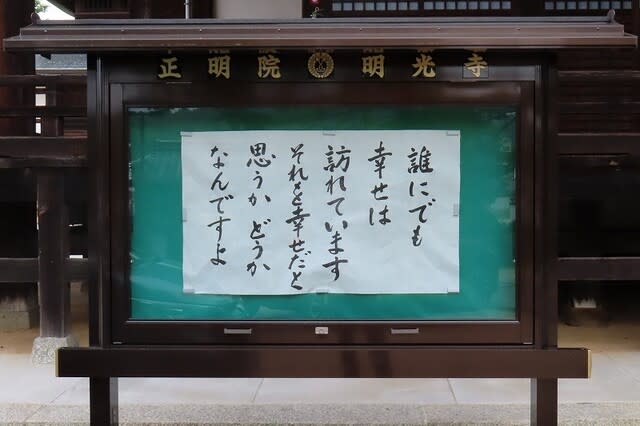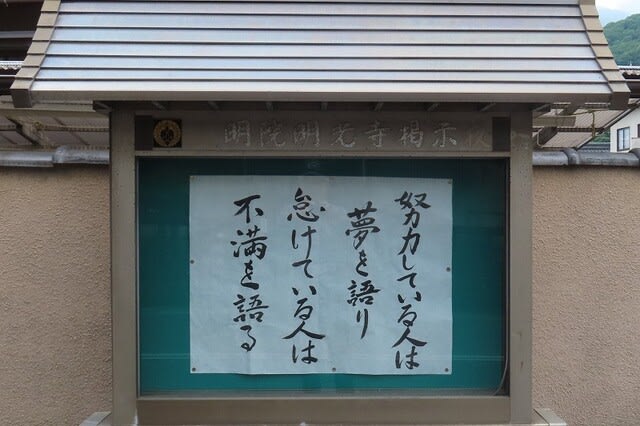今まで、何の気なしに見過ごしてきた花ですが・・・
よく見ると、ちょっと神秘的で、愛らしい花でした。
昨朝09:00頃写したものです。

ぐっと近づいてみました。

よく見ると、ちょっと神秘的で、愛らしい花でした。
昨朝09:00頃写したものです。

ぐっと近づいてみました。



我が家の猫の額で咲いているこんな花でした。

スーと伸びた花茎ですが、下から何段も小枝(?)が分岐してその先々にたくさんの花がついています。
花の構造について調べてみるとこんな説明画像があったので借用しました。

(「Hiroken 花さんぽ」さんのサイトから借用)
要旨次のような説明がなされていました。
①--3つの小さな花弁で上3/2は淡紅色に濃紅色斑紋。下3/1は白色。長さは約3㎜。
②--2つ細長い純白の花弁。長さは1~2㎝で大きさは不揃い
③--10本のオシベ。
④--子房(受粉すると果実となる部分)
⑤--2本の花柱(メシベの一部分)
ユキノシタ(雪の下)は、ユキノシタ科ユキノシタ属の常緑多年草とか。
名前は、「雪のような白い花をかぶってその下に緑の葉を広げるから」とか。
「白い舌状の花の形から雪の舌」、それが転じて「雪の下」となったとの説もあるとか。
薬がなかった時代には民間薬として重宝され、食用としても利用されたため、生活になじみの深い植物だったようです。
現在でも食用のほか、化粧品の素材など、さまざまな用途に利用されているそうです。
ともあれ、よく見てみると、小さくて愛らしいきれいな花でした。