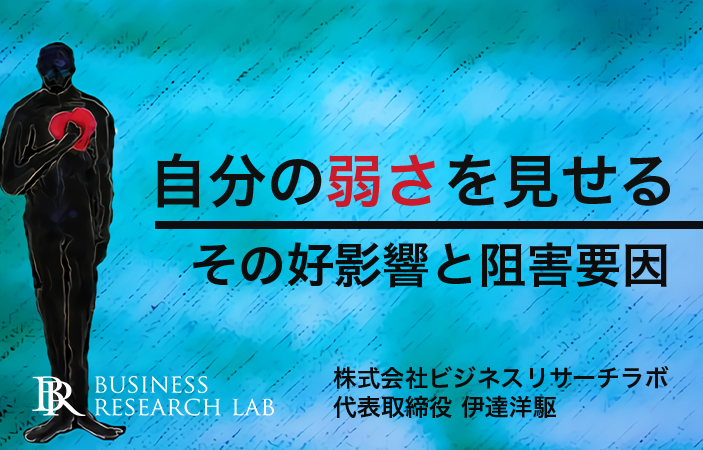
人は完璧ではなく、長所があれば短所もあります。これはあたり前のことです。職場において、自分の弱さを適切に見せることは、お互いを補い合い、より良いパフォーマンスを発揮するために必要です。
しかし、多くの人が頷けるように、他者に弱さを見せることは簡単ではありません。これは能力というより、心理的障壁があるという表現が近いかもしれませんが、なぜ難しいのかを考えるべきでしょう。
職場で弱さを見せる文化を作るためにはどうすれば良いのでしょうか。弱さを見せることに関する研究知見から得られる含意をもとに、本コラムでは弱さの開示に対して多角的に検討を加えます。
弱さを見せることには意義がある
弱さを見せることの重要性の一つは、心理的安全性を高めることにあります。特にマネジャーが自らの弱さを示すことで、部下の心理的安全性が高まります。心理的安全性とは、エドモンドソンという研究者が発展させた概念であり、対人関係のリスクを恐れないことを指します[1]。
心理的安全性が高い環境では、恐れることなく自分の意見やアイデアを表明できます。その結果、職場での個々人の能力が最大限に引き出され、パフォーマンスが向上します。さらに、心理的安全性の高い社員は、エンゲージメントも高いことが実証されています[2]。
自らの欠点を認めたり、部下に助言を求めたりすることで、マネージャーが部下に対して自分の弱さを示す行動は「謙虚なリーダーシップ」と呼ばれ、心理的安全性を高める要因です[3]。
謙虚なリーダーシップは、これまでの研究で多くの効果が認められています。例えば、会社に対する愛着を高めたり、仕事の満足度を上昇させたり、上司との関係を良質なものにしたりする効果があります[4]。
このように、特に部下を持つマネージャーにとって、弱さを見せることは重要であり、職場全体にとっても有益な行動と言えます。
開示の悪影響を過大評価する
問題は、私たちには自分の弱さを見せようとしない傾向にあることです。多くの人が、自分の弱さを積極的に見せることはありません。私自身もその一人です。これはなぜでしょうか。
この現象に関する興味深い研究を紹介します。人が自分の失敗やミスをどれだけ他者が厳しく評価するかについて過大評価することを明らかにした研究です[5]。
この研究では複数の実験が行われました。一つの実験では、想像上の社会的失敗をおかした場合、参加者は他者からの評価が実際よりも厳しいと予想していました。一方で、他者は本人が考えるほどには厳しい評価をしておらず、失敗をそこまで気にしていないことが示されました。
他の実験では、公開の場における知的失敗に関しても試されています。先述の結果と同様に、他者は本人が推測するよりも厳しく評価していないことが明らかになりました。
人は自分の失敗が他者に与える負の印象を過大評価しがちです。この傾向は、失敗した本人が自分の失敗に過度に焦点を当てることから生じ、これを「焦点効果の錯覚」と呼びます。
実際に、自分の失敗から焦点をずらすことで、その悪影響を過大評価することがいくらか緩和されることが分かりました。
この研究が示すように、人は自分の弱さを見せることによって、自分に対する評価が本来よりも過剰に下がると考えがちです。その結果、弱さを見せる行動が抑制されているのです。
他者の脆弱性は肯定的に捉える
他者の脆弱性をより肯定的に見る現象を「美しい混乱効果」と呼びます。脆弱性を示すことは本人にとってあまり良くないと推測されがちです。しかし、他者からは意外にも(少なくとも本人の推測よりは)良い形で受け止められるのです[6]。
研究では、脆弱性を見せる様々な状況を準備し、自分自身と他者がそれぞれどのように評価するかを検討しました。
結果の一般性を少しでも高めるために、複数のシナリオが用いられましたが、結果は一貫していました。他者の脆弱性を示す行動が肯定的に受容されたのです。
例えば、即興演奏を行うかもしれないというタスクを用いた実験があります。自分が演者である場合(実際には演奏していません)と審査員である場合では、脆弱性の評価に違いがありました。自分の評価より他者の評価の方が肯定的で、やはり美しい混乱効果が裏付けられました。
美しい混乱効果に影響を与える要素の一つが感情です。実験によってネガティブな感情を誘発した場合、自分と他者の脆弱性の評価差がより大きくなることが分かりました。
美しい混乱効果がなぜ起こるのかというと、他者の脆弱性を目の当たりにした時、人はオーセンティシティや信頼感、勇気などを感じ取るからです。これは、人が社会的なつながりや共感を重視していることが背景にあると思われます。
逆に、脆弱性を示す本人は、脆弱性を示すことで否定的な評価を受けたり、拒絶されたりすることを他者が思う以上に懸念しています。これは、対人関係のリスクを誤評価している結果とも言えるでしょう。
弱さを見せるために何ができるか
ここまでの研究知見を通じて、人が自己評価を過剰に厳しく行い、自分の弱さを見せることに対して過度な恐れを抱いていることが明らかになりました。しかし、実際には他者は、本人の推測よりも弱さを肯定的かつ寛容に受け止める傾向にあります。
このようなメカニズムを踏まえた上で、私たちが弱さを見せるために何ができるかを、周囲にできることと本人にできることに分けて、いくつかの提案をしてみます。
周囲にできること
- 話をしっかり聞くことが重要です。他者の話を安易に評価せず、共感を示すことで、安心感を提供できる可能性があります。判断を留保することが特に求められます。
- 弱さを開示することを勇気ある行動として称賛します。ポジティブな言葉をかけるなど、具体的な行動を取りましょう。弱さを見せても問題ないという信頼関係を築くことにつながります。
- 開示する人と開示される人という非対称な関係は、開示する人にとって負荷が高まります。小さなグループを作り、お互いに弱さを開示し、それを受け止めるといった工夫があり得ます。
- 弱さを見せることが組織にとって有用であることを啓蒙することも一案です。その上で、弱さを見せるための方法や、それを受け止める際の良い対応について教育の機会を提供します。
本人にできること
- 自分を知ることが第一歩となります。自分にはどのような特徴があるか、弱さや強さは特徴を重み付けしたものです。弱さも強さも自分の一部であることを理解し、自分自身をまず受け入れることが大切です。
- いきなり自分の核に近い弱さをさらけ出すのは誰にとっても無理があります。それどころか、反動の危険性があります。まずは小さな弱さを開示し、そして身近な仲の良いメンバーに対して開示するなど、ステップを踏みましょう。
- 弱さを開示した際にどのような反応が得られるかを予測し、それを記述しておきます。実際に開示した後に答え合わせをすると良いでしょう。そうすることで、自分が過剰に厳しい評価を予測していたことに気づくかもしれません。
- 弱さを上手に伝える方法は、コミュニケーションスキルの一種です。自分の弱さを正確に、そして建設的な表現で伝え、相手に負担を与えない方法を学びましょう。
弱さは強さをもたらす資源になる
弱さを開示するという行動は、一見すると文字通り弱い行動と思われがちです。しかし、他者から見れば、弱さを開示できること自体が強さとして受け止められることがあり、社会的な信頼を得ることができます。少し逆説的ではありますが、弱さを見せることが強さを得る方法になり得るのです。
例えば、マネージャーが自分の過去の失敗や現在の不安を部下に打ち明けた場合、これは上司の弱点や不完全さをさらけ出す行動であると同時に、それを打ち明けたことでマネージャーに対する部下の共感や敬意を引き出します。結果的にマネージャーは弱さではなく強さを手にすることができます。
弱さを見せることは、他者との関係を強化する手段となり得ます。この意味で、弱さはむしろ個々人が持つ資源であり、うまく活かせば社会的な支持を得ることが可能です。
結局のところ、人は他者に完ぺきであることを求めているわけではありません。それよりも、ある種の人間性を求めています。弱さを開示することは、自分の人間らしさを他者に感じてもらう機会となる可能性があります。
弱さというと、それをいかに克服するかという観点からアプローチされることが多いのですが、弱さはいつも克服すべき対象ではなく、周囲との関係を構築する上で、また、冒頭で紹介したようにチームのパフォーマンスを高めるための資源でもあります。
他者の評価に依存しないことが大事
ただし、こうした議論には注意すべき点があります。弱さが社会的な関係を築く強さにつながること、そして弱さは資源であるという視点は、弱さをネガティブなものと捉えがちな人にとって有効な主張になり得るはずです。
とはいえ、他者との関係を築くために自分の弱さを「利用する」という行為は、実際には、自分がどう思われるかを恐れて弱さを開示できない心理状態と構造的に似ています。つまり、他者からの評価を気にしているわけです。
他者からの評価が悪化することを恐れて弱さを開示しないのも、他者からの評価が実際には悪化せず、むしろ肯定的に受け止められる可能性を知った上で弱さを開示するのも、結局は自分自身の価値を他者の評価に依存していることに他なりません。
もちろん、人は組織において他者との関係の中で働いており、他者からの評価を気にすることは自然であり、それが全くなければ協働は成立しません。他者からの評価を意識することは高次の学習と考えられますが、自分の弱さを開示することが他者からの評価と強く結びついている状態は問題でもあります。
先ほど、弱さを開示するためには自分の弱さを受け入れることが重要である点を指摘しましたが、ここでその観点を再度考察する必要があります。
弱さや強さに絶対的なものはありません。あるチームでは特定の特徴が弱さとなっても、別のチームではその同じ特徴が強さとなることもあります。弱さや強さは、このように文脈によって変化する可能性があるものです。
そのため、変化する価値を見極め、何よりも自分自身で承認することが必要ではないでしょうか。他者の評価に依存した構造の中で自分の弱さを開示しても、自尊心の低下などの問題に直面することになるかもしれません。
最後は少し複雑な話になりましたが、弱さを見せることを単なる手段として還元するだけでは、それが危険であるという点を強調したいと考え、いくらかの私見を展開しました。
脚注
[1] Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44, 350-383.
[2] Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, R. L., Pezeshkan, A., and Vracheva, V. (2017). Psychological safety: A meta-analytic review and extension. Personnel Psychology, 70(1), 113-165.
[3] Wang, Y., Liu, J., and Zhu, Y. (2018). Humble leadership, psychological safety, knowledge sharing, and follower creativity: A cross-Level investigation. Frontiers in Psychology, 9, 1727.
[4] Luo, Y., Zhang, Z., Chen, Q., Zhang, K., Wang, Y., and Peng, J. (2022). Humble leadership and its outcomes: A meta-analysis. Frontiers in Psychology. 21, 980322.
[5] Savitsky, K., Epley, N., and Gilovich, T. (2001). Do others judge us as harshly as we think? Overestimating the impact of our failures, shortcomings, and mishaps. Journal of Personality and Social Psychology, 81(1), 44-56.
[6] Bruk, A., Scholl, S. G., and Bless, H. (2018). Beautiful mess effect: Self?other differences in evaluation of showing vulnerability. Journal of Personality and Social Psychology, 115(2), 192-205.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。














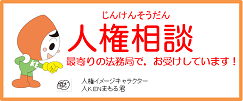
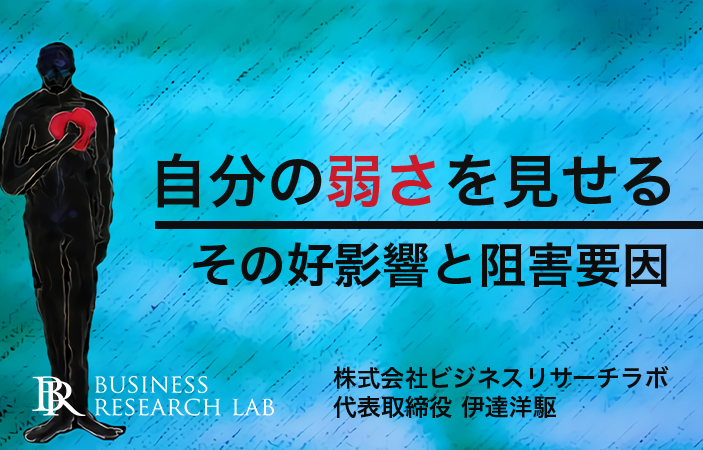
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役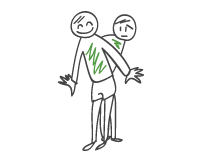 毎日ゆかいで、楽しく、うきうきしながらすごしたいもの。
毎日ゆかいで、楽しく、うきうきしながらすごしたいもの。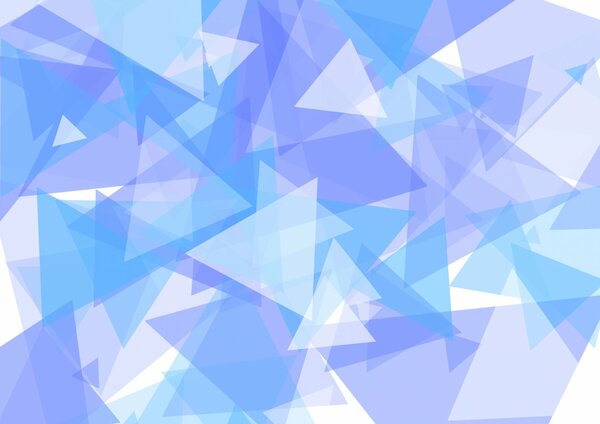 photo AC
photo AC
 再調査報告書(公表版・全文)(PDF形式 16,615キロバイト)
再調査報告書(公表版・全文)(PDF形式 16,615キロバイト)