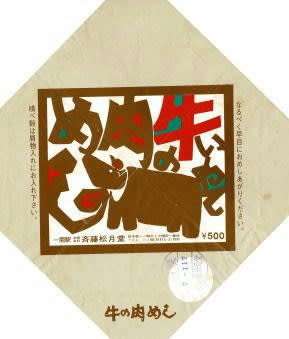今日は天気に恵まれ、予定通り山車の合同運行が行われました。
町三役などが先導して山車がやってきます。
町三役などが先導して山車がやってきます。

先陣は、浜町祭典部です。

「のへじ祇園祭り」は、野辺地港が南部藩の商港として大阪、長崎方面と交易していた最盛期の文政時代に、野辺地八幡宮のつけ祭りとして、日本海航路で上方から伝わったとされるお祭りです。
山車行列は、海水運が主流であった時代の「浜下り神事」と共通した意味をもっていて、上方の文化や物を運ぶ「宝船」である千石船の航海の安全と豊漁を祈願する行事と言われています。
そのため、毎年浜町祭典の野辺地港の合船場(造船所)で建造された千石船(北前船)の模型であると伝えられている船山車「宝船」が、露払い役として御神輿の先頭で運行します。
山車行列は、海水運が主流であった時代の「浜下り神事」と共通した意味をもっていて、上方の文化や物を運ぶ「宝船」である千石船の航海の安全と豊漁を祈願する行事と言われています。
そのため、毎年浜町祭典の野辺地港の合船場(造船所)で建造された千石船(北前船)の模型であると伝えられている船山車「宝船」が、露払い役として御神輿の先頭で運行します。

続いて熊野神社。

野辺地八幡宮。

太鼓を打っているのは、同級生A君「青森の社長さん」です。
以前は歩いていたのですが、太鼓の関係というか自分の太鼓腹の都合で、最近は軽トラックの荷台に載っているようです。
以前は歩いていたのですが、太鼓の関係というか自分の太鼓腹の都合で、最近は軽トラックの荷台に載っているようです。

少子化で、めっきり少なくなったお稚児さんの行列です。

野辺地神明宮が続きます。

一般の山車の運行も藩政時代から行われていたのではないかと推測されていますが、記録からはっきりしているのは明治30年に町内有志によって、飾山車として屋形様式の山車に移行し、今日に至っているそうです。
各祭典部自作の歌舞伎や故事等から題材を取った飾山車が続きます。
下袋町組祭典部。
各祭典部自作の歌舞伎や故事等から題材を取った飾山車が続きます。
下袋町組祭典部。

「歌舞伎十八番矢の根・藤娘」
☆「特別賞」(青い森鉄道株式会社より授与)
☆「流粋賞」(整然とし統率のとれた運行を評価)
☆「特別賞」(青い森鉄道株式会社より授与)
☆「流粋賞」(整然とし統率のとれた運行を評価)

屋形山車の下にでは、南部藩における唯一の上方文化の移入地であったとされる野辺地町に伝わる、笛、太鼓、三味線の優雅な「祇園ばやし」を奏でています。

袋町組祭典部。

「不撓不屈 山中鹿之介」
☆「秀作」
☆「秀作」

新道組祭典部。

「桜門五三桐」

同級生B君「生徒会長」です。
写真も上手いのですが、それ以上に筆が立つため、ご祝儀を頂いた方の名前を張り出すための書き手として乗っています。
写真も上手いのですが、それ以上に筆が立つため、ご祝儀を頂いた方の名前を張り出すための書き手として乗っています。

馬門組祭典部。

「仁田四郎忠常 猪狩」

金沢町組祭典部。

「里見八犬伝 化け猫退治の場」

下町組祭典部。

「木曽義仲 俱利伽羅の合戦」

城内組祭典部。

「天照伝説(天使の願い)」
☆「優秀賞」
☆「優秀賞」

野辺地西高等学校組祭典部。

「桶狭間 今川義元血戦」

最後は、駅前組祭典部です。

「清姫伝説」
☆「最優秀賞」
☆「輝星賞(山車全体のきらびやかな照明設定を評価)」
☆「祇園未来賞(町内にある中学校1校・高等学校2校計3名の生徒代表者が評価)」
☆「最優秀賞」
☆「輝星賞(山車全体のきらびやかな照明設定を評価)」
☆「祇園未来賞(町内にある中学校1校・高等学校2校計3名の生徒代表者が評価)」

本家、京都の「祇園祭」では祭り期間中、山鉾町の家々で伝わる家宝を飾ってご披露しているそうです。その時に一緒に檜扇の花を「軒花」として活けるそうです。
祇園祭が疫病や災難除けのお祭りなのと、檜扇の花は悪霊を退散させるといわれていて、
祇園祭の厄除けの花として祭りのお花にもなっているそうです。
我が町の「軒花」は、豊漁や豊作を願い稲穂に見立てたもののようです。
祇園祭が疫病や災難除けのお祭りなのと、檜扇の花は悪霊を退散させるといわれていて、
祇園祭の厄除けの花として祭りのお花にもなっているそうです。
我が町の「軒花」は、豊漁や豊作を願い稲穂に見立てたもののようです。


今では、数える程しか見ることができません。
お祭りが終わるともう秋です。
お祭りが終わるともう秋です。