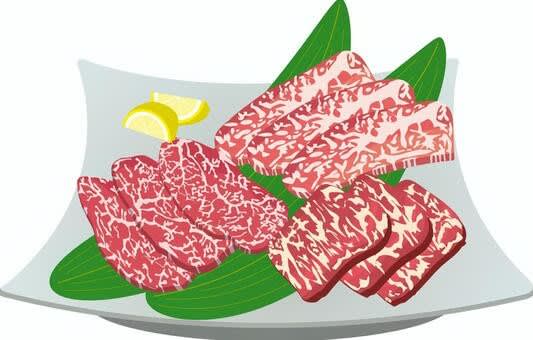令和4年10月26日(水)
火鉢欲し : 火恋し

火鉢は灰を入れて炭を熾(おこ)したり、煮炊き等に使う器具。
木製、金属製、陶磁器製などがある。

木製、角火鉢

陶製、丸火鉢
昔はもっぱら火桶(丸型の桐の木等をくり抜いて作る火鉢)を
用いたが、後世では木材で方形に作ったものを箱火鉢、角火鉢、
長火鉢といって使用していた。

ストーブ、

暖炉、
電熱、ガス、石油などを利用した暖房器具が一般化された現在
では、陶器の丸火鉢さえもあまり見かけなくなった。
火鉢は冬の季語であるが、「火鉢欲し」は晩秋の季語である。

俳人の夏井いつきさんの著書「絶滅寸前季語辞典」に、「火鉢
欲し」の記述が在ったので紹介したい。
【火鉢欲し : 火恋しの副題。
勝手に買えばア~と言いたくなるような季語であるが、これは
「火鉢」を買ってくれと言っているのではなく、「火鉢」の中
の「火恋し」という意味であるからして、誤解してはいけない。

それにしても、これも単純な季語のように見えて中々お金の掛
かる季語である。先ずは骨董品屋に行って手頃な大きさの火鉢
を買い、次にアウトドアグッズの店に行って炭を買い、、、、
はて? 火鉢の中の灰は何処で買うのじゃ?、仏壇店か?それ
とも自分で何か燃やして作らねばならぬのか。近所の寺に行っ
たら分けてくれたりしないのか?
こんなこと考えてたら、何処かの国の童話みたいに、マッチを
一本一本擦りながら,その火を恋しがってみる方がよっぽど現
実的に見えてくる。】
(俳人夏井いつき著:絶滅寸前季語辞典より、引用しました。)
ロシアのウクライナ侵攻から8カ月、、、、

このところ、ロシア軍の戦況が不利と見るや、、、、ロシア軍は
ウクライナの全土・各地に、それも発電所などの重要なインフラ
設備にミサイル攻撃を繰返し、更には一般市民の住居、公共施設
等への無差別攻撃が続く、、、、、
街の破壊、老若男女問わず無差別に殺戮をし続けている、、、。
ウクライナでは早くも冬の厳しい季節を迎え、電気が通わずに、
停電の真っ暗な中で暖房も使えずに寒さに打ち震える市民の姿
が写し出される、、、。

今、暖房を使えず、市民は薪を作り、寒さを凌いでいる姿が。
日本に出来る支援はないのか、、、?軍事支援ばかりではなく
布団や毛布などの寝具もダブついているように聞くが、、、
衣類や、暖房用品(木炭、湯たんぽ、貼る使い捨て懐炉など)
日本特有の文化は、彼の地でも役立ちそうだが、、、、

湯たんぽ、

使い捨ての貼るカイロ、
これはとても便利で直ぐ役立ちそうだが、、、
皆さん、どんどん送りましょうヨ、、、、、
今日の1句(俳人の名句)
火鉢欲しければ男もちよと恋し 夏井いつき