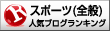東京本庄会の皆さんと手子舞のおなご衆
29日の夕刻から江戸天下祭の山車・神輿の巡行が行われた。
日比谷公園を出発。日比谷シャンテ通り、丸の内仲通りを丸ビルまでの順序。
行列は、先導(江戸木遣り、手古舞など)→民謡流し踊り→朝鮮通信使→山車(14台)→神輿(9基)と続き2時間を掛けてオフィス街を江戸情緒に染めあげる。
山車の高さは10メートル近いものもあるために電線の無い通りを選考した。
森陽一郎先生に同行した。
埼玉県本庄市出身のグループが集まり、大きく「東京・本庄会」と書かれた紙を持って丸ビルのところで待機していた。
本庄市本町自治会の山車は9番目の巡行。
山車は「石橋(しゃっきょう)」で、全長7m×幅4m×前高8m。
その由来は、1895年(明治28年)、日清戦争凱旋を記念して11世武田近江大掾清兼作の「翁」山車を購入。
1928年(昭和3年)、天皇即位の御大典に合わせ、人形を「石橋」に改めた。
人形は牡丹花に戯れて踊る獅子の姿である。人形の装束、山車胴幕は、能の約束事に従い、すべてを絹織物で金糸銀糸、金箔を用いている。
本庄の山車「石橋」が通過すると、関係者が「東京本庄会」へ近寄り声を掛けてきた。
市長をはじめ実行委員長、商店会長等々すべて森陽一郎先生の馴染みの人たちである。
歓声があがりそして交歓の様子は祭りを一層盛り上げる雰囲気を醸し出していた。
手子舞のおなご衆も集まってきて写真撮影となる。
埼玉県本庄市から参加した人たちもゴール地点に待機していた「東京本庄会」のメンバーによる思わぬ歓迎にとても喜んでいた。
開府400年(平成15年)に再現された「江戸天下祭」は、2年ごとに開催されている。
今回は3回目となる。
(9月30日記 池内和彦)
29日の夕刻から江戸天下祭の山車・神輿の巡行が行われた。
日比谷公園を出発。日比谷シャンテ通り、丸の内仲通りを丸ビルまでの順序。
行列は、先導(江戸木遣り、手古舞など)→民謡流し踊り→朝鮮通信使→山車(14台)→神輿(9基)と続き2時間を掛けてオフィス街を江戸情緒に染めあげる。
山車の高さは10メートル近いものもあるために電線の無い通りを選考した。
森陽一郎先生に同行した。
埼玉県本庄市出身のグループが集まり、大きく「東京・本庄会」と書かれた紙を持って丸ビルのところで待機していた。
本庄市本町自治会の山車は9番目の巡行。
山車は「石橋(しゃっきょう)」で、全長7m×幅4m×前高8m。
その由来は、1895年(明治28年)、日清戦争凱旋を記念して11世武田近江大掾清兼作の「翁」山車を購入。
1928年(昭和3年)、天皇即位の御大典に合わせ、人形を「石橋」に改めた。
人形は牡丹花に戯れて踊る獅子の姿である。人形の装束、山車胴幕は、能の約束事に従い、すべてを絹織物で金糸銀糸、金箔を用いている。
本庄の山車「石橋」が通過すると、関係者が「東京本庄会」へ近寄り声を掛けてきた。
市長をはじめ実行委員長、商店会長等々すべて森陽一郎先生の馴染みの人たちである。
歓声があがりそして交歓の様子は祭りを一層盛り上げる雰囲気を醸し出していた。
手子舞のおなご衆も集まってきて写真撮影となる。
埼玉県本庄市から参加した人たちもゴール地点に待機していた「東京本庄会」のメンバーによる思わぬ歓迎にとても喜んでいた。
開府400年(平成15年)に再現された「江戸天下祭」は、2年ごとに開催されている。
今回は3回目となる。
(9月30日記 池内和彦)