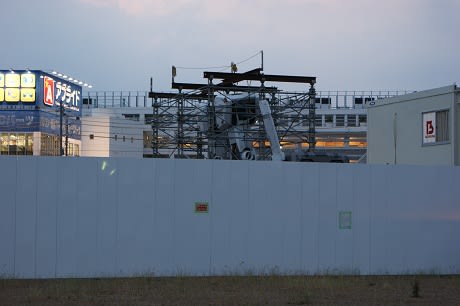やっと卒業旅行のレポが終わったかと思えば、次は大井川鐡道の話です。いつになったら終わるんでしょうねえ・・・?

んなわけで、現実世界ではもう梅雨に入りそうなところですがここではGWの話をします。
GWは故郷の静岡へ帰ってきたわけですが、ほいじゃま大鐡のSLでも撮ってくるかと思いまず琥龍さんを誘ってみました。
そしたらTAMOさんも名乗りを上げ、なんとTAMOさんの家で一泊させてもらうことになり、大鐡を2日間楽しもうというスケールのでかい話になりました。

初日はTAMOさんが都合がつかないので琥龍さんと2人で回ることに。まず新金谷のホームで1本目のSLを見送ります。
GWは大鐡にとっても書き入れ時なので1日にSLが3本運転されます。なので1本くらいここで見てもいいんじゃない見たいなノリになってます。2日目もあるしw

牽引機はC56 44。タンク式機関車のC12に長距離走行能力を付加させたもので、後ろにはテンダー(炭水車)が付いています。なのでC12との共通部分も多いです。
C56の多くは戦争中にタイに出征しました。どのほとんどが被災した中で44号機は無事生き延び、その後も現地で使い続けられました。
そして1979年に日本へ帰還。国内仕様に復元され大井川鐡道で活躍していましたが、ボイラーの不調により一旦運転休止に。
しかし、蒸機の心臓部ボイラー交換といった大改造を経て復活。その時にタイとの修好120周年を記念して外観はタイにいたときのものになっています。
賛否両論なこのタイ仕様のSLですが、私としては戦争のことを伝える一つの遺産としてこれからもこの姿で走り続けていってほしいなと思います。
次のSLまで少し時間が空くので
例の場所へ行ってみました。

通称「大代側線」や「側線」や「墓場」などと呼ばれたりそうでなかったりする新金谷から延びる引き込み線です。
ここには使命を終えた電車や機関車が運ばれてきて解体される場所です。付近には台車や車輪などのパーツがごろごろしています。
駅から別に遠いというわけでもないのですが、線路を挟んで駅舎の反対側にあるので普通の観光客なんかはまず迷い込むことはない場所で、知っている人はそのスジの人か付近にある工場の人間たちぐらいです。
本線の車窓からも見えませんし、結構巧みに隠匿されているのですw
そんなここには一見してスクラップにしか見えないC12 208が眠っています。この機関車、もとより部品取り用としてやってきたのだとか。
事実色々なパーツが抜き取られ、心臓部であるボイラーも先ほど見送ったC56 44に移植されています。共通設計だからこそなせたワザですね。それでも1台ごとに性格の違う蒸気機関車ですから、マッチしたのはある意味奇跡です。

こちらはC11 312。C12 208と違ってかつては本線を走ったことのある機関車です。引退後は静態保存される予定だったのですが、こんな感じに部品取りに。
本線を走れなくてもピカピカな静態保存機として静かな余生を送るか、自らの身体の一部を他の機関車に取り込まれようともそれでもまだ走り続けるか、どっちが正しいというのはないんだと思います。
それを知っているのは機関車自身でしょう。
死してもなお他の機関車の中で走る彼らのもとを去り、新金谷駅へ戻りました。
続く