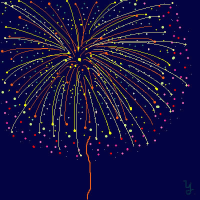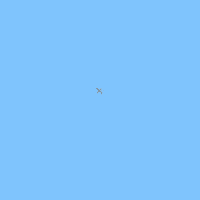認知症専門医で、認知症になり、
2021年に92歳で亡くなった
長谷川和夫さんの、
お元気だった頃の言葉
「一握りの専門家とか、
ある部分の施設とかだけでは、
認知症の人が本当に安心して暮らせるとい社会に(なるのは)なかなか難しい。
市民の一人一人が、自分のこととして、あなたのこととして、
そして、
私の事として。
そして、
ちょっとした支え合いとか、頑張ろうじゃありませんか。」
この長谷川さんの言葉の「認知症」を「脳脊髄液減少症」と入れ替えると、
私が訴えたい事もほぼ同じ。
一握りの専門医とか、
一部の病院とかだけでは、
脳脊髄液減少症の人が本当に安心して暮らせる社会になるのはなかなか難しいと私も思います。
市民の一人一人が、脳脊髄液減少症を他人事ではなく、
自分も明日事故でなりうるものとして、
自分事として、考え、
普段から、脳脊髄液減少症に対する意識を、もっと身近なものとして考え、
自分になにができるか一人一人が考えられるようになれば、
ちょっとした支え合いが、できるようになるのではないか、と思います。
脳脊髄液減少症の専門医も、
脳脊髄液減少症のさまざまな症状を自ら体験して初めて、
脳脊髄液減少症の事がわかった!と言うのかもしれません。
体験のないうちは、いくら脳脊髄液減少症患者をたくさん診たとしても、それは、
外側からだけ。
もし、脳脊髄液減少症専門医が脳脊髄液減少症になって!内側から脳脊髄液減少症を診たら、
その症状の多彩さ、
軽症から重症の症状のピンキリさ、
不定愁訴程度の症状から、
自殺を考えるほどのキツい症状まで、
その程度の差に驚くでしょう。
患者を外側からだけ診てたら、そんな症状の程度なんてなかなか見抜けないと思います。
認知症専門医の長谷川さんが認知症になって体験してはじめて、認知症の事がわかったと言うように、
脳脊髄液減少症専門医も、
自分が脳脊髄液減少症になってはじめて、
今まで診てきた患者の苦しみが理解できると思います。
逆に言えば、体験しない限り、理解できっこないと思います。
長谷川さんは、実際に起きた出来事をモチーフに絵本の原作を手がけたそうです。













![「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」の手引き: 臨床現場における正しい使い方と活かし方[DVD付き]](https://m.media-amazon.com/images/I/41OTM3qrBvL._SL160_.jpg)