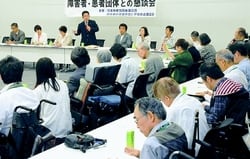紙幣にスマートフォン(スマホ)をかざすと、その券種を読み上げる──。図1は財務省と日本銀行、国立印刷局が現在開発中の視覚障害者向けスマホアプリだ。2013年内に、iOS向けアプリとして無償公開予定という。
スマホやタブレットを利用した障害者向けのサービスやアプリが充実し始めている。カメラやマイクなどの機能を活用し、有益な情報を提供する。その一つが、iOS向けの無料アプリ「TapTapSee」(開発は米イメージサーチャー)。アプリを起動して写真を撮ると、それがアプリの開発元に送られ、何が写っているのかを音声で知らせてくれる。
例えば図2のような写真を撮ると、「机の上にある白い表紙の雑誌と黒のラップトップです」と驚くほど正確な答えが返ってくる。コンピューターによる画像解析だけでなく、クラウドソーシングによる“人力”も活用しているのが特徴だ。アクセシビリティコンサルタントで、弱視の視覚障害があるCocktailzの伊敷政英氏は「缶詰の種類を確かめる際などに便利」と話す。
■JR東日本が遠隔手話通訳サービス
JR東日本が2013年6月から試験導入した「遠隔手話通訳サービス」も、タブレットを活用する(図3)。駅の案内所などに設置したiPadを、遠隔地にいる手話通訳者と接続。手話による問い合わせを受けられるようにした。
筆談には従来から対応していたが、生まれつき聴覚障害がある人には、日本語を書くことが苦手な人も少なくないという。「手話と日本語では、文法をはじめ言語の性質が全く違う」(JR東日本が導入した遠隔手話通訳サービスを提供する、シュアールの大木洵人社長兼CEO)からだ。「筆談では伝えにくい複雑な内容も、手話ならスムーズに話せる」(JR東日本 鉄道事業本部 サービス品質改革部の山根木和也副課長)という利点がある。
アプリを使う以前に、そもそもスマホやタブレットは、障害者にとって便利な機能を標準で備えている(図4)。代表格が、iOSの音声読み上げ機能である「VoiceOver」。表示中のWebサイトの文字情報や、タップしたメニューの名称、ソフトキーボードのキーなどをその都度読み上げる。このため、全盲の人でも文字を入力したり、読んだりできる。
Android(アンドロイド)の場合も、富士通の「らくらくスマホ」など一部の機種で日本語の音声読み上げに対応する。それ以外の機種でも、KDDI研究所などが公開する音声読み上げアプリを利用できる。
一般向けに提供されている機能やアプリにも、有用なものが多い。iOSが搭載する「FaceTime」などのビデオ通話アプリは、遠隔地との手話に便利だ。手話通訳士の資格を持つシュアールの河野真衣氏は「電話が難しい聴覚障害者とも、手軽に話せる」と評価する。
前出の伊敷氏がフル活用するのは、iPadのカメラ機能(図5左上)。「時刻表などの小さな文字も、撮影して指で拡大すれば読めるようになる」(伊敷氏)。電子書籍アプリも便利という。「Kindle」などでは文字サイズを手軽に拡大可能で、拡大鏡がなくても読める(図5左下)。単純な画面拡大ではページ全体を読むのにスクロールが発生するが、Kindleでは文字サイズに応じて1ページの範囲に文字が再配置されるため、快適に読書できる。
全盲の人も、電子書籍ならそのまま音声読み上げができる。慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任助教で、視覚障害がある中根雅文氏によれば「これまでは、各ページをスキャンして光学式文字読み取り装置(OCR)で処理する苦労があった」という。電子書籍の普及で、その手間が激減した。
■患者にiPad活用を指導
その中根氏は、位置情報を基に他人と交流する人気SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)「foursquare」の情報を活用する(図5右)。対応アプリや音声読み上げ機能を組み合わせれば、現在地周辺にどんな店舗や名所があるかを把握できる。目的地にたどり着くためには必ずしも必要な情報ではないが、「こういう“どうでもいい”情報にどれだけ触れられるかが、人生の楽しみ。街歩きが楽しくなった」(中根氏)。
「生活が一変する」「革命的な変化が起こる」──。伊敷氏や中根氏は、スマホやタブレットの威力をこう表現する。今後求められるのは、これをさらに多くの人に広げるための工夫だ。
既に取り組みも進んでいる(図6)。最近では、「患者にiPad活用を指導する眼科医が増えている」(iPad活用に取り組む眼科医の三宅琢氏)という。
[日経パソコン2013年8月26日号の記事を基に再構成]-2013/9/27 7:00
スマホやタブレットを利用した障害者向けのサービスやアプリが充実し始めている。カメラやマイクなどの機能を活用し、有益な情報を提供する。その一つが、iOS向けの無料アプリ「TapTapSee」(開発は米イメージサーチャー)。アプリを起動して写真を撮ると、それがアプリの開発元に送られ、何が写っているのかを音声で知らせてくれる。
例えば図2のような写真を撮ると、「机の上にある白い表紙の雑誌と黒のラップトップです」と驚くほど正確な答えが返ってくる。コンピューターによる画像解析だけでなく、クラウドソーシングによる“人力”も活用しているのが特徴だ。アクセシビリティコンサルタントで、弱視の視覚障害があるCocktailzの伊敷政英氏は「缶詰の種類を確かめる際などに便利」と話す。
■JR東日本が遠隔手話通訳サービス
JR東日本が2013年6月から試験導入した「遠隔手話通訳サービス」も、タブレットを活用する(図3)。駅の案内所などに設置したiPadを、遠隔地にいる手話通訳者と接続。手話による問い合わせを受けられるようにした。
筆談には従来から対応していたが、生まれつき聴覚障害がある人には、日本語を書くことが苦手な人も少なくないという。「手話と日本語では、文法をはじめ言語の性質が全く違う」(JR東日本が導入した遠隔手話通訳サービスを提供する、シュアールの大木洵人社長兼CEO)からだ。「筆談では伝えにくい複雑な内容も、手話ならスムーズに話せる」(JR東日本 鉄道事業本部 サービス品質改革部の山根木和也副課長)という利点がある。
アプリを使う以前に、そもそもスマホやタブレットは、障害者にとって便利な機能を標準で備えている(図4)。代表格が、iOSの音声読み上げ機能である「VoiceOver」。表示中のWebサイトの文字情報や、タップしたメニューの名称、ソフトキーボードのキーなどをその都度読み上げる。このため、全盲の人でも文字を入力したり、読んだりできる。
Android(アンドロイド)の場合も、富士通の「らくらくスマホ」など一部の機種で日本語の音声読み上げに対応する。それ以外の機種でも、KDDI研究所などが公開する音声読み上げアプリを利用できる。
一般向けに提供されている機能やアプリにも、有用なものが多い。iOSが搭載する「FaceTime」などのビデオ通話アプリは、遠隔地との手話に便利だ。手話通訳士の資格を持つシュアールの河野真衣氏は「電話が難しい聴覚障害者とも、手軽に話せる」と評価する。
前出の伊敷氏がフル活用するのは、iPadのカメラ機能(図5左上)。「時刻表などの小さな文字も、撮影して指で拡大すれば読めるようになる」(伊敷氏)。電子書籍アプリも便利という。「Kindle」などでは文字サイズを手軽に拡大可能で、拡大鏡がなくても読める(図5左下)。単純な画面拡大ではページ全体を読むのにスクロールが発生するが、Kindleでは文字サイズに応じて1ページの範囲に文字が再配置されるため、快適に読書できる。
全盲の人も、電子書籍ならそのまま音声読み上げができる。慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任助教で、視覚障害がある中根雅文氏によれば「これまでは、各ページをスキャンして光学式文字読み取り装置(OCR)で処理する苦労があった」という。電子書籍の普及で、その手間が激減した。
■患者にiPad活用を指導
その中根氏は、位置情報を基に他人と交流する人気SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)「foursquare」の情報を活用する(図5右)。対応アプリや音声読み上げ機能を組み合わせれば、現在地周辺にどんな店舗や名所があるかを把握できる。目的地にたどり着くためには必ずしも必要な情報ではないが、「こういう“どうでもいい”情報にどれだけ触れられるかが、人生の楽しみ。街歩きが楽しくなった」(中根氏)。
「生活が一変する」「革命的な変化が起こる」──。伊敷氏や中根氏は、スマホやタブレットの威力をこう表現する。今後求められるのは、これをさらに多くの人に広げるための工夫だ。
既に取り組みも進んでいる(図6)。最近では、「患者にiPad活用を指導する眼科医が増えている」(iPad活用に取り組む眼科医の三宅琢氏)という。
[日経パソコン2013年8月26日号の記事を基に再構成]-2013/9/27 7:00