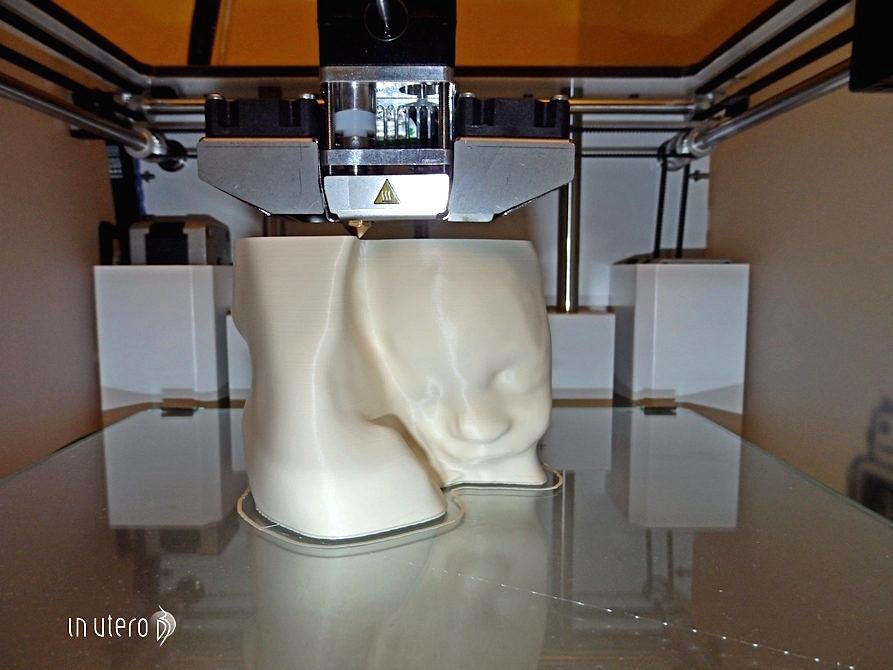障害者マークの乱立の行方、いったい誰のための何のためのマーク・・・?
透析歴29年の患者が代表を務め、腎臓病・透析患者向けポータルサイト「じんラボ」を運営する株式会社ペイシェントフッド(東京都世田谷区、代表取締役:宿野部武志)は、腎臓病・透析患者を対象に 『ヘルプマーク』 についてアンケート調査を行いました。
【調査概要】
『ヘルプマーク』とは、内部障害や難病の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人々が、配慮が必要なことを周囲に知らせることで援助を得やすくなるよう、東京都によって作成されたマークです。平成24年10月の導入から東京都は認知度向上、普及啓発活動に取り組み、4年を経過した現在では、4月から京都府が導入開始、平成28年度以降は青森県、徳島県、札幌市なども導入を検討するなど、日本全国へ拡大しつつあります。
しかし一方で、援助や配慮を必要としている方自身や、周りの方の認知度はまだまだ低いようです。透析患者は外見からは分かりづらい慢性疾患を抱えており、まさに周りから理解されにくいのですが、援助や配慮を必要としている内部障害者です。
そこで、腎臓病・透析患者のヘルプマークに対する認知度を調査し、現状の問題点等を検討するため、アンケートを実施しました。
◇調査方法:WEBアンケート
◇調査エリア:全国(内東京在住者27名:24.8%)
◇調査対象:腎臓病・透析患者・腎移植者 男女 年齢不問
◇調査期間:2016年8月1日~8月8日
◇有効回答数:109名(内透析患者90名:82.6%)
(1)あなたは3つのマークの違いが分かりますか (n=109)
※「障害者のための国際シンボルマーク」、「ハートプラスマーク」、「ヘルプマーク」を提示
知っている 37.6%
あまり知らない 47.7%
全く分からない 14.7%
ヘルプマークの画像3択クイズは正解率82.6%と高かったのですが、上記設問の3つのマークの違いについては、『知っている』と回答した方が37.6%。ヘルプマークは東京都が作成、4年前に導入しているため、上記回答を東京在住者に絞ってみたところ、「知っている」が55.6%と全国対象よりは18%高かったものの、マーク使用の対象者でありながら、認知度の低さが目立つ結果となりました。
記述回答の中には、「このアンケートで初めて知った」という意見も多く寄せられた『ヘルプマーク』ですが、現在、障害者を対象としたシンボルマークや標識が多数存在しているのも原因の一つではないでしょうか。
世界共通の『障害者のための国際シンボルマーク』は、すべての障害者を対象としていますが、「車いす使用者個人を表している」と誤解されていることが多いようです。障害の中には心臓や呼吸器、腎臓など身体内部の機能障害があり、長時間の立位維持が困難な方や日常生活に大きな支障があり、援助や配慮を必要とされている方が大勢います。そんな、外見からでは分からない内部障害や難病の方などが、援助や配慮を周囲に知らせるためのマークとして、2012年に『ヘルプマーク』が東京都より導入されましたが、実はほぼ同じ意味合いを持つマークとして、10年以上も前から『ハートプラスマーク』があります。当時これに類似したものはなく、多くの地方自治体が同マークを啓発し、内閣府の障害者白書にも掲載されています。
上表一覧の障害者マークはほんの一部であり、地方自治体や各障害者団体等が独自に作成・提唱を行っている障害者マークも多数あります。これらのマークは対象者、利用方法、マークの示す意味、帰属団体などはバラバラで、まったく同じ目的なのに、都道府県によってマークが異なることも少なくありません。これだけ乱立した多種多様な障害者マークをいったいどれだけの人が認識しているのでしょうか。
同じ目的なのにマークだけが次々と制作され、マークの普及活動が活発化した背景には、2016年4月に施行された「障害者差別解消法 」により、障害者に対し「合理的配慮(※)」を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようになったことがあるといえます。
善意から生まれたマークのはずが、これだけ乱立すれば一般の人はもちろん、対象障害者ですらその意味を認識出来なくなるのは当然です。障害者を援助するどころか、かえって混乱をきたしているのではないでしょうか。
本アンケートの障害者マークに対する要望・意見の記述回答の中で、「マークの認知度を向上してほしい」と、多くの方が切願されていましたが、「内部障害の理解を深めてほしい」という意見も多数寄せられました。
見た目は健常者と変わらないため、誤解されたり、危険にさらされるなど、社会生活をする上で多くの不便を抱えている内部障害者。
「なぜ内部障害者が援助や配慮を必要とするのか」
1)障害に対する理解を深める活動
2)同じ目的のマーク全国統一化
3)マークの認知度向上の活動
本当に障害者マークを根付かせるためには、この3つが重要だと考えます。
援助する側、される側、双方がマークの真意を正しく理解し、助け合える社会となるよう、マークのあり方を今一度見直すことが必要です。
(※)合理的配慮とは、障害の有無を問わず、社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や
社会的障壁の除去が求められる場面に応じて合理的な範囲で行われる配慮のこと

株式会社ペイシェントフッド !2016年9月1日