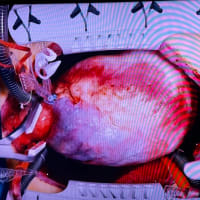昨年宇都宮で開催された日本臨床外科学会でのテーマは「地域に外科を」という主催の自治医大らしいフレーズになっており、その中のシンポジウムでへき地の医療を経験した後に心臓血管外科の世界に入った筆者にシンポジストの依頼がきました。この時の内容抄録をいかに提示します。最後に述べているとおり、なんでも情熱をもって飛び込むことが次につながる、ということです。
私は自治医科大学卒業後に秋田県の僻地病院に卒後3~8年目の6年間勤務した。外科医としての5年間、執刀可能な手術は胃・腸切、胆摘、アッペ、ヘルニアに限られ、自家麻酔で実施。安全性担保にこのレベルが適切と判断していた。他病院で手術研修させてもらう機会はモチベーション維持に役立ったが、見学をいくら重ねても自分の経験にはならず、自ら担当医として責任を伴って経験することこそが、意味のある修練と実感した。現在、見学だけならインターネットの情報で充分かもしれない。それより、都会では経験できない僻地ならではの医療をたくさん経験することこそが、その後の集中した外科トレーニングにおいて、医師個人の特技や武器として役立つことになる。多くの特殊な外傷治療経験に加えて、へき地では内科医としての仕事が主になりがちで、超音波検査を多く経験した。それに関連し、一般住民検診に合わせて腹部エコーによる腹部大動脈瘤健診を、研究費助成を得て実施した。この結果は、英文誌に投稿して掲載され、その後の心臓血管外科修練開始後に大学で同期入局者よりも先んじて助教に昇進させてもらい、より多くの術者経験を得るのに役立った。地域保健診療や、一見、外科とは無関係の経験がその後の心臓外科医としての修練に役立ったと実感している。共通しているのは、いずれも情熱を持って現場に飛び込んでいく精神が次の結果をもたらすということだ。