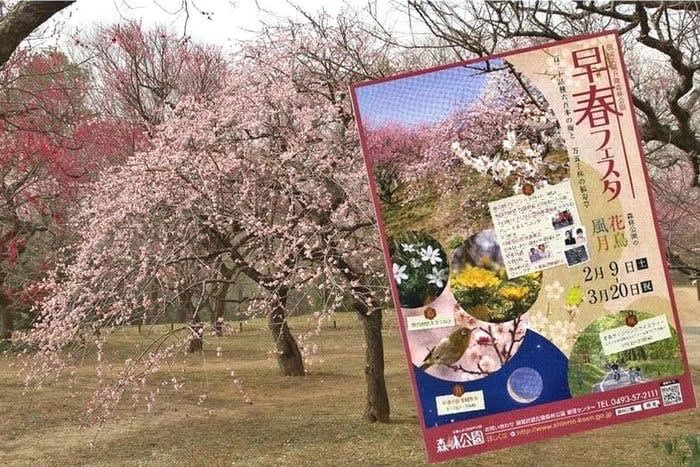《 心をゆさぶる万葉の歌 》
『万葉集』は1300年前の日本人の飾らぬ想いと言葉を集めた歌集で、古代文化が花開いた奈良時代に編さんされました。
作者は天皇から庶民まで幅広い階層に渡っています。読まれた歌は、4500首余りで世界に誇れる最高の文化遺産です。
《 よめなかった『万葉集』 》
『万葉集』の歌は仮名文字がなかった時代に、全て漢字で表現されております。日本語を音(おと)で表わした万葉仮名(まんようかな)や
漢字の音読み、訓読みが組み合わされ、さらに仏教の悉曇文字(しったんもじ)まではいっていたた め 大変むずかしいものでした。
奈良時代中期、大伴家持(おおとものやかもち)の「あたらしき年の始めの初春の 今日降る雪のいやしき吉事(よごと)」の歌でしめくくら
れて完成した『万葉集』ですが、仮名文字が定着した平安時代の初めにはすでに読めなくなっておりました。
《 仙覚の偉業 》
現代の私たちが感情豊かな万葉の歌を読むことができるのは、鎌倉時代に『万葉集』の研究に一生をささげ、万葉学の基礎を築いた仙覚の偉業によるものです。
《 仙覚の新点 すべての歌を読む 》
鎌倉時代の学僧仙覚は、13歳から取り組んできた万葉集の研究成果をもとに、漢字の歌のすぐ脇にカタカナで訓点(くんてん)を書き記して
全てを読み解きました。このことに付けられた訓点を「仙覚の新点(しんてん」と呼びます。これにより難解で全く読むことのできなかった
152首の歌を含め、全20巻の歌が読めるようになり、生涯に少なくとも3度に渡り『万葉集』を校訂し、『万葉集』の校訂本(写本)を完成させました。
《 小川町で「万葉集注釈」完成 》
仙覚が、万葉歌を読み解いたのちに取り組んだのが、難解な歌の解読でした。それが我国で初めての解読書となった『万葉集注釈』です。
1269年(文永6年)、現在の小川町域「麻師宇郷(ましうごう)」でなしとげられました。仙覚67歳のときです。仙覚抄と呼ばれる『万葉集注釈』
第二巻の奥書に、文永6年3月2日「武蔵国比企郡北方麻師宇郷」で書写したとあります。さらに第6巻と10巻には麻師宇郷の「政所(まんどころ)」で
書写したと明記してあり、仙覚は麻師宇郷を管理する領主の館(やかた)にいたことがわかります。これは、仙覚と小川町の関係を示す貴重な史料で、
小川町が仙覚を通して『万葉集』ゆかりの地であることを物語っています。
(「第5回おがわ仙覚万葉まつり」パンフレットから抜粋)

そんな仙覚律師=万葉集と関係の深い小川町において、本日16日、「第5回おがわ仙覚万葉まつり」が開催され、
仙覚万葉ウォークが行われましたので参加してきました。
写真は、会場である町民会館外のステージにおいて、和紙で作られた古代衣裳姿で挨拶する小川町長。
このあと、万葉モニュメントと仙覚律師顕彰碑等を訪ねる仙覚万葉ウォークに・・・

仙覚万葉ウォークが始まりました

左前方の丘が、仙覚律師顕彰碑が建立されている中城跡(八幡台・陣屋台)

仙覚律師顕彰碑の前で、古代衣裳姿の参加者の記念撮影

参加者全員(と言っても私を含む数人は入っていませんが)での記念撮影。参加者の中に私の知り合いはひとりもいませんでした・・・

郷土史研究家(?)の方が色々と説明してくれました

甘酒がふるまわれました

仙覚律師顕彰碑が建立されている中城跡の空堀
この中城は、鎌倉時代、猿尾(ましお)太郎直種が築き室町期には、斎藤六郎尉重範の居城し
近世の元禄元年 旗本金田丹波守の陣屋がおかれたと伝えられているそうです。
このことから、いまでもここを「陣屋」あるいは「陣屋台」と地元の人は呼んでいます

続いて「仙覚万葉展」を開催中の町立図書館へ

仙覚万葉に関する資料がパネルになって展示されています。貴重な史料も特別展示されていました。
ここでも郷土史研究家(?)の方の説明があり、大変勉強になりました。
このあとも仙覚万葉ウォークは続いたのですが、私は所用がありコースからはずれて出発点まで戻りました。
散策日:2013年(平成25年)3月16日(土)