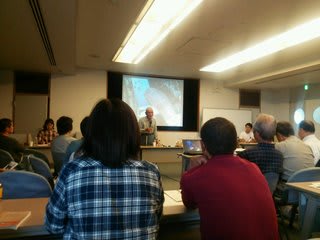10月4日、講演会「大沢の自然と私のしいたけづくり」(主催:講演会実行委員会、楽農クラブ・後援:島本町農業振興団体協議会、フリーペーパー「しまもとノート」)に参加、原木しいたけづくり70年、地元のしいたけ農家のSさん(88歳)のお話をお聴きしました。
原木栽培に興味のあるひと、島本の自然に関心あるひと、まちの話を聴きたいひと、70人近くの方が会場の島本町ふれあいセンター第4学習室に集まっておられました。高槻市の原や亀岡市などからの参加もあり、正直、驚きました。丁寧な準備、広報、そしてなにより伝えたいという主催者の思いがあってこその成功です。
S氏さんは「キノコの慈父」と呼ばれる故森喜作博士(桐生市出身)がつくられた「森友の会」の全国組織副会長を務められ、全国各地で後援活動、後進の指導にあたられてきたそうです。しいたけの原木栽培では有名な方なのだそうです。「
わたくしごとになりますが、足利市にある夫の生家は桐生市に近く、義母は桐生出身、原木栽培に世界ではじめて成功した偉人・ドクター森の存在を知らない人は地元にはいない、とかねてより聞き及んでいました。
桐生のしいたけ栽培と大沢のしいたけ栽培のつながりを思うと嬉しいですが、残念なことに、今や日本のシイタケ生産量の90%が菌床栽培となっているとのことです。多くの人が原木栽培の味を知らず、また島本町民のほとんどがS氏のしいたけの味を知る機会に恵まれません。
近年は、毎週火曜と木曜の朝(9時~なくなり次第)にJR島本駅前の歴史文化資料館前庭で開かれる朝市に出されていますが、今も栽培を続けておられるのはSさんのみ。数には限りがあります。島本で原木栽培を絶やさない、そういう思いで今日の講演会を引き受けましたとSさんはおっしゃいました。
島本の大沢地区でしいたけの原木栽培でやっていくのだ、と決められた不退転の決意。山桜の葉の色が変わる頃合いや月の満ち欠けに寄り添って原木や菌と向きあい、皮を撫でただけで菌のひろがり具合がわかると言う「山の人」。「ひと」に魅せられた講演会でした。
原木栽培に興味のあるひと、島本の自然に関心あるひと、まちの話を聴きたいひと、70人近くの方が会場の島本町ふれあいセンター第4学習室に集まっておられました。高槻市の原や亀岡市などからの参加もあり、正直、驚きました。丁寧な準備、広報、そしてなにより伝えたいという主催者の思いがあってこその成功です。
S氏さんは「キノコの慈父」と呼ばれる故森喜作博士(桐生市出身)がつくられた「森友の会」の全国組織副会長を務められ、全国各地で後援活動、後進の指導にあたられてきたそうです。しいたけの原木栽培では有名な方なのだそうです。「
わたくしごとになりますが、足利市にある夫の生家は桐生市に近く、義母は桐生出身、原木栽培に世界ではじめて成功した偉人・ドクター森の存在を知らない人は地元にはいない、とかねてより聞き及んでいました。
桐生のしいたけ栽培と大沢のしいたけ栽培のつながりを思うと嬉しいですが、残念なことに、今や日本のシイタケ生産量の90%が菌床栽培となっているとのことです。多くの人が原木栽培の味を知らず、また島本町民のほとんどがS氏のしいたけの味を知る機会に恵まれません。
近年は、毎週火曜と木曜の朝(9時~なくなり次第)にJR島本駅前の歴史文化資料館前庭で開かれる朝市に出されていますが、今も栽培を続けておられるのはSさんのみ。数には限りがあります。島本で原木栽培を絶やさない、そういう思いで今日の講演会を引き受けましたとSさんはおっしゃいました。
島本の大沢地区でしいたけの原木栽培でやっていくのだ、と決められた不退転の決意。山桜の葉の色が変わる頃合いや月の満ち欠けに寄り添って原木や菌と向きあい、皮を撫でただけで菌のひろがり具合がわかると言う「山の人」。「ひと」に魅せられた講演会でした。