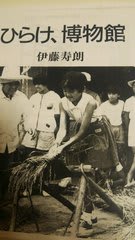個別自衛権があれば、万一、日本が攻撃を受けたとき防衛できるはず。それなのに安倍政権は、なぜ集団的自衛権に固執するのでしょうか。
「集団的自衛権」行使には、「必要最小限」であろうがなかろうが「宣戦布告」が国際法上不可欠であるとのこと。
そこで、インターネットの検索機能に「集団的自衛権」「宣戦布告」と入力してみると
第三国が集団的自衛権を行使するには、宣戦布告を行い中立国の地位を捨てる必要があると書かれていました。「宣戦布告」すれば「戦争」です。
宣戦布告を行わないまま集団的自衛権を行使することは、戦時国際法上、違反になるとのこと。「布告」なきまま、戦争の当事者になることなど許されません。
国際法上、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」はその行使に「宣戦布告」がいるかいらないかで決定的に違うそうです。
第9条は「国権の発動たる戦争」と「国の交戦権」を否定しています。だから「宣戦布告」はできないことになります。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「国の交戦権は、これを認めない。」(日本国憲法第9条)
いくら屁理屈こねても、集団的自衛権は憲法違反。政権の閣議決定で、一度、集団的自衛権を容認してしまったら、憲法九条を改正したのと同じ結果になってしまいます。
解釈憲法を許してしまえば、法ではなく「政治家による支配」となり、これを国際社会では独裁と呼びます。
画像
過日、兵庫県立芸術文化センターで二人芝居
「請願」~核のない世界~を鑑賞
物語の縦軸は
女性が人として自らの思想をもって生きること
三田和代さんの見事な演技に感動
「集団的自衛権」行使には、「必要最小限」であろうがなかろうが「宣戦布告」が国際法上不可欠であるとのこと。
そこで、インターネットの検索機能に「集団的自衛権」「宣戦布告」と入力してみると
第三国が集団的自衛権を行使するには、宣戦布告を行い中立国の地位を捨てる必要があると書かれていました。「宣戦布告」すれば「戦争」です。
宣戦布告を行わないまま集団的自衛権を行使することは、戦時国際法上、違反になるとのこと。「布告」なきまま、戦争の当事者になることなど許されません。
国際法上、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」はその行使に「宣戦布告」がいるかいらないかで決定的に違うそうです。
第9条は「国権の発動たる戦争」と「国の交戦権」を否定しています。だから「宣戦布告」はできないことになります。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「国の交戦権は、これを認めない。」(日本国憲法第9条)
いくら屁理屈こねても、集団的自衛権は憲法違反。政権の閣議決定で、一度、集団的自衛権を容認してしまったら、憲法九条を改正したのと同じ結果になってしまいます。
解釈憲法を許してしまえば、法ではなく「政治家による支配」となり、これを国際社会では独裁と呼びます。
画像
過日、兵庫県立芸術文化センターで二人芝居
「請願」~核のない世界~を鑑賞
物語の縦軸は
女性が人として自らの思想をもって生きること
三田和代さんの見事な演技に感動