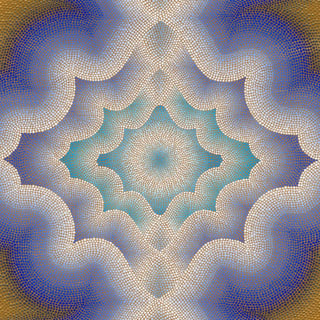毎日新聞 2025/2/12 14:54(最終更新 2/12 14:54)
2025年版自動車産業の環境・人権への影響評価を発表
(東京、日本)本日発表されたリード・ザ・チャージ(Lead the Charge)の第3回年次「自動車産業の環境・人権への影響評価ランキング(リーダーボード)」において、トヨタ、日産自動車、本田技研工業(Honda)は、18のグローバル自動車メーカーの中で特に進展が遅れていることが明らかとなった。本ランキングは、自動車メーカーが電気自動車(EV)への移行に伴う公正で持続可能かつ化石燃料に依存しないサプライチェーンの構築に向けた取り組みを評価するものである。今年、日本の自動車メーカーはいずれも、気候と環境の部門において大幅な向上が見られず、気候対策に後れを取っている企業という位置づけが一層強まっている。
今年の分析では、一部の自動車メーカーが特定の分野で進展を見せたものの、業界全体としては進捗が遅く、サプライチェーン全体における環境・人権への影響は未だ大きな課題があることが明らかとなった。3年連続で、いずれの自動車メーカーも総合スコア50%を超えることができず、全体の平均スコアもわずか22%にとどまっている。
トヨタ、日産自動車、本田技研工業(Honda)の日本勢3社は最も低い評価を受け、スコアの上昇幅も最小にとどまった。トヨタとHondaは人権デュー・ディリジェンスの面では一定の進展を見せたものの、いずれの企業もサプライチェーンの持続可能性や脱炭素化のスコアを向上させることはできなかった。特にトヨタは、2023年以降に評価された企業の中で、この分野のスコアが一切向上していない唯一の企業となっている。
この包括的な分析では、1,584のデータポイントを基に、88の指標に沿って各社のサプライチェーンにおける気候、環境、人権への取り組みを評価している。ランキングの評価は、企業の取締役会レベルで承認された公開情報を基に分析を行っている。なお、本分析に反映された企業の情報開示の締切日は、2024年7月1日である。
今年のリーダーボードでは、テスラ、フォード、メルセデス・ベンツの3社が僅差で上位争いを繰り広げた。最終的にテスラが首位となり、フォードを0.5ポイント、メルセデス・ベンツを1.4ポイント上回る結果となった。テスラは、サプライチェーンの詳細なマッピング情報や鉱業サプライヤーとの直接調達契約の開示など、透明性向上の取り組みを進めおり、鋼材、アルミニウム、バッテリーのサプライチェーンに関するスコープ3排出量を詳細に開示している唯一のメーカーである。しかし、総合スコアは43%にとどまり、鋼材・アルミニウムの脱炭素化、労働者の権利といった分野では依然として課題が残っている。
アースワークス(Earthworks)の暫定採掘共同ディレクター、エレン・ムーア氏は次のように述べた。
今年のランキング結果は明確である。一部の自動車メーカーが強固な方針やコミットメントを掲げているが、実施段階で大きく遅れを取っている。しかし、改善は可能である。他社の成功事例から学び、各指標におけるベストプラクティスを取り入れることで、公正なサプライチェーン、責任ある調達、そして公正な移行を実現できる
主な評価結果(ランキングはこちら)
- ボルボは最も大きく前進し、総合スコアが9ポイント上昇した。 全8区分のうち7つでパフォーマンスを改善し、特に気候および環境の部門では最大のスコア向上を記録した。現在、ボルボのスコアは業界平均の2倍以上に達している。
- テスラは首位であるものの、その立場は不安定である。 同社の政策チームの取り組みにより、2024年の気候対策のロビー活動が好意的に評価され、今年のスコア向上の大きな要因となった。しかし、最近の報道ではテスラが米国でのEV税額控除の廃止を支持していることが指摘されており、こうした好意的な評価を維持できなければ、来年トップの座を失う恐れがある。
- フォードは、人権および責任ある調達の部門で3年連続の最高評価を獲得した。 一方、メルセデス・ベンツは、リーダーボードの全8区分でトップ5入りした唯一の自動車メーカーとなった。
- 中国の吉利汽車(Geely)は2年連続で大幅なスコア向上を達成し、サプライチェーンの持続可能性や責任ある調達の面での前進が際立った。また、起亜自動車(Kia)とフォルクスワーゲンも大きなスコア改善を果たしている。
今年のリーダーボードでは、自動車のサプライチェーンの持続可能性に関するいくつかの重要な傾向が浮き彫りになった。 特に、鋼材・アルミニウムの脱炭素化に関しては、憂慮すべき状況を示している。昨年、多くの自動車メーカーが大きな前進を遂げたものの、今年はほぼ停滞しているのが実情である。鋼材・アルミニウムはEVのサプライチェーン全体の排出量の約50%を占めており、自動車業界はこれらの材料の主要な消費者となっている。
スティールウォッチのアジア担当、ロジャー・スミスは次のように述べた。
石炭を使わずに高品質な鉄鋼を生産する技術はすでに確立されている。しかし、需要が高まらなければ、日本製鉄のような企業は石炭拡張計画の見直しが急務だとは考えないだろう。日本企業がわずかな排出削減で乗り切れると考えているかもしれないが、リーダーボードは、実際には自動車メーカーも鉄鋼メーカーも競争相手に大きく後れを取るリスクを抱えていることを示している
また、パブリックシチズン(Public Citizen)の気候プログラムのシニア・サプライチェーン・キャンペーナー、カーリー・オボス氏は次のように述べた。
自動車業界が、温室効果ガスを排出しない鋼材・アルミニウムの確保に向けた進展をほとんど見せていないのは、非常に憂慮すべき状況である。鋼材・アルミニウムの製造は、世界の温室効果ガス排出量の約10%を占めており、自動車メーカーが行動しない理由はない。もはや生ぬるい対応ではなく、低排出サプライチェーンの実現に向けた真のコミットメントが求められている
ソリューションズ・フォー・アワー・クライメート(Solutions for Our Climate)のグリーンスチール担当、ヘザー・リー氏は次のように述べた。
現代自動車グループは、自動車メーカーと鉄鋼メーカーの両方を抱える企業グループとして、特に鉄鋼生産においてサプライチェーンの脱炭素化を推進する大きな可能性を持っている。しかし、この分野で明確な進展が見られないのは非常に残念である。現代自動車の将来的な競争力を確保するためにも、現代製鉄はサプライチェーンのクリーン化を進め、グリーンスチールの生産を加速させる必要がある
一方、先住民族の権利に関しては業界全体でほぼ2年間ほとんど進展が見られなかったものの、昨年はこの問題への関心が高まりつつある兆しが見られた。複数の企業が新たなコミットメントを発表し、既存の取り組みを強化する動きが見られた。しかし、全体の平均スコアはわずか6%にとどまり、この分野は依然として最も低い評価を受けている。
サージ・コーリション(SIRGE Coalition)のエグゼクティブ・ディレクター、ガリーナ・アンガロワ氏は次のように述べた。
先住民族の権利を尊重するための方針を採用し始めた企業が複数あることを評価し、これらの方針がサプライチェーン全体で確実に実施されることを期待する。しかし、業界全体では依然として先住民族の基本的権利が軽視されている現状を深く懸念している。すべての自動車メーカーは、単なる認識の段階を超え、これらの権利を守るための具体的な行動を直ちに起こす必要がある
今年の評価結果は、サプライチェーンの持続可能性やデュー・ディリジェンス、EV製造に関して企業のパフォーマンス向上を促してきた政策立案者や規制当局にとって、励みとなるメッセージとなった。特に、今年最も大きな進展が見られたのは、欧州バッテリー規則や企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)など、最近承認された政策や規制によって重点的に取り組まれてきた分野である。これは、現在弱体化の危機にあるCSDDDをはじめとするEUの厳格な説明責任に関する法律が、いかに重要であるかを改めて示している。こうした措置が損なわれれば、これまでの前進が失われ、変革への有望な道筋が断たれる恐れがある。
T&Eの原材料担当、フランツィスカ・グルーニング氏は次のように述べた。
今年のリーダーボードの結果は、自動車メーカーがEUの先進的な法律のもとで、持続可能なサプライチェーンの取り組みをどのように進めているかを示している。欧州バッテリー規則は、持続可能な供給網に向けた確かな道筋を示しており、CSDDDのような法律も、これまでの重要な進展を損なわないよう、現状のまま維持される必要がある
全体的な進展は遅いものの、今年の結果からは業界がより良い成果を達成できる可能性も見えてくる。指標の半数以上は、少なくとも1社が完全に満たしており、各社が異なる分野で最も優れた競合他社の取り組みを取り入れれば、スコアを70%以上に引き上げることができる。先進企業のベストプラクティスを他の企業が採用すれば、大きな改善の余地がある。
シエラクラブ(Sierra Club)のClean Transportation for All campaignのディレクター、キャサリン・ガルシア氏は次のように述べた。
リーダーボードは、自動車業界が不可避なEV移行に向けて投資を進める中で、サプライチェーンのクリーン化にどれだけ取り組んでいるかを問うものであるが、各社にはまだ多くの課題が残されていることが明らかである。現在、自動車の排出基準によって、スコアカードの上位企業ではEV市場の拡大が進んでいる。しかし今回も、世界最大の自動車メーカーであるトヨタがランキングの最下層となり、スコアカードの初版から一切改善が見られていない。気候危機の最悪の事態を防ぐためには、すべての自動車メーカーがEV生産のスピードを加速させる必要がある。時間は限られている
リード・ザ・チャージ(Lead the Charge)について
リード・ザ・チャージは、公正で持続可能、かつ化石燃料に依存しない自動車のサプライチェーンの実現を目指す、地域、国、世界の多様なアドボカシーパートナーのネットワークである。メンバーは、気候変動、環境正義、人権、先住民族の権利、重工業、ESGなど幅広い分野の専門知識を持ち、様々な地域や課題に取り組んでいる。
スティールウォッチ(SteelWatch)について
スティールウォッチは、鉄鋼セクターにおける気候変動対策を促進することを目的とし、2023年7月に設立された国際NGO。「ゼロエミッション経済を支え、そして環境や地域が栄え、労働者が生き生きと暮らすことを可能にする鉄鋼産業」をビジョンに掲げている。
https://mainichi.jp/articles/20250212/pr2/00m/020/402000c