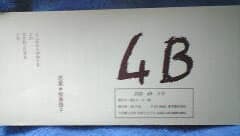
芥川賞を受賞した黒田夏子は、人称代名詞を使わないことで、人称の曖昧さ、交換可能性を示していた。あるいは、人称代名詞化されないものを示すという逆のベクトルもあったのかもしれない。でも、一方で固有名詞も避けていたわけだから、やっぱり名詞の名状しがたさの捉え直しから始めようとしていたのかもしれない。
あっ、別のところにはまり込まないように、人称代名詞に限って考える。現代詩は、おそらく、確立されたかのような人称への疑いを早くから持っていて、一人称や一人称複数との葛藤を詩史に刻んでいるのだと思う。
が、一方で、葛藤という近代的な様相ではなく、もっと自在に自身を何ものかにしてしまう「自由」を詩において実践できる人たちもいて、そこでは、むしろ使われる人称の指し示すものの方が入れ替わるのだ。それを、あっさり何ものかになっちゃうことでやるか、鏡像現象のようにして、まなざす行為でやるか。
中井さんの詩は、見られることでの自己の確認ではなく、見るー見られるの関係の移行に存在の入れ代わりが映し込まれるのだ。
と、そんな能書きよりも、中井さんの詩の魅力は、こちらをすいと中井さんの風景の中に連れだして、おまけに置き去りにしてくれることで、そこから、じわりと沁みだしてくる感慨が、切な哀しく、なつかし温かいところだ。それは、当然のようによぎるような怖さも秘めていて。
と、またまた、そんな能書きよりも、詩「家」の魅力的な第一連。
日暮れの向こうの
裏道にふらりとはいった
あっ、と引き込まれてしまう。「日暮れの向こう」なのだから、夜の側なのだ。それは理解。ただ、夜の裏道ではなく、「日暮れ」と書かれることで、夜との境が見えてくる。日暮れという言葉が、日暮れの残照を示すのだ。また、「向こう」は距離も示している。日の暮れる向こう側という場所を告げてもいるのだ。だから、逆光で夕暮れが視界に入ってくる。そして、また、そこには、言葉としてあって、今、実際には無いものが書き記される。
生垣深くに確かにあった
瓦屋根の家が
すとんと消えている
そこにある空白。同時に、あったはずの時間の出現。無くなった何かに連れていかれるのは案外あっさりとした言葉によってなのだ。そして、関係を一行一連で表す。
よそよそしさが好きだった
いろいろな読みがすでにきっかけを待っている。消えた家の持つ「よそよそしさ」なのだろう。しかし、それは、主人公の過去の時間の中で感じ続けていた「よそよそしさ」でもある。つまり、主人公が持っていた「違和感」なのかもしれない。では、この「家」は何者が住む家なのか。昔の私の家。私が暮らした家の近所の家。あるいは、彼の家。
門の前でふと目があって
互いに目をそらしたことがある
勝手に母のイメージが浮かぶ。かつての私が私の家族と暮らした家か。だが、目をそらした「互い」とは私と私なのかもしれない。
ゆっくり開き戸を
閉めた人影が消え落ちていく
いいなと思う。「人影が消え落ちていく」。この存在感のバランスがいい。「日暮れ」とも呼応しているし、「開き戸」と「閉めた」の呼応もいいなと思う。そして、
くずれた石段の柵のなか
ぽそりと一本の杉の木が立っていて
乾いた土には
ヨモギやハコベが繁殖している
ここで時間の経過を告げる。だから、消え落ちた人影の一端が、時間の向こう側に行ってしまったことがわかる。今の時間が戻ってくるのだ。意識の揺れが、詩の時間を柔らかに揺らす。その、今と過去の時間をつなぎ、ふたたび時を遡行するために次の一行が来る。
草の風がひと吹きした
風を吹かす。それは同時に、「開き戸」を、過去の「開き戸」をなでる。
開き戸のきしむ音に
振り返る
人影も振り返っている
「消え落ちていく」人影が、ふたたび像を結ぶのだ。「振り返る」が「きしむ音」に振り返る者と振り返る「人影」の両方に掛かる。また、「振り返る」時間にも掛かっている。第四連の「門の前でふと目があって/互いに目をそらしたことがある」を変奏させている。そして、最終連は、こう表現される。
裏がえったわたしになって
杉の木の枝でひらひらゆれている
(「家」全篇)
ここで初めて「わたし」という言葉が書き記される。「裏がえったわたし」として。すると、この「家」にいたのは「わたし」なのだろうか。過去の「わたし」であると同時に、生きられなかった別の時間を生きているかもしれない「わたし」なのかもしれない。過去もすでに「過去」という架空のものになりながら、「今」という時間に出会う。「わたし」が見るのは、木の枝で「ひらひらゆれている」わたしであり、そこに時間の描きだした物語の一切が、切れ切れに宿っているのかもしれない。
いくつもの読みの可能性を秘めている表現は、それ自体魅力的で、結局、その中から、どんな読みをしてしまうのか。「家」の住人を誰にするかで、いくつかの物語を紡ぎ出してしまう詩かもしれない。けれど、ボクは、やはり、「わたし」に出会う「家」だと思った。
あっ、別のところにはまり込まないように、人称代名詞に限って考える。現代詩は、おそらく、確立されたかのような人称への疑いを早くから持っていて、一人称や一人称複数との葛藤を詩史に刻んでいるのだと思う。
が、一方で、葛藤という近代的な様相ではなく、もっと自在に自身を何ものかにしてしまう「自由」を詩において実践できる人たちもいて、そこでは、むしろ使われる人称の指し示すものの方が入れ替わるのだ。それを、あっさり何ものかになっちゃうことでやるか、鏡像現象のようにして、まなざす行為でやるか。
中井さんの詩は、見られることでの自己の確認ではなく、見るー見られるの関係の移行に存在の入れ代わりが映し込まれるのだ。
と、そんな能書きよりも、中井さんの詩の魅力は、こちらをすいと中井さんの風景の中に連れだして、おまけに置き去りにしてくれることで、そこから、じわりと沁みだしてくる感慨が、切な哀しく、なつかし温かいところだ。それは、当然のようによぎるような怖さも秘めていて。
と、またまた、そんな能書きよりも、詩「家」の魅力的な第一連。
日暮れの向こうの
裏道にふらりとはいった
あっ、と引き込まれてしまう。「日暮れの向こう」なのだから、夜の側なのだ。それは理解。ただ、夜の裏道ではなく、「日暮れ」と書かれることで、夜との境が見えてくる。日暮れという言葉が、日暮れの残照を示すのだ。また、「向こう」は距離も示している。日の暮れる向こう側という場所を告げてもいるのだ。だから、逆光で夕暮れが視界に入ってくる。そして、また、そこには、言葉としてあって、今、実際には無いものが書き記される。
生垣深くに確かにあった
瓦屋根の家が
すとんと消えている
そこにある空白。同時に、あったはずの時間の出現。無くなった何かに連れていかれるのは案外あっさりとした言葉によってなのだ。そして、関係を一行一連で表す。
よそよそしさが好きだった
いろいろな読みがすでにきっかけを待っている。消えた家の持つ「よそよそしさ」なのだろう。しかし、それは、主人公の過去の時間の中で感じ続けていた「よそよそしさ」でもある。つまり、主人公が持っていた「違和感」なのかもしれない。では、この「家」は何者が住む家なのか。昔の私の家。私が暮らした家の近所の家。あるいは、彼の家。
門の前でふと目があって
互いに目をそらしたことがある
勝手に母のイメージが浮かぶ。かつての私が私の家族と暮らした家か。だが、目をそらした「互い」とは私と私なのかもしれない。
ゆっくり開き戸を
閉めた人影が消え落ちていく
いいなと思う。「人影が消え落ちていく」。この存在感のバランスがいい。「日暮れ」とも呼応しているし、「開き戸」と「閉めた」の呼応もいいなと思う。そして、
くずれた石段の柵のなか
ぽそりと一本の杉の木が立っていて
乾いた土には
ヨモギやハコベが繁殖している
ここで時間の経過を告げる。だから、消え落ちた人影の一端が、時間の向こう側に行ってしまったことがわかる。今の時間が戻ってくるのだ。意識の揺れが、詩の時間を柔らかに揺らす。その、今と過去の時間をつなぎ、ふたたび時を遡行するために次の一行が来る。
草の風がひと吹きした
風を吹かす。それは同時に、「開き戸」を、過去の「開き戸」をなでる。
開き戸のきしむ音に
振り返る
人影も振り返っている
「消え落ちていく」人影が、ふたたび像を結ぶのだ。「振り返る」が「きしむ音」に振り返る者と振り返る「人影」の両方に掛かる。また、「振り返る」時間にも掛かっている。第四連の「門の前でふと目があって/互いに目をそらしたことがある」を変奏させている。そして、最終連は、こう表現される。
裏がえったわたしになって
杉の木の枝でひらひらゆれている
(「家」全篇)
ここで初めて「わたし」という言葉が書き記される。「裏がえったわたし」として。すると、この「家」にいたのは「わたし」なのだろうか。過去の「わたし」であると同時に、生きられなかった別の時間を生きているかもしれない「わたし」なのかもしれない。過去もすでに「過去」という架空のものになりながら、「今」という時間に出会う。「わたし」が見るのは、木の枝で「ひらひらゆれている」わたしであり、そこに時間の描きだした物語の一切が、切れ切れに宿っているのかもしれない。
いくつもの読みの可能性を秘めている表現は、それ自体魅力的で、結局、その中から、どんな読みをしてしまうのか。「家」の住人を誰にするかで、いくつかの物語を紡ぎ出してしまう詩かもしれない。けれど、ボクは、やはり、「わたし」に出会う「家」だと思った。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます