
1966年発行の小説である。『されど われらが日々』が64年の発行である。柴田翔が35年生まれらしいから、この二作品、29歳から31歳ごろの作品。青春への作者の思いと若さということの現れと時代への鎮めるようなまなざしが込められた一編かもしれない。生きることを律しながら、自由であろうとする潔癖と未熟の混在。観念と生活の絡まるような関係が、越えがたい壁として自由を束縛していくことになる実人生の中での存在の意味づけの難しさ。それを難しさとして抱え込む精神の時期。どうにかして存在忘却から逃れようとしながら、逆に報復されるように観念が、その価値観が抑圧を生みながら、無力感と空虚を露呈させる無惨さが、青春小説として描かれる。青春とは悔いと鎮魂と、そして傷つきやすさを、感傷のオブラートに包み込むものなのかもしれない。しかし、ここでは、その観念が暴力を拒む方向で抗っている。倫理的潔癖さを守ろうとすることと、自分を他人に投影することへの激しいためらいがある、そのことが、結果として、お互いを傷つけてしまったとしても。そこに、何か、現在の事件との距離を感じる。自己と向き合うことと他者と触れあうことの葛藤を、お互いが関係性を持つことへの勇気として語った小説とも読めそうな気がする。










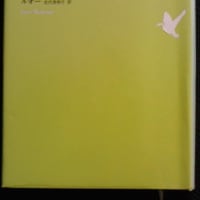
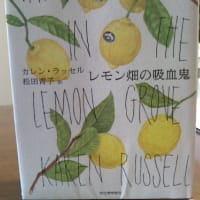
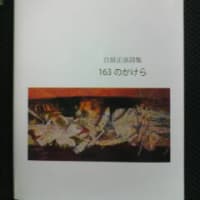
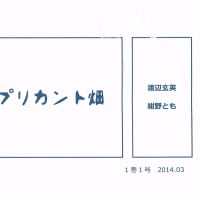
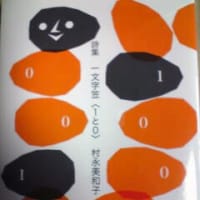
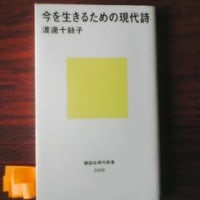









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます