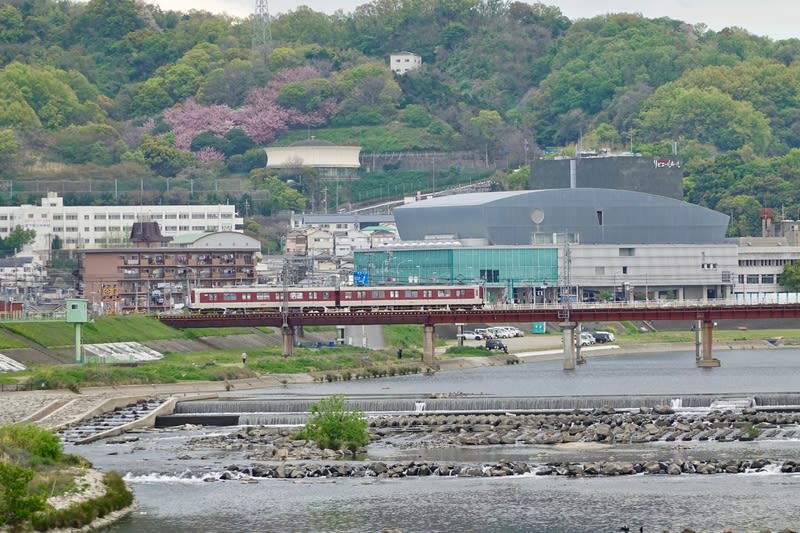万博記念公園の「生産の森」を歩いていると、アオスジアゲハが飛んでいました。
けっこう近くまで寄って来てくれたので、カメラに収めることができました。
アオスジアゲハ はそんなに珍しい種類ではありませんが、名前の通り青いスジが綺麗な蝶です。

この日も野鳥でも撮れればと思っていましたが、野鳥は撮れませんでしたが、蝶が撮れました。

そんなに興味があるわけではありませんが、やはり目の前にとまっているとカメラを向けてしまいます。

翅を広げて美しい姿を見せてくれました。

さらに近くまで寄って来てくれました。

花から花へ飛び回りますが、近い所の移動でサービス精神のある蝶でした。

翅も広げてくれました。

太陽の光を受けて、青いスジが綺麗に輝いていました。

私が一度は撮ってみたい蝶はアサギマダラです。
その姿は何度か見たことはあるのですが、まだカメラに収めたことはありません。
※訪問日 2021.4.19
けっこう近くまで寄って来てくれたので、カメラに収めることができました。
アオスジアゲハ はそんなに珍しい種類ではありませんが、名前の通り青いスジが綺麗な蝶です。

この日も野鳥でも撮れればと思っていましたが、野鳥は撮れませんでしたが、蝶が撮れました。

そんなに興味があるわけではありませんが、やはり目の前にとまっているとカメラを向けてしまいます。

翅を広げて美しい姿を見せてくれました。

さらに近くまで寄って来てくれました。

花から花へ飛び回りますが、近い所の移動でサービス精神のある蝶でした。

翅も広げてくれました。

太陽の光を受けて、青いスジが綺麗に輝いていました。

私が一度は撮ってみたい蝶はアサギマダラです。
その姿は何度か見たことはあるのですが、まだカメラに収めたことはありません。
※訪問日 2021.4.19