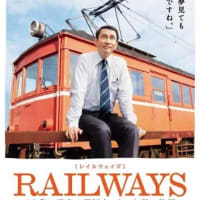建築の世界には宮大工の西岡常一と東京大学の丹下健三がいた。職人と学者である。西岡は薬師寺の伽藍を復興して、丹下は東京オリンピックの代々木体育館の建設で有名である。西岡は伝統工法による木造建築で、丹下は近代工法の学問で鉄を使った建物を造ることで、人に感動を与えた。社会で働きながら体験を積み重ね技術を取得して、自分の仲間で造る職人も、理論で設計図を描き、赤の他人に作らせる学者も建築物を創る事が出来る。富士山の頂上に行く多くの方法があるのに似ている。自分の足でとぼとぼ歩いて、時間を掛けて到達する事が出来るし、ヘリコプターをチャーターして簡単に降り立つことも出来る。頂上からの景色は同じである。その景色をどの様に感じ取るかは個人の問題である。
死んだら皆仏になるが、生き仏になる手段の一つに禅がある。その方法は二つに分けられる。臨済宗と曹洞宗で、看話禅(かんな)黙照禅(もくしょう)とか、臨済将軍、曹洞土民とか区別するが、到達点は同じである。同じ仏教なのだから。臨済禅は公案といわれる宿題を携えて、参禅するが、曹洞禅は只管打座でひたすら座る方法の違いがある。臨済学者、曹洞職人である。
臨済禅の公案の一つに白隠禅師の「隻手音声」があるが、おさんという土産物屋のお婆さんの問答がある。ブログで以前に記述したが、白隠が「両掌相打って音声あり、隻手に何の音声かある」と問うと、おさん婆さんは「白隠の隻手の声を聞くよりも両手を打って商いをせん」と答える。白隠は「商いが両手叩いてなるならば隻手の音は聞くにおよばず」と言った。
白隠は学者で、おさん婆さんは職人で、結局のところ到達するところは同じになるのであり、お互いに認めなければならない。おさん婆さんは臨済宗の信者と思うが、理屈を抜きにして、ひたすら自分の商売に徹する姿勢は曹洞禅になってしまった。宗派に分かれる所以であるが、結局のところ究極は同じ禅なのである。
曹洞宗永平寺の高齢の住職である宮崎禅師の話が有る。「自然は立派やね。私は日記をつけておるけど、何月何日に花が咲いた。何月何日に虫が鳴いた。ほとんど違わない。規則正しい。そういうのが法だ。法にかなったのが大自然だ。法にかなっておる。だから自然の法則を真似て人間が暮らす。人間の欲望に従っては迷いの世界だ。真理を黙って実行するというのが大自然だ。誰に褒められると言うことも思わんし、これだけのことをしたら、これだけの報酬がもらえるということもない。時がきたならばちゃんと花が咲き、そして黙って褒められても、褒められんでも、すべきことをして黙って去っていく。そういうのが、実行であり、教えであり、真理だ。」
報道で言葉が氾濫して、学者や評論家が増えて、騒々しく、物事が高速で変化する昨今であるが、静かに、ゆっくりと時が流れる世間が懐かしい。学者と職人の中間を行く、生き方が中道と言うことなのだろう。今の自分はどちらかと言えば、職人志向である。
最新の画像[もっと見る]