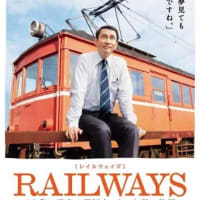「風が吹けば桶屋が儲かる」とは日本の諺で、あたかもバタフライ効果のように思わぬ所に思わぬ物事の影響が出ることの例えである。
バタフライ効果とは、カオス理論を端的に表現する「ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こす」に由来する、ドミノ理論的な波及効果の考え方である。パスカルなら「クレオパトラの鼻。それがもっと短かったなら、大地の全表面は変わっていただろう」と言う。
「風が吹けば桶屋が儲かる」は、江戸時代の浮世草子「世間学者気質(かたぎ)」が原典である。
風が吹く⇒目に埃が入る⇒失明する⇒三味線弾きになる⇒三味線が売れる⇒猫革が要る⇒猫が絶滅する⇒ネズミが増える⇒桶をかじる⇒桶屋が儲かる⇒桶屋になりたい⇒資金が無い⇒貧乏風が吹く
ある些細な事柄から連想して話を作っていくと、ある結論を導き出せるが、現実に適合するかどうか不明である。事柄と事柄の繋がりには、確たる理論的・学問的な証明が無く、思い付きであるからである。選択肢が多く存在するから、一つに決めることに無理がある。連想ゲームになり、株の取引になると、マネーゲームで、バブル経済となり実体経済といえない。資本主義はギャンブル経済である。
過去の例をみると「オイルショックになるとトイレットペーパーが無くなる」というデマが飛び交い、先を争って買い占め、商品が市場から消えたが、倉庫には在庫の山であった。そして製紙会社の株価が高騰しその後急落した。株取引の乱高下は、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な思考の産物である。付和雷同する大衆が、自分を見失い右往左往することの現れである。ギャンブルには有効な考え方である。当たるも八卦・当たらぬも八卦の不確性理論で、的中か紙切れかの分水嶺の決定権は、勝利の女神の専管事項である。
人間は過去を記憶し、未来を予測する能力がある。過去の歴史を踏まえて、未来を推測するのが、統計学であるが、本来は繋がりが無く、瞬間・刹那しかない。連続していると考えることが、強さになったり、弱さになったりする。過去を忘れ、未来を妄想しないことを、禅では前後裁断といい、現象世界は一期一会なのである。
バタフライ効果とは、カオス理論を端的に表現する「ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こす」に由来する、ドミノ理論的な波及効果の考え方である。パスカルなら「クレオパトラの鼻。それがもっと短かったなら、大地の全表面は変わっていただろう」と言う。
「風が吹けば桶屋が儲かる」は、江戸時代の浮世草子「世間学者気質(かたぎ)」が原典である。
風が吹く⇒目に埃が入る⇒失明する⇒三味線弾きになる⇒三味線が売れる⇒猫革が要る⇒猫が絶滅する⇒ネズミが増える⇒桶をかじる⇒桶屋が儲かる⇒桶屋になりたい⇒資金が無い⇒貧乏風が吹く
ある些細な事柄から連想して話を作っていくと、ある結論を導き出せるが、現実に適合するかどうか不明である。事柄と事柄の繋がりには、確たる理論的・学問的な証明が無く、思い付きであるからである。選択肢が多く存在するから、一つに決めることに無理がある。連想ゲームになり、株の取引になると、マネーゲームで、バブル経済となり実体経済といえない。資本主義はギャンブル経済である。
過去の例をみると「オイルショックになるとトイレットペーパーが無くなる」というデマが飛び交い、先を争って買い占め、商品が市場から消えたが、倉庫には在庫の山であった。そして製紙会社の株価が高騰しその後急落した。株取引の乱高下は、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な思考の産物である。付和雷同する大衆が、自分を見失い右往左往することの現れである。ギャンブルには有効な考え方である。当たるも八卦・当たらぬも八卦の不確性理論で、的中か紙切れかの分水嶺の決定権は、勝利の女神の専管事項である。
人間は過去を記憶し、未来を予測する能力がある。過去の歴史を踏まえて、未来を推測するのが、統計学であるが、本来は繋がりが無く、瞬間・刹那しかない。連続していると考えることが、強さになったり、弱さになったりする。過去を忘れ、未来を妄想しないことを、禅では前後裁断といい、現象世界は一期一会なのである。