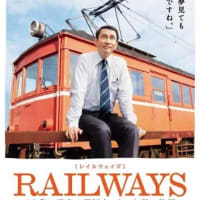大相撲の発祥は神社仏閣の建築や修繕などの募金を目的とした勧進だったが、現在は興行。
横綱は相撲の家元だった神道の19世吉田追風が考案し、太刀持ち、露払いの土俵入りの所作を江戸時代に決め、今に繋がる。蝶結びの不知火、片結びの雲竜の型が有る。
土俵を司る行司が相撲美学を統制する。
高貴な総紫房の立行司の木村庄之助の軍配の手の甲が上を向くのは陽、紫白の式守伊之助が逆で陰の陰陽思想、仏教の高貴な色は緋色で三役格の行司の指定色。
横綱を裁く立行司は間違えたら切腹覚悟で腰に刀、修行に挫折したら死の比叡のお山の千日回峰行者の帯刀と同じ武士道。
黄色の土俵の東西南北を示す青白赤黒は五行思想、伊勢神宮と同じ神明造りの屋根、清め塩、宗教的思想を具現化する裏方仕事は呼出が担当する。
尺貫法の廃止で西洋単位に変更になって国際化が進み、弱肉強食の狩猟民族の格闘技に変質したが、農耕民族の祭祀と思うなら大相撲に新たな魅力を発見する。
年寄り・行司・呼出が三位一体となって作る日本古来の宗教観の舞台で力士が演技する、国技なる芸術なのだろう。