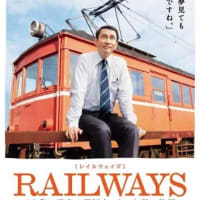冬に暖房を効かせ、アイスクリームを毎日食べ、夏に冷房の効いた屋台でおでんを食べる時代で誰も疑問に思わない。食べたい時に食べたい物を、金の力で満腹にしている。豊かな時代なのだろうか?
夏は氷屋、冬は炭屋の商売に馴染んだ世代である。狭いながらも楽しい我が家。老人の古き善き日本の郷愁で、若者から無視される。
春の鰹のたたき、筍。夏のうなぎ、鮎の塩焼き。秋の松茸御飯、栗御飯。冬の越前ガニ、石狩鍋。季節には旨いものがあり、我慢して待つ楽しみがあった。旬であるが、今では通用しない言葉になった。
旬とは、食材が新鮮で美味しく食べられる時期で、量が豊富だから値段も安価になる出盛り期である。蟹ならば、越前蟹・毛蟹・タラバ蟹・花咲蟹は秋から冬、渡り蟹(がざみ)が夏である。
砂漠の民が憧れの季節感を人工的に創作したのが、ラマダンという断食の期間である。反面、天然自然の季節をカネの力で破壊して、砂漠を志向している日本人。
日本文化の旬の概念を破壊したのは、牧畜文化の牛肉・豚肉・鶏肉の洋食である。その西洋に毒された寿司やうなぎの蒲焼なども「ヨウショク」に成り下がった。マグロは近畿大学で完全養殖の全身トロ、うなぎは三河一色で養殖。
季節感を失った金満家の日本人は、金力で飽食の毎日が、筋力の無い全身脂肪のメタボリック・シンドロームの肥満児になっている。
カネを得る為だけの出世欲の権化の上司の企画する慰労会は、夏に蟹道楽での割り勘の食事会だという。酒は禁止、話も駄目、只管食べ、自分だけ土産を調達して帰宅する自己満足の上機嫌。哀れな心の貧乏人である。人が離散する。
先日は定年を迎える仲間の慰労会に招待された。元上司は酒が飲めないが、愚痴を聞いてくれ、名古屋錦の中納言の伊勢海老料理をご馳走してくれる。飲んで食って上機嫌の満腹の私。元上司は高額勘定5名分支払ってくれる。そしてまもなく退職する。返礼の会を開催しないと失礼になる。
蟹は甲羅に似せて穴を掘るとは、人間性の違いを言っている。蟹より伊勢海老が好きになった。伊藤公さんありがとう。
夏は氷屋、冬は炭屋の商売に馴染んだ世代である。狭いながらも楽しい我が家。老人の古き善き日本の郷愁で、若者から無視される。
春の鰹のたたき、筍。夏のうなぎ、鮎の塩焼き。秋の松茸御飯、栗御飯。冬の越前ガニ、石狩鍋。季節には旨いものがあり、我慢して待つ楽しみがあった。旬であるが、今では通用しない言葉になった。
旬とは、食材が新鮮で美味しく食べられる時期で、量が豊富だから値段も安価になる出盛り期である。蟹ならば、越前蟹・毛蟹・タラバ蟹・花咲蟹は秋から冬、渡り蟹(がざみ)が夏である。
砂漠の民が憧れの季節感を人工的に創作したのが、ラマダンという断食の期間である。反面、天然自然の季節をカネの力で破壊して、砂漠を志向している日本人。
日本文化の旬の概念を破壊したのは、牧畜文化の牛肉・豚肉・鶏肉の洋食である。その西洋に毒された寿司やうなぎの蒲焼なども「ヨウショク」に成り下がった。マグロは近畿大学で完全養殖の全身トロ、うなぎは三河一色で養殖。
季節感を失った金満家の日本人は、金力で飽食の毎日が、筋力の無い全身脂肪のメタボリック・シンドロームの肥満児になっている。
カネを得る為だけの出世欲の権化の上司の企画する慰労会は、夏に蟹道楽での割り勘の食事会だという。酒は禁止、話も駄目、只管食べ、自分だけ土産を調達して帰宅する自己満足の上機嫌。哀れな心の貧乏人である。人が離散する。
先日は定年を迎える仲間の慰労会に招待された。元上司は酒が飲めないが、愚痴を聞いてくれ、名古屋錦の中納言の伊勢海老料理をご馳走してくれる。飲んで食って上機嫌の満腹の私。元上司は高額勘定5名分支払ってくれる。そしてまもなく退職する。返礼の会を開催しないと失礼になる。
蟹は甲羅に似せて穴を掘るとは、人間性の違いを言っている。蟹より伊勢海老が好きになった。伊藤公さんありがとう。