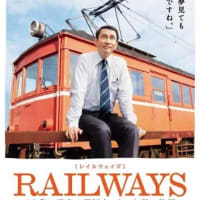明治時代の八百屋の長兵衛は通称を「八百長(やおちょう)」といい、大相撲の年寄・伊勢ノ海五太夫と囲碁仲間であった。囲碁の実力は長兵衛が勝っていたが、野菜をチャンコ用として大量に買ってもらう商売上の打算から、わざと負けたりして伊勢ノ海五太夫のご機嫌をとっていた。転じて金品を受領して、わざと負けることを、八百長というのである。
力士の一方が前以て負ける約束をしておいて、土俵上でうわべだけの勝負を争うこと、馴れ合い勝負を八百長相撲として、社会悪であるとする報道が世間の常識である。本当に社会悪なのだろうか。必要悪ではないのか。人生の黄昏を迎えた現在、考えが変わってきたのである。缶ビールにおまけのフィギャーを付けるのは八百長と言わず、サービスである。
相撲は本来、五穀豊穣を願う儀式が起源になっており、歌舞伎や能楽と同じように伝統芸能で、観客に娯楽を提供する興業なのである。公営ギャンブルと違い、勝負の結果はどうでも利害損得は無いのである。プロセスを楽しんでいるのである。舞台裏で、金品のやりとりがあり、ドラマを演出しても結構で、詮索しないのである。手品は種も仕掛けもあり、騙されるのであるが、怒ることは無く楽しんでいる。舞台裏でプロ手品師はギャラを受け取っている。
相撲は形の美しさと心の美しさの「男の美学」である。自力で回復不可能なほど体が崩れた状態を「死に体」というが、先に手を着いて「死に体」の相手を怪我させない配慮を「かばい手」、早く土俵外に足を出す「かばい足」と名付け、相撲の美風とされ勝ちになる。自分の都合のみで、戦うのは喧嘩で、行司が裁くのではなく、警察の世話になる。
相撲は格闘技であるから、お互いの肉体闘争のはずであるが、接触しない前に勝負が決まることがあることが面白い。相手の力が加わらぬままバランスを崩し、土俵上に足の裏以外の体の部分が着いてしまう「腰砕け・つき手・つきひざ」と後ずさりして足が誤って土俵外に出る「踏み出し」の非技(勝負結果)である。
我々の窺い知れない世界で、練習・工夫・鍛錬・演出して、奇想天外な結果になっても、八百長であると騒ぐことはしないのである。素人にわかる幼稚な、不真面目な動作は、プロとして恥ずかしく、観客は離れていく。八百長にも血の滲む稽古が必要なのである。
秘密の部分があって、気分良く騙さるのが、娯楽である。「知らぬが仏」は良い言葉である。
公共放送のNHKにおける相撲放送の時間が多過ぎるという闘争は、土俵が違い場外乱闘である。
最新の画像[もっと見る]