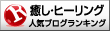偏食ならぬ偏問いが東洋医学、鍼灸の世界には蔓延している、と思える。問うべきことを問わない、問えないことの恐さを痛感する。
鍼灸学校に通う三年間は、これまで以上に鍼灸や東洋医学の世界の先生がたと直接にまた媒介的に関わる機会を多く持つこととなった。
その度に思わされたことが、彼等の(偏食ならぬ)偏問いの凄まじさである。端的には、問わねばならないことを問わない、問えないということである。
例えば、脈診について、通常ならば、脈とは何か、を人間の解剖生理から、もう少し実力があれば、生命の歴史に尋ねてその過程的構造から問うての脈診とは何かでなければならない、あるいは、それらと併せて認識論の問題として、荒唐無稽と思える脈診というものが、何故に有効性を持つがごとく現象するのか、そのような現実があるのは何故か?と問う、問うて行かなければならない、と自身の拙いレベルででも思える。
しかしながら現実にはそうでは無くて、東洋医学、鍼灸の世界の先生がたは、自身の信じる先生、先輩が正しいとしているからとか、伝統的に正当なものとして伝わっているものだからとか、何か自身の感性にぴったりくるからとかで、それに加えて、自身で試してみて効果があったと思えるからといった理由で、それらの問いかけはスタートとしては悪くは無いと思えるが、伝わっている脈診を正しいものとして受け入れ、学び、行う、のみならず他者にもそのレベルで、正しいものとして説いていくのである。
別言すれば、本来ならば、論理的に対象に問いかけて行かねばならないものを、自身の思い、それもほとんどが感性レベルの思い(有り体に言えば、好き嫌いレベル)で対象に問いかけて行くから、結果としては何も無いに等しい、どころか現実にはありえないオバケを創り上げていってしまう、ということになってしまっているのだ、と思える。
これは子供にも分かるレベルの譬え話をすれば、本来なら人間にとっての必要な食とは何か、との問いかけで食の選択は為されねばならないものを、自身の好き嫌いから食の選択を行い(偏食)、食べ続けることで、病気へとなっていってしまっている、という図を、よくある偏食から病への道を思い描いて見ていただければ、と思う。
これが、「偏食ならぬ偏問い」とした理由でもある。
鍼灸学校に通う三年間は、これまで以上に鍼灸や東洋医学の世界の先生がたと直接にまた媒介的に関わる機会を多く持つこととなった。
その度に思わされたことが、彼等の(偏食ならぬ)偏問いの凄まじさである。端的には、問わねばならないことを問わない、問えないということである。
例えば、脈診について、通常ならば、脈とは何か、を人間の解剖生理から、もう少し実力があれば、生命の歴史に尋ねてその過程的構造から問うての脈診とは何かでなければならない、あるいは、それらと併せて認識論の問題として、荒唐無稽と思える脈診というものが、何故に有効性を持つがごとく現象するのか、そのような現実があるのは何故か?と問う、問うて行かなければならない、と自身の拙いレベルででも思える。
しかしながら現実にはそうでは無くて、東洋医学、鍼灸の世界の先生がたは、自身の信じる先生、先輩が正しいとしているからとか、伝統的に正当なものとして伝わっているものだからとか、何か自身の感性にぴったりくるからとかで、それに加えて、自身で試してみて効果があったと思えるからといった理由で、それらの問いかけはスタートとしては悪くは無いと思えるが、伝わっている脈診を正しいものとして受け入れ、学び、行う、のみならず他者にもそのレベルで、正しいものとして説いていくのである。
別言すれば、本来ならば、論理的に対象に問いかけて行かねばならないものを、自身の思い、それもほとんどが感性レベルの思い(有り体に言えば、好き嫌いレベル)で対象に問いかけて行くから、結果としては何も無いに等しい、どころか現実にはありえないオバケを創り上げていってしまう、ということになってしまっているのだ、と思える。
これは子供にも分かるレベルの譬え話をすれば、本来なら人間にとっての必要な食とは何か、との問いかけで食の選択は為されねばならないものを、自身の好き嫌いから食の選択を行い(偏食)、食べ続けることで、病気へとなっていってしまっている、という図を、よくある偏食から病への道を思い描いて見ていただければ、と思う。
これが、「偏食ならぬ偏問い」とした理由でもある。