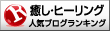「思索への示唆」(ナイチンゲール)を読むと、『形而上学』(アリストテレス)の説き方が想起される、合わせて読むことで何かが見えてくるのでは、との思いから『形而上学』に目を通した。アリストテレスもまたナイチンゲールと同じ労苦を味わっているのだと思えた。
『形而上学』を読んでいただければ、そこにはアリストテレスが分からないことを分かっていこうと、対象の構造に分け入ろうと(これが、概念規定を行うということなのだろうか?)必死の努力を為していることが見て取れる。(と自身には思える)
具体的には、『形而上学』をお読みいただければと思うが、例えば以下である。
「(1)知恵とは、ある種の学的認識であるとする場合、それは単一の学としてあるとなすべきか。それとも、それは単一ではなく多くの学としてあるとなすべきであろうか。──というのは、まず(a)それは単一の学としてあるとしよう。一つの学は、反対関係にある諸事物をつねに対象とする。しかし諸原理は相互に反対関係にあるものではないのである。(b)しかし、もしも一つかぎりの学ではないとすれば、いったいいかなる諸学が、特にそれら(つまり知恵)があると見なされるべきであろうか?
さらに、(2)論証の諸原理を考察することは、一つの学のなすことか。あるいは、一つより多くの学のなすことか──。(a)しかしもし一つより多くの学のなすこととすれば、なにゆえに他の任意の学ではなしに、とりわけその学のなすことであるのか。(b)しかしもし一つより多くの学のなすこととすれば、いったいいかなる諸学が、まさにそれらであると見なされるべきであろうか?
さらに、(3)この学は、すべての種類の実体を対象とするのか。あるいはそうではないのか。──(b)もしもそのすべてをではないとすれば、いかなる種類の実体を対象とするかについて、その正当性を示すことは難事であろう。(a)しかしもし、すべてについて一なる学があるとすれば、いかにして、多くの種類の実体を、同一の学が対象となしうるかは、不明確である。
さらに、(5)この学は、実体のみを考察の対象とするのか。それとも、実体に付帯して生ずるもの(諸属性)をも考察するのか。──というのは、実体に付帯して生ずるもの(諸属性)については論証ということがあるが、実体(「何であるか」というそのもの)については、論証することはありえないからである。しかしもし、その両者についての学が相互に異なるとすれば、いったいそのそれぞれは何であり、またそのいずれの学が、「知恵」であるのか。(a)もしも「知恵」が論証的な学であるとすれば、実体に付帯して生ずるもの(所属性)についての学が、それであることになろう。(b)しかし「知恵」とは、第一の原理となるものどもにかかわるとすれば、諸実体(「何であるか」というそのもの)についての学が、それであることになるのである。
だがしかし、いまわれわれが求めている学は、かの自然学講義のうちで述べられた四原因を、対象とするのであろうか。いな、それはまたそうすべきではない。なぜならこの学は、「何のために」というその原因(目的因)を、対象とすることはないからである。というのは、「何のために」というそのような原因(目的因)は、善にほかならないが、それは、好意的な事物や、動(転化)をなす事物の場合に見いだされるものである。そしてそのような場合には、それの原因(善)が第一に動かすものとなる。なぜなら、目的とは、まさにそのような本性のものだからである。しかしながら、普遍なる諸存在者のうちには、こうした第一に動かすものは、ないのである。」(『世界の名著8 アリストテレス』責任編集 田中美知太郎 中央公論社)
このように、「(学としての)知恵」について延々と、さまざまな角度からアリストテレスは問い続けていく。これを「思索への示唆」でのナイチンゲールの説くところと比較してみれば、その共通性に驚かされないだろうか?
念のため、「思索への示唆」の一部をご紹介すれば以下である。
「われわれは人々がごくわずかの言葉の上に壮大な体系を築いたことを認めねばならない。
この愚かさに気づいた他の人たちは、われわれは神については何も知りえないという。われわれは、確実に知りうることと、経験にもとづいて推論できるだけのこと(推論する理由が正しいとわかるもの)、および来るべき時代の能力の働きによって確かめるようにするしかないものとの間の区別に線を引くにあたっては、慎重すぎることはありえない。同時に、人類が確かな知識をもっていると主張してきた事柄についても、それがどこに基礎をおいているか知らない、と認めるにあたっても然りである。
われわれのさまざまな能力で認識可能な、存在しているものおよび存在してきたものを観察し熟考したとき、一脈の慈悲深い意志、賢明な意志、力強い意志のしるしを認めないわけにはいかない。われわれが働いている機械を見ると(そこに人間の意志を持つ人を感知しなくても)、人間の意志があり、そこに働いていると断言させる兆候を否定できるであろうか。そのまったく同じ徴候が、人間の意志が取り組んでいる目的と同じ目的を達成するための、より優れた知恵と力をもっていて人間と区別されるある意志の存在を明示しているのだということを否定できるであろうか?
しかし、この意志が完全で永遠であると《主張する》ために独断的な意見を述べたりしないようにしよう。神の思慮と目的が完全であるとするならば、その完全な実現は永遠の仕事である。したがって完全な実現が人間に認識されることはありえない。人間は、彼が現在、過去、未来について学びうることのなかに、完全な目的をつかみとってくる《傾向》を認識するだけである。
われわれが何か知っているというときには厳密さを保つよう最大の注意を払おう。特に考え深く誠実な人々は、わかるはずのないことを信じるよう要求されたため、わかっていることをも疑っているのである。
ある意志についての証拠は、われわれが《ある》慈愛、知恵、力の跡をたぐり取れる長い間の過去の活動から手に入れられるだろう。しかしわれわれは確かに知っていることだけから行動したり感じたりすることはまれである。われわれには経験的に行動しなければならないことがよくある。
経験は確実性への道につながるにちがいない。経験的法則とは「観察や実験によって、存在することをしめしてきた一定の性質であるが、《なぜ》そういう法則が存在するかが充分知られていないため、われわれはそれに寄りかかるのをためらう。日食の定期的な繰り返しが古代東洋の天文学者のたゆまぬ観察によってたしかめられたとき、天の運行の一般法則がそれを説明してしまうまでは、ひとつの経験的法則であった。それゆえ、経験的法則とは、観察によって得られた一定の性質であり、究極の法則に帰結すると推定されるけれどもまだそうなっていないものをいう」。
われわれは、慈愛、知恵、力のしるしを発見するが、それらは、存在するものがまさに存在することの原因となっている意志が、現在または未来のいつの日か、その存在を完全に実現しようと望んでいることを示しているように見える。しかし、今も以前もわれわれが見なれた現在にはいくつも多くの苦しみがある。そして、どうしてこの現在が幸福な未来へと導かれていくことができるのか、細かな点で理解に苦しむ。しかし、大局的には幸福な未来へと導かれつつあり、至福のために現在を欠くことはできないということを示す証拠は手にいれられるであろう。
ここの苦しみの原因は、人間の能力を働かせることによって時がたつにつれて消えていく。われわれは、もし人間がその能力をこれまでとは異なった使い方をするならば、他の苦しみもどんなに消えていくかと考えてみることができる。人間の能力を活用することによって喜びが大いに増大することが、すでにある方向ではじまっている。そしてここでもまた我々人間が到達できる測り知れない喜びについて一瞥することができる。
このように見てくると……」(「思索への示唆」薄井坦子訳 現代社)
このように、神の存在を知るということについて、延々とさまざまな角度からナイチンゲールは問い続けていく。これらアリストテレスの述べるところとナイチンゲールの述べるところとの両者には、多くの相違点があるものの、そこには共通性がある、それは言ってみれば「(一人での自身の主張とそれを強烈に否定する主張との討論、闘論を行うところの)弁証術」であると思われる。それが思弁するということであると自身にはおもえるのであるが……。
別の観点からは、ナイチンゲールはアリストテレスのなした、個の歴史性としての、かつ人類の精神の歴史性としてのアリストテレスの為した思弁ということをしっかりと学の?出発点において為したがゆえに、つまり見事に人類としての系統発生をくり返しえたがゆえに、のその後の見事な発展があったのであろうと思える。
【これは良く書けていると思うが、同時に、一つ大きな疑問がある。
『形而上学』を読んでいただければ、そこにはアリストテレスが分からないことを分かっていこうと、対象の構造に分け入ろうと(これが、概念規定を行うということなのだろうか?)必死の努力を為していることが見て取れる。(と自身には思える)
具体的には、『形而上学』をお読みいただければと思うが、例えば以下である。
「(1)知恵とは、ある種の学的認識であるとする場合、それは単一の学としてあるとなすべきか。それとも、それは単一ではなく多くの学としてあるとなすべきであろうか。──というのは、まず(a)それは単一の学としてあるとしよう。一つの学は、反対関係にある諸事物をつねに対象とする。しかし諸原理は相互に反対関係にあるものではないのである。(b)しかし、もしも一つかぎりの学ではないとすれば、いったいいかなる諸学が、特にそれら(つまり知恵)があると見なされるべきであろうか?
さらに、(2)論証の諸原理を考察することは、一つの学のなすことか。あるいは、一つより多くの学のなすことか──。(a)しかしもし一つより多くの学のなすこととすれば、なにゆえに他の任意の学ではなしに、とりわけその学のなすことであるのか。(b)しかしもし一つより多くの学のなすこととすれば、いったいいかなる諸学が、まさにそれらであると見なされるべきであろうか?
さらに、(3)この学は、すべての種類の実体を対象とするのか。あるいはそうではないのか。──(b)もしもそのすべてをではないとすれば、いかなる種類の実体を対象とするかについて、その正当性を示すことは難事であろう。(a)しかしもし、すべてについて一なる学があるとすれば、いかにして、多くの種類の実体を、同一の学が対象となしうるかは、不明確である。
さらに、(5)この学は、実体のみを考察の対象とするのか。それとも、実体に付帯して生ずるもの(諸属性)をも考察するのか。──というのは、実体に付帯して生ずるもの(諸属性)については論証ということがあるが、実体(「何であるか」というそのもの)については、論証することはありえないからである。しかしもし、その両者についての学が相互に異なるとすれば、いったいそのそれぞれは何であり、またそのいずれの学が、「知恵」であるのか。(a)もしも「知恵」が論証的な学であるとすれば、実体に付帯して生ずるもの(所属性)についての学が、それであることになろう。(b)しかし「知恵」とは、第一の原理となるものどもにかかわるとすれば、諸実体(「何であるか」というそのもの)についての学が、それであることになるのである。
だがしかし、いまわれわれが求めている学は、かの自然学講義のうちで述べられた四原因を、対象とするのであろうか。いな、それはまたそうすべきではない。なぜならこの学は、「何のために」というその原因(目的因)を、対象とすることはないからである。というのは、「何のために」というそのような原因(目的因)は、善にほかならないが、それは、好意的な事物や、動(転化)をなす事物の場合に見いだされるものである。そしてそのような場合には、それの原因(善)が第一に動かすものとなる。なぜなら、目的とは、まさにそのような本性のものだからである。しかしながら、普遍なる諸存在者のうちには、こうした第一に動かすものは、ないのである。」(『世界の名著8 アリストテレス』責任編集 田中美知太郎 中央公論社)
このように、「(学としての)知恵」について延々と、さまざまな角度からアリストテレスは問い続けていく。これを「思索への示唆」でのナイチンゲールの説くところと比較してみれば、その共通性に驚かされないだろうか?
念のため、「思索への示唆」の一部をご紹介すれば以下である。
「われわれは人々がごくわずかの言葉の上に壮大な体系を築いたことを認めねばならない。
この愚かさに気づいた他の人たちは、われわれは神については何も知りえないという。われわれは、確実に知りうることと、経験にもとづいて推論できるだけのこと(推論する理由が正しいとわかるもの)、および来るべき時代の能力の働きによって確かめるようにするしかないものとの間の区別に線を引くにあたっては、慎重すぎることはありえない。同時に、人類が確かな知識をもっていると主張してきた事柄についても、それがどこに基礎をおいているか知らない、と認めるにあたっても然りである。
われわれのさまざまな能力で認識可能な、存在しているものおよび存在してきたものを観察し熟考したとき、一脈の慈悲深い意志、賢明な意志、力強い意志のしるしを認めないわけにはいかない。われわれが働いている機械を見ると(そこに人間の意志を持つ人を感知しなくても)、人間の意志があり、そこに働いていると断言させる兆候を否定できるであろうか。そのまったく同じ徴候が、人間の意志が取り組んでいる目的と同じ目的を達成するための、より優れた知恵と力をもっていて人間と区別されるある意志の存在を明示しているのだということを否定できるであろうか?
しかし、この意志が完全で永遠であると《主張する》ために独断的な意見を述べたりしないようにしよう。神の思慮と目的が完全であるとするならば、その完全な実現は永遠の仕事である。したがって完全な実現が人間に認識されることはありえない。人間は、彼が現在、過去、未来について学びうることのなかに、完全な目的をつかみとってくる《傾向》を認識するだけである。
われわれが何か知っているというときには厳密さを保つよう最大の注意を払おう。特に考え深く誠実な人々は、わかるはずのないことを信じるよう要求されたため、わかっていることをも疑っているのである。
ある意志についての証拠は、われわれが《ある》慈愛、知恵、力の跡をたぐり取れる長い間の過去の活動から手に入れられるだろう。しかしわれわれは確かに知っていることだけから行動したり感じたりすることはまれである。われわれには経験的に行動しなければならないことがよくある。
経験は確実性への道につながるにちがいない。経験的法則とは「観察や実験によって、存在することをしめしてきた一定の性質であるが、《なぜ》そういう法則が存在するかが充分知られていないため、われわれはそれに寄りかかるのをためらう。日食の定期的な繰り返しが古代東洋の天文学者のたゆまぬ観察によってたしかめられたとき、天の運行の一般法則がそれを説明してしまうまでは、ひとつの経験的法則であった。それゆえ、経験的法則とは、観察によって得られた一定の性質であり、究極の法則に帰結すると推定されるけれどもまだそうなっていないものをいう」。
われわれは、慈愛、知恵、力のしるしを発見するが、それらは、存在するものがまさに存在することの原因となっている意志が、現在または未来のいつの日か、その存在を完全に実現しようと望んでいることを示しているように見える。しかし、今も以前もわれわれが見なれた現在にはいくつも多くの苦しみがある。そして、どうしてこの現在が幸福な未来へと導かれていくことができるのか、細かな点で理解に苦しむ。しかし、大局的には幸福な未来へと導かれつつあり、至福のために現在を欠くことはできないということを示す証拠は手にいれられるであろう。
ここの苦しみの原因は、人間の能力を働かせることによって時がたつにつれて消えていく。われわれは、もし人間がその能力をこれまでとは異なった使い方をするならば、他の苦しみもどんなに消えていくかと考えてみることができる。人間の能力を活用することによって喜びが大いに増大することが、すでにある方向ではじまっている。そしてここでもまた我々人間が到達できる測り知れない喜びについて一瞥することができる。
このように見てくると……」(「思索への示唆」薄井坦子訳 現代社)
このように、神の存在を知るということについて、延々とさまざまな角度からナイチンゲールは問い続けていく。これらアリストテレスの述べるところとナイチンゲールの述べるところとの両者には、多くの相違点があるものの、そこには共通性がある、それは言ってみれば「(一人での自身の主張とそれを強烈に否定する主張との討論、闘論を行うところの)弁証術」であると思われる。それが思弁するということであると自身にはおもえるのであるが……。
別の観点からは、ナイチンゲールはアリストテレスのなした、個の歴史性としての、かつ人類の精神の歴史性としてのアリストテレスの為した思弁ということをしっかりと学の?出発点において為したがゆえに、つまり見事に人類としての系統発生をくり返しえたがゆえに、のその後の見事な発展があったのであろうと思える。
【これは良く書けていると思うが、同時に、一つ大きな疑問がある。
そのような気づきが本当であるならば、なにゆえに自身でも、自身の論の展開として、物事を考えるにあたって、テーゼに対してのアンチテーゼを立てての大論争としていかなかったのか?思弁への第一歩を踏み出さなかったのか!?ということである。
単なる知識、あるいは他人事であったのでは?と。
思弁への一歩を踏み出すべく、「書くことは考えることである」の実践に全力を、と思う。】