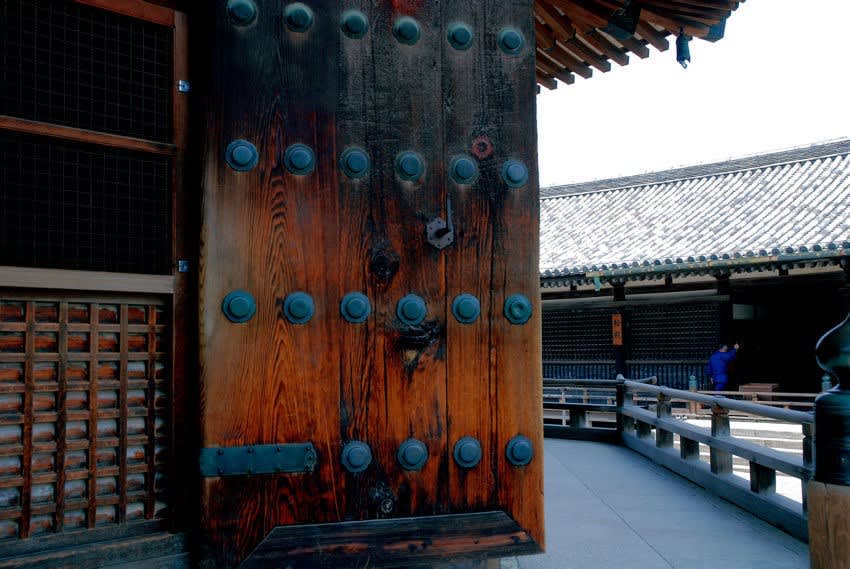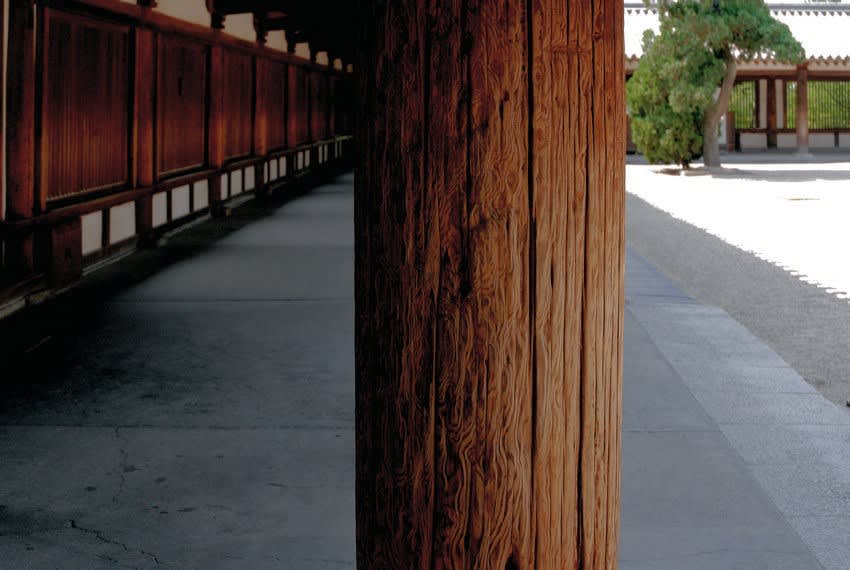法隆寺の東、なだらかな山裾に沿って位置する聖徳太子ゆかりの古寺、法起寺、法輪寺に
二つの三重塔を訪ねます。
法起寺(ほうきじ)三重塔は慶雲3年(706)太子の子、山背大兄王(やましろのおおえのおう)
の建立とみられています。現存するわが国最古の三重塔なのです。
高さ23.9m、三重塔としては最大級のもの。同時期建立の法隆寺五重塔とは共通する所
が多い。法隆寺の初層、三層、五層の大きさが、この三重塔の初層、二層、三層に
ほぼ等しいこと。雲肘木、隅尾垂木上に鬼斗が入る木組み・・などです。
法起寺と法隆寺の間にもう一つの寺、法輪寺があります。ここにも、7世紀末に建てられた
と言われる三重塔がありましたが、不幸にも昭和19年雷火で炎上。
でも、境内には朱色鮮やかな美しい三重塔の姿がみられます。昭和50年、作家幸田文の
支援、宮大工西岡棟梁の手で創建当時そのままの姿で再建されたものです。(幸田文の父
幸田露伴には宮大工を描いた「五重塔」という名作がありますね。その縁でしょうか。)
法起寺の塔とはうり二つ、双子の姉が蘇ったような姿に感動を覚えます。(写真6、7枚目)
法輪寺講堂には、飛鳥の香り(いや、大陸のお顔かな・・)高い、寺伝虚空蔵菩薩がおられ
ます。熱烈な愛好者が多いと言われる美しいお像です。
斑鳩の地に広がる田園の道を歩きながら、思うような写真は撮れなかったけれど、1300年
昔の面影を持った三重塔と仏に会えたことにまずまず満足とせねば・・と思ったものです。








二つの三重塔を訪ねます。
法起寺(ほうきじ)三重塔は慶雲3年(706)太子の子、山背大兄王(やましろのおおえのおう)
の建立とみられています。現存するわが国最古の三重塔なのです。
高さ23.9m、三重塔としては最大級のもの。同時期建立の法隆寺五重塔とは共通する所
が多い。法隆寺の初層、三層、五層の大きさが、この三重塔の初層、二層、三層に
ほぼ等しいこと。雲肘木、隅尾垂木上に鬼斗が入る木組み・・などです。
法起寺と法隆寺の間にもう一つの寺、法輪寺があります。ここにも、7世紀末に建てられた
と言われる三重塔がありましたが、不幸にも昭和19年雷火で炎上。
でも、境内には朱色鮮やかな美しい三重塔の姿がみられます。昭和50年、作家幸田文の
支援、宮大工西岡棟梁の手で創建当時そのままの姿で再建されたものです。(幸田文の父
幸田露伴には宮大工を描いた「五重塔」という名作がありますね。その縁でしょうか。)
法起寺の塔とはうり二つ、双子の姉が蘇ったような姿に感動を覚えます。(写真6、7枚目)
法輪寺講堂には、飛鳥の香り(いや、大陸のお顔かな・・)高い、寺伝虚空蔵菩薩がおられ
ます。熱烈な愛好者が多いと言われる美しいお像です。
斑鳩の地に広がる田園の道を歩きながら、思うような写真は撮れなかったけれど、1300年
昔の面影を持った三重塔と仏に会えたことにまずまず満足とせねば・・と思ったものです。