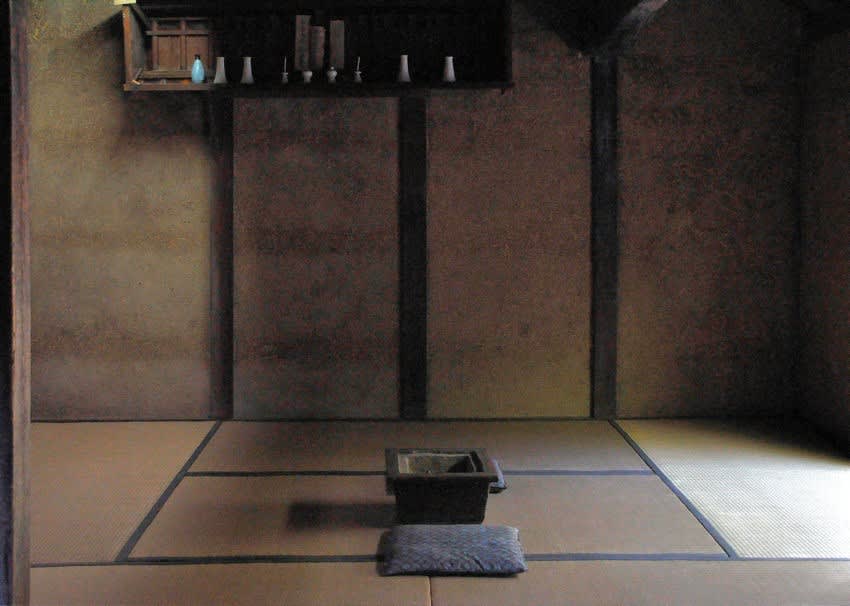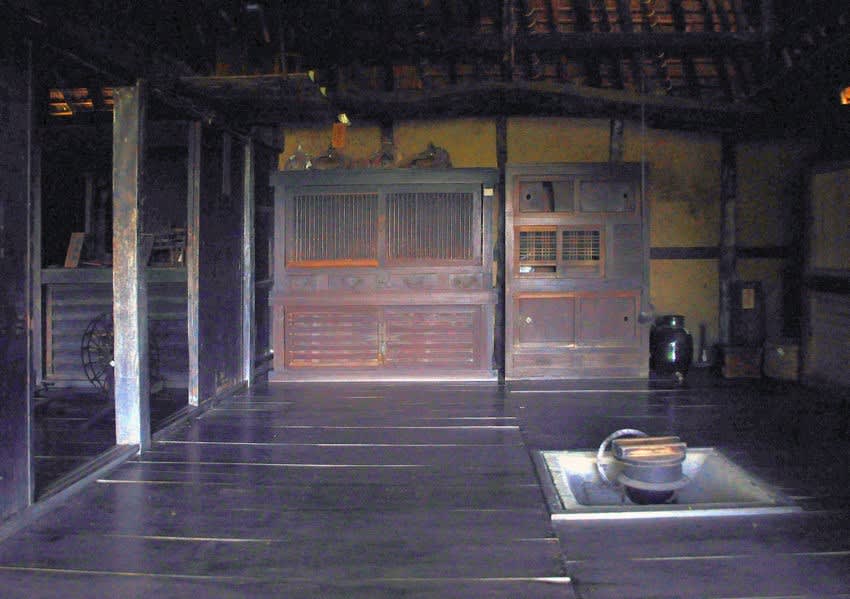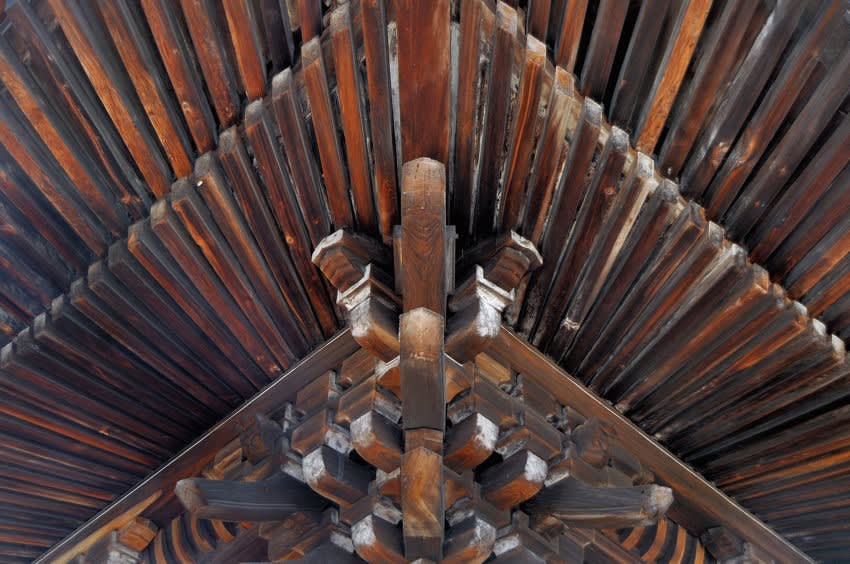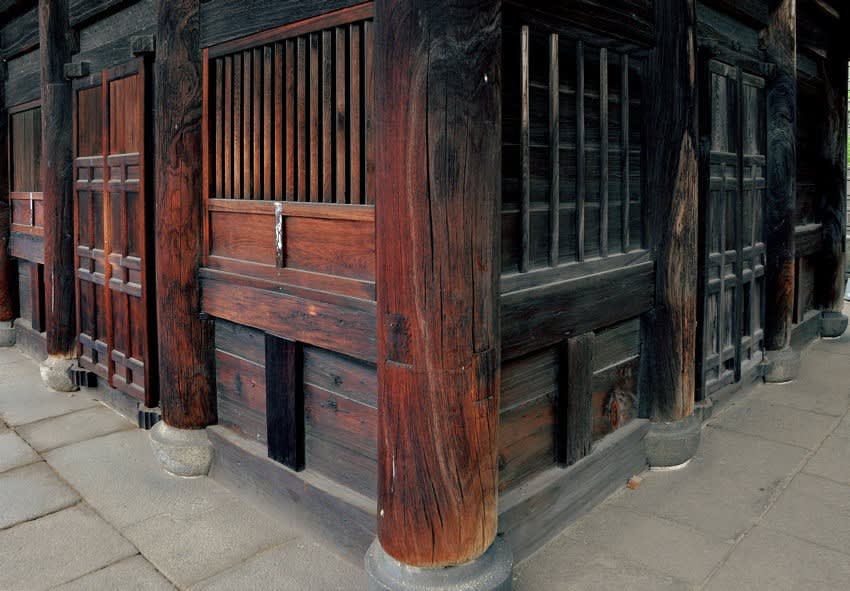兵庫県赤穂といえば、云わずと知れたあの忠臣蔵の浅野家の居城があった所。
その赤穂の東部の坂越湾に面した港町が坂越(さこし)。
天然の良港に恵まれ、西廻り航路の廻船業の拠点として古くから発展したと
いいます。坂越の中心街は大道(だいどう)と呼ばれます。
坂越浦会所は、赤穂藩主の茶屋、また村の会所として明治まで使用されてきた
もの。現在の建物は江戸後期(1831)の建築。
奥藤酒造、今も現役、地酒「忠臣蔵」の醸造元。江戸初期に建てられた酒蔵
が並ぶ。
この大道の街並みは最近整備され、それは見事に蘇った。あまりの清潔さは
生活臭までも消し去ってはいないか・・。それとも、江戸時代の日本の街は
かくも整然と美しかったのであろうか・・と。









その赤穂の東部の坂越湾に面した港町が坂越(さこし)。
天然の良港に恵まれ、西廻り航路の廻船業の拠点として古くから発展したと
いいます。坂越の中心街は大道(だいどう)と呼ばれます。
坂越浦会所は、赤穂藩主の茶屋、また村の会所として明治まで使用されてきた
もの。現在の建物は江戸後期(1831)の建築。
奥藤酒造、今も現役、地酒「忠臣蔵」の醸造元。江戸初期に建てられた酒蔵
が並ぶ。
この大道の街並みは最近整備され、それは見事に蘇った。あまりの清潔さは
生活臭までも消し去ってはいないか・・。それとも、江戸時代の日本の街は
かくも整然と美しかったのであろうか・・と。