著者の大平健は聖路加病院の精神科医ですが、「豊かさの精神病理」を読んで以来、妙に腹に落ちる話に感心して、新しい著書が出ると気が付き次第フォローしています。もう一人の著者の倉田真由美は失礼ながら漫画家という以外ほとんど知識がなく紹介欄を読んで「へ~こんな人か」と思ったくらいです。
こんな二人の対談なんですが、硬い話しはほとんどなく精神科の診察の実際も分かって、「ほんまかいな」とか「ふふーん、なるほど」などと思いながら読み終えることができました。
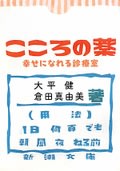
最初の驚きは「訓練を受けた精神科医だと、患者が診察室に入ってきたとたんに、与えるべき薬が頭に浮かびますし、患者が椅子に座ったときには大雑把に病気の見当もつくものです。」という大平の話。倉田は信じてない雰囲気なのですが、精神科は顔を見て勝負なんだそうです。そういえば人は見かけが9割という本もありましたね。映像とかではなく実際に顔を見ないと駄目なんだそうですけど言葉では説明しづらい類のもの。なんとなく分かるような分からないような・・・・
では見たとたん分かるのになぜ診察に長い時間かけるのか。患者にどうしてこうなったのか、不安が残るからです。精神科の特徴でしょうけど病名をつけ薬を出せばいいというものではなく何がきっかけで症状が出たのか突き止める必要があるのです。
患者は自分で原因らしきことをしゃべるのですが本当の原因を分かっているわけではないからです。う~ん、説得力あるな~。
ちなみにこころの病にも流行りすたりがあって、今はリストカットの流行の末期とか。そういえば拒食症とか多重人格が流行ったときもありましたね。でも当然ながら症状自体でなくて原因が重要です。その3大原因は「恋愛」「仕事」「家族」なんですが核家族が増えおのおのが個室に自由にすごすことができるようになって家族の悩みを抱えた患者はどんどん減っているとか。これも「ふ~ん」ですよね。
で、その原因なんですけど、一番のストレスはやっぱりというか「嫉妬」とか。恋愛でも仕事でも勝ち負けにこだわっているとそうなるのかな。
ちょっと余談ですが「うつ」とは鬱と書くのですけど、鬱蒼とした森というときの鬱で、これは草木が生い茂っている様子を言うので「うつ」とは森に迷ったみたいに、思考の出口を見失った状態。落ち込んだ気分のときの「憂」とは違う。対比される「そう」も「躁」で、足がじっとしていない、落ち着かないという意味です。
辛いことがあったら落ち込む(憂)のは当然のことですが、それだけでは思考力が低下(鬱)するまでには至りません。「鬱」の原因になるのは自分では気づかないようなもっと微妙なストレスであり、生活時間を自分でコントロールできないような不規則な生活習慣とか。治療の第一歩はこの小さなストレスの一つ一つを思い出すことであり、生活習慣の建て直しなんですよね。勉強になるな~。
流行り廃りで言えば今は重い精神病の患者は減って「わたし、うつだと思うんです」と自己申告する患者が急増。こういう人は薬は必要ないというか必要ないのに薬を飲んでいる人が多い・・・
それではストレスにはどうすればいいかというとストレスは発散しないのが正解。八つ当たりしても怒鳴っても何の効果もない。う~ん、そうかもね。でもそれではなかなか腹の虫が収まらないんですけど、難しいですね。
腹が立ったらまずは気持ちを抑える、人に不愉快な思いをさせる人というのは勝手に消えていくもの。無神経な人間は、庇ってくれる人もないまま、いつの間にか消えていくでしょうし、人を人と思わない奴は出世するかもしれませんが、老後は家族から見放されます。かわいそうな奴!と相手を哀れんでおくので十分なのです。それでも気持ちを抑えるのが難しいときには意識して、愚痴をこぼすのが上策です。
病気の概念は時代とともに変わっていくんだなーと思いますが、一昔前だったら今テレビで大活躍している「おねえキャラ」は性同一性障害として精神科の教科書に載っていた病気、「おバカキャラ」にも学習障害と定義できます。
学校、病院、いろいろなところにクレマーが増えていますが、共通しているのは世間から見た自分、という考え方すっかり欠落していること。「世間」という鏡を覗き込んで「自分」の姿を見ていたのが、鏡がなくなってしまい、自分が見えなくなり、自分が他人にどう見られるかなんて考えもしないで、理不尽なことをしたり、大げさに文句を言う。クレマーの被害を受けているのが一番は教師で、次いで区役所の職員とか聞くとさもありなんと思います。
倉田真由美との掛け合いも面白く、恋愛についての男と女の考え方とか、まだまだ興味深い話はいろいろあるんですが、全部紹介するのもなんですので是非読んでください。新潮文庫で400円ですけど何倍かの価値はあると思えます。でも私は図書館で借りて読んだのですけどね。
こんな二人の対談なんですが、硬い話しはほとんどなく精神科の診察の実際も分かって、「ほんまかいな」とか「ふふーん、なるほど」などと思いながら読み終えることができました。
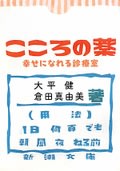
最初の驚きは「訓練を受けた精神科医だと、患者が診察室に入ってきたとたんに、与えるべき薬が頭に浮かびますし、患者が椅子に座ったときには大雑把に病気の見当もつくものです。」という大平の話。倉田は信じてない雰囲気なのですが、精神科は顔を見て勝負なんだそうです。そういえば人は見かけが9割という本もありましたね。映像とかではなく実際に顔を見ないと駄目なんだそうですけど言葉では説明しづらい類のもの。なんとなく分かるような分からないような・・・・
では見たとたん分かるのになぜ診察に長い時間かけるのか。患者にどうしてこうなったのか、不安が残るからです。精神科の特徴でしょうけど病名をつけ薬を出せばいいというものではなく何がきっかけで症状が出たのか突き止める必要があるのです。
患者は自分で原因らしきことをしゃべるのですが本当の原因を分かっているわけではないからです。う~ん、説得力あるな~。
ちなみにこころの病にも流行りすたりがあって、今はリストカットの流行の末期とか。そういえば拒食症とか多重人格が流行ったときもありましたね。でも当然ながら症状自体でなくて原因が重要です。その3大原因は「恋愛」「仕事」「家族」なんですが核家族が増えおのおのが個室に自由にすごすことができるようになって家族の悩みを抱えた患者はどんどん減っているとか。これも「ふ~ん」ですよね。
で、その原因なんですけど、一番のストレスはやっぱりというか「嫉妬」とか。恋愛でも仕事でも勝ち負けにこだわっているとそうなるのかな。
ちょっと余談ですが「うつ」とは鬱と書くのですけど、鬱蒼とした森というときの鬱で、これは草木が生い茂っている様子を言うので「うつ」とは森に迷ったみたいに、思考の出口を見失った状態。落ち込んだ気分のときの「憂」とは違う。対比される「そう」も「躁」で、足がじっとしていない、落ち着かないという意味です。
辛いことがあったら落ち込む(憂)のは当然のことですが、それだけでは思考力が低下(鬱)するまでには至りません。「鬱」の原因になるのは自分では気づかないようなもっと微妙なストレスであり、生活時間を自分でコントロールできないような不規則な生活習慣とか。治療の第一歩はこの小さなストレスの一つ一つを思い出すことであり、生活習慣の建て直しなんですよね。勉強になるな~。
流行り廃りで言えば今は重い精神病の患者は減って「わたし、うつだと思うんです」と自己申告する患者が急増。こういう人は薬は必要ないというか必要ないのに薬を飲んでいる人が多い・・・
それではストレスにはどうすればいいかというとストレスは発散しないのが正解。八つ当たりしても怒鳴っても何の効果もない。う~ん、そうかもね。でもそれではなかなか腹の虫が収まらないんですけど、難しいですね。
腹が立ったらまずは気持ちを抑える、人に不愉快な思いをさせる人というのは勝手に消えていくもの。無神経な人間は、庇ってくれる人もないまま、いつの間にか消えていくでしょうし、人を人と思わない奴は出世するかもしれませんが、老後は家族から見放されます。かわいそうな奴!と相手を哀れんでおくので十分なのです。それでも気持ちを抑えるのが難しいときには意識して、愚痴をこぼすのが上策です。
病気の概念は時代とともに変わっていくんだなーと思いますが、一昔前だったら今テレビで大活躍している「おねえキャラ」は性同一性障害として精神科の教科書に載っていた病気、「おバカキャラ」にも学習障害と定義できます。
学校、病院、いろいろなところにクレマーが増えていますが、共通しているのは世間から見た自分、という考え方すっかり欠落していること。「世間」という鏡を覗き込んで「自分」の姿を見ていたのが、鏡がなくなってしまい、自分が見えなくなり、自分が他人にどう見られるかなんて考えもしないで、理不尽なことをしたり、大げさに文句を言う。クレマーの被害を受けているのが一番は教師で、次いで区役所の職員とか聞くとさもありなんと思います。
倉田真由美との掛け合いも面白く、恋愛についての男と女の考え方とか、まだまだ興味深い話はいろいろあるんですが、全部紹介するのもなんですので是非読んでください。新潮文庫で400円ですけど何倍かの価値はあると思えます。でも私は図書館で借りて読んだのですけどね。
















