
ナチスの時代を描いた映画はホロコーストそのものから、次第にその周辺事象やヒトラーやナチス側を描いた作品に広がっていった。「ソハの地下水道」でそのことに少し触れたが(http://blog.goo.ne.jp/kenro5/s/%A5%BD%A5%CF)、「アドルフの画集」や「ヒトラー ~最後の12日間~」などヒトラーそのものを描いた作品は多いが、ナチス高官あるいはその家族のその後を描いた本作は珍しい。しかも、わずか14歳の少女に幼い兄弟らの命運を任された過酷な物語である。
「さよなら、アドルフ」は、ナチスの高官家庭として何不自由なく暮らし、またヒトラー=ナチスの教え、反ユダヤ主義を内面化していた少女ローレが、両親を囚われ、ドイツ北部ハンブルク近郊の祖母の家を目指す過程で、隠されていた事実と両親や崇拝するヒトラーやナチスの本当の姿や、ナチス敗退後の混乱した国で大人の邪悪な所業を経験することで成長する物語である。そして、その成長にはローレが唾棄していたユダヤ人(と少なくともローレは思っている)青年の援助がかかわっている。
ローレの知ったナチスの蛮行は、まずホロコーストの写真を見ることからはじまる。そこに写っていた軍人は父と同じ軍服を来ていたため、自分の父親が長い間家を空けているあいだ何をしていたかを知ることになる。道すがら大人たちはあの写真はでっち上げだとか、ユダヤ人の大量殺戮を否定しようとするが、写真の衝撃にローレは苛まされる。そして、強姦の上無残に殺された女性や、ナチス敗北を知って拳銃自殺した蛆のわく男性…。ローレの目に映るものはすべて醜く、そして物乞いするローレに冷たい。現実を知ったローレに手を差し伸べたのは収容所から出てきたと思しい寡黙な青年トーマス。そして大きな川を渡るため漁師に体で払おうとするまでになったローレ。しかしローレに覆いかぶさろうとした漁師を撲殺したのはトーマスだった。「今は悪い奴ばかり」と言い放つトーマスに頼らざるを得ない現実。
トーマスも去り、幼い弟を失いながらやっとの思いで祖母の家にたどり着くが、ナチスの思想=規律や統制を貴び、厳格な振る舞いを強要する祖母についにローレは爆発する。
自分が信じてきたこと、当たり前と思い過ごしてきた前提が覆されるのは辛いし、窮地に陥っている自分らを助けてくれたのが忌み嫌っていた対象=ユダヤ人、であることを受け入れるにはとてつもない葛藤があるであろうし、ローレはまだ14歳。いや、14歳といえば大人直前の年でもある。彼女が戦後どのように価値観の転換を受け入れたか想像するしかないが、真実は知らないより知ったほうがいい。ましてや自国・自民族の負の歴史ならなおさらだ。命は助かったが、これからは頑迷な祖母の姿勢=ナチスの思想そのまま、と闘っていかなければならないローレは、自分らをこのような目に合わせた両親を含むナチスの大人たちを見限るとともに、それまで盲目的に信奉してきたヒトラーに告げることができたのだろう。「さよなら、アドルフ」と。
ところで、逃避行の最中、ローレの幼い双子の弟らがナチス軍隊を称揚する歌を歌って、助けてくれたドイツ人老婆を喜ばせるシーンがある。ナチスドイツでは「ヒトラー・ユーゲント(ヒトラーの青年団)」という組織において、徹底的なナチス式教育が行われたが、全体主義国家では共通に見られる政策で、日本では子どもたちが皇民化教育として天皇絶対の軍国主義を叩きこまれた。
ドイツでは「さよなら、アドルフ」のようにナチス教育を相対的に描き、その罪をいつまでも告発し続けているが、翻って日本はどうか。教科書検定を制限し、再び国定化をも狙う安倍自民党政権では、戦前の天皇制軍国主義と同一ではないにしても国家主義教育の危険性は大きく増している。安倍首相のトモダチのNHK経営委員は特攻隊をある意味美化する小説を書き、南京事件はなかったとか言っているそうな。まともな戦時中映画もつくれないこの国ならではの現状を象徴しているようだ。
「さよなら、アドルフ」は、ナチスの高官家庭として何不自由なく暮らし、またヒトラー=ナチスの教え、反ユダヤ主義を内面化していた少女ローレが、両親を囚われ、ドイツ北部ハンブルク近郊の祖母の家を目指す過程で、隠されていた事実と両親や崇拝するヒトラーやナチスの本当の姿や、ナチス敗退後の混乱した国で大人の邪悪な所業を経験することで成長する物語である。そして、その成長にはローレが唾棄していたユダヤ人(と少なくともローレは思っている)青年の援助がかかわっている。
ローレの知ったナチスの蛮行は、まずホロコーストの写真を見ることからはじまる。そこに写っていた軍人は父と同じ軍服を来ていたため、自分の父親が長い間家を空けているあいだ何をしていたかを知ることになる。道すがら大人たちはあの写真はでっち上げだとか、ユダヤ人の大量殺戮を否定しようとするが、写真の衝撃にローレは苛まされる。そして、強姦の上無残に殺された女性や、ナチス敗北を知って拳銃自殺した蛆のわく男性…。ローレの目に映るものはすべて醜く、そして物乞いするローレに冷たい。現実を知ったローレに手を差し伸べたのは収容所から出てきたと思しい寡黙な青年トーマス。そして大きな川を渡るため漁師に体で払おうとするまでになったローレ。しかしローレに覆いかぶさろうとした漁師を撲殺したのはトーマスだった。「今は悪い奴ばかり」と言い放つトーマスに頼らざるを得ない現実。
トーマスも去り、幼い弟を失いながらやっとの思いで祖母の家にたどり着くが、ナチスの思想=規律や統制を貴び、厳格な振る舞いを強要する祖母についにローレは爆発する。
自分が信じてきたこと、当たり前と思い過ごしてきた前提が覆されるのは辛いし、窮地に陥っている自分らを助けてくれたのが忌み嫌っていた対象=ユダヤ人、であることを受け入れるにはとてつもない葛藤があるであろうし、ローレはまだ14歳。いや、14歳といえば大人直前の年でもある。彼女が戦後どのように価値観の転換を受け入れたか想像するしかないが、真実は知らないより知ったほうがいい。ましてや自国・自民族の負の歴史ならなおさらだ。命は助かったが、これからは頑迷な祖母の姿勢=ナチスの思想そのまま、と闘っていかなければならないローレは、自分らをこのような目に合わせた両親を含むナチスの大人たちを見限るとともに、それまで盲目的に信奉してきたヒトラーに告げることができたのだろう。「さよなら、アドルフ」と。
ところで、逃避行の最中、ローレの幼い双子の弟らがナチス軍隊を称揚する歌を歌って、助けてくれたドイツ人老婆を喜ばせるシーンがある。ナチスドイツでは「ヒトラー・ユーゲント(ヒトラーの青年団)」という組織において、徹底的なナチス式教育が行われたが、全体主義国家では共通に見られる政策で、日本では子どもたちが皇民化教育として天皇絶対の軍国主義を叩きこまれた。
ドイツでは「さよなら、アドルフ」のようにナチス教育を相対的に描き、その罪をいつまでも告発し続けているが、翻って日本はどうか。教科書検定を制限し、再び国定化をも狙う安倍自民党政権では、戦前の天皇制軍国主義と同一ではないにしても国家主義教育の危険性は大きく増している。安倍首相のトモダチのNHK経営委員は特攻隊をある意味美化する小説を書き、南京事件はなかったとか言っているそうな。まともな戦時中映画もつくれないこの国ならではの現状を象徴しているようだ。















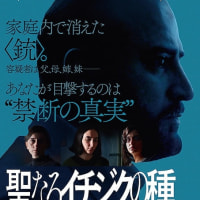


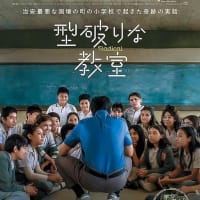






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます