
巷では「昭和100年」と浮かれている向きもあるが、100年前の1925年は、日本法政史上最も悪法の一つ「治安維持法」が制定された年である。当初「反共」、無産主義者を処罰の対象としていたのが、幾度かの改定によって自由主義者やキリスト者なども弾圧されたのは周知のことである。
「聖なるイチジクの種」は、厳格なイスラム法解釈のもと、女性にヒジャブの着用ほか様々な制限を課すイランの実状と、そういった性差別を一家庭内でも貫徹せんとして壊れていく「家族」の姿を描いた問題作である。監督・製作・脚本のモハマド・ラスロフは、政府による拘束を逃れ、秘密裏に出国。出国中に本国で「鞭打ち、私財没収、禁固刑8年」の判決が出されたことを聞かされ、公の場への登場があやぶまれたが、カンヌ映画祭会場に現れたのだった。カンヌでは審査員特別賞を受賞する。
裁判所に務めるイマンは、念願の調査官に昇進。仕事は、検察が請求するままに被告に死刑を含む重罰の許可証を発布すること。護身用のためと、上司から拳銃を渡される。ある日、その拳銃が寝室の引き出しから消えた。学生らの民主化運動に共鳴し、学内で重傷を負った友人を匿うなど「反体制的」な娘らと、何事にも夫に従順な妻ナジメ。一体、拳銃はどこへ、誰が盗んだのか。
イラン社会を描く本作のテーマは、「家父長制」と「監視社会」であると思う。イスラム国家、それも1979年の新米パフラヴィー政権の崩壊後、2005年から2013年まで大統領を務めたアフマディーネジャード政権下では、その家父長制的政策、強権主義が強まったという。イマム・ナジメ一家でもその姿はよく描かれる。娘二人は父親の庇護の元自由を謳歌できないばかりか、母ナジメは全て父親に従いなさいと言うばかり。自分の意見を持つことはない。
イマムの口癖は「神がお赦しになる/ならない」、「神の思し召しのとおり/でない」。そこでは一公僕たる自身の地位や職務もそこに帰することによって、疑ったり、深く考えたり、自立・自律に入り込もうとはしない。国家そのものが家父長制なのだ。
一方の「監視社会」は言うまでもないだろう。本作の着想の一つが2022年9月にヒジャブを適切に着用していないとし、道徳警察に拘束されたマフサ・アミニさん(22)の急死に端を発したヒジャブ(非着用)・デモである。イランにおいてもSNSの発展により、デモは瞬く間に全国に広がるとともに、そのSNSの傍受や取締りを政権側は強行した。映画でも娘らはスマホを巧みに操り、親が知らない情報を得るシーンが何度もあった。
ネット上に「殺人者」として氏名、住所などを晒され、家族を疑ったイマンは、田舎の旧家にナジメと上の娘を監禁して口を割らせようとする。辛くも逃げたナジメと娘らを追うイマンは完全に常軌を逸していて、下の娘に拳銃を向ける。
ラスロフ監督の描くイランはおそらく誇張なく、そのままで、そのような社会に危機を覚えているのは明らかだ。そしてなんとか「民主化」に繋げたいと。しかし、現状では監督はもう祖国には帰れまい。
映画の中でイマンや職場の同僚だったか、「外国が全てイランを悪者にしている。」との発言があった。現政権を支持する(せざるを得ない)層からは、そのように強権主義の合理化や納得できる説明が必要なのだろう。同時に不明朗な政権運営、警察国家体制にきちんと異議申し立てする若者らの姿もある。
イランよりはるかに「民主的」で強権国家ではない日本でも「家父長制」のくびきは強い。そして治安維持法がなくなったと言って安心できるだろうか。安倍政権下では「秘密保護法」「共謀罪」などの市民監視体制が進み、現在の経済安全保障体制下ではますますその重圧は厳しくなっている。軍事費増大の理由とともに政権が口にする「我が国をめぐる領海など周辺、いつになく厳しい国際情勢」。イラン政権支持者の「他国が自国を悪者にする」と相似形である。










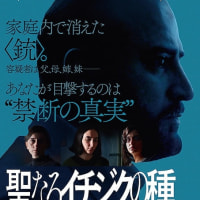


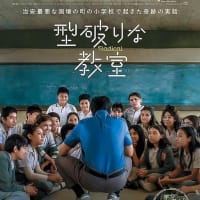











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます