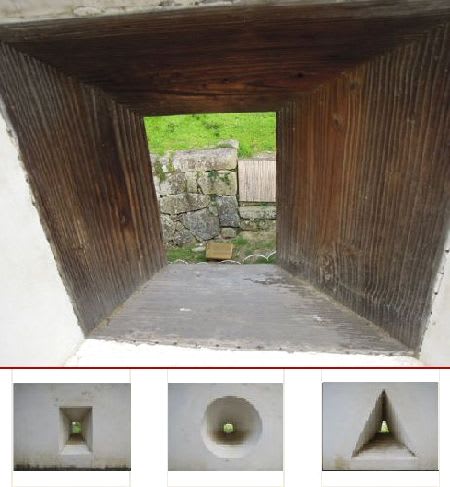昨日のことですが・・・JR三宮に10時頃着で出かけていると
お昼過ぎのニュースで
11日午後1時過ぎにJR神戸線の新駅「摩耶駅」の建設現場で工事用の足場が突然崩れ、線路をふさぐように落下したため、JR神戸線・六甲道~灘駅間で建設中の新駅で甲子園口~西明石駅間で運転を見合わせています・・・。
「神戸ルミナリエ」の会場で、11日午前5時半ごろイルミネーションの一部が倒れているのが見つかりましたが安全であることが確認できたので、噴水広場の作品を除き通常通り点灯されるそうです。
いつもより路上の落葉が多いと思ってましたが、昨夜は強風だったのですね。
でも夕方には帰れるだろうと軽く考えていると、どうも無理なことが分かり
JRは諦めて21時30分頃に、三宮から初めて阪急電車で帰ることにしました。
(発生から9時間後の午後22時過ぎに運転が再開されました。)
阪急電車は満員状態だと覚悟して、阪急電車で帰る事にしたのですが・・・
乗車券を買うときに、JRでは810円なのが阪急電車だと半額の400円でした。
間違っていないか何度も確認しても不安でしたが、その時は精算すれば良いと
思って改札口に向かうと、問題なくスッと出ることができました。(*^^*)
30分ほど帰るのは遅くなりましたが、こんなに乗車料金が違うことに驚き!
数年前まで車ばかりで電車に乗らなかったので知らなかっただけなんですね。
お昼過ぎのニュースで
11日午後1時過ぎにJR神戸線の新駅「摩耶駅」の建設現場で工事用の足場が突然崩れ、線路をふさぐように落下したため、JR神戸線・六甲道~灘駅間で建設中の新駅で甲子園口~西明石駅間で運転を見合わせています・・・。
「神戸ルミナリエ」の会場で、11日午前5時半ごろイルミネーションの一部が倒れているのが見つかりましたが安全であることが確認できたので、噴水広場の作品を除き通常通り点灯されるそうです。
いつもより路上の落葉が多いと思ってましたが、昨夜は強風だったのですね。
でも夕方には帰れるだろうと軽く考えていると、どうも無理なことが分かり
JRは諦めて21時30分頃に、三宮から初めて阪急電車で帰ることにしました。
(発生から9時間後の午後22時過ぎに運転が再開されました。)
阪急電車は満員状態だと覚悟して、阪急電車で帰る事にしたのですが・・・
乗車券を買うときに、JRでは810円なのが阪急電車だと半額の400円でした。
間違っていないか何度も確認しても不安でしたが、その時は精算すれば良いと
思って改札口に向かうと、問題なくスッと出ることができました。(*^^*)
30分ほど帰るのは遅くなりましたが、こんなに乗車料金が違うことに驚き!
数年前まで車ばかりで電車に乗らなかったので知らなかっただけなんですね。