
浴衣姿の若い人が街を闊歩している
街が一気にカジュアルになって若々しくなる
男の子はみんな帯が胸高で裾が広がり涼しそう
女の子は体ができていて胸や腰が主張されピーーんと貼った肌がはちきれそう
みんな嬉しそうに着ていてそれがいい
浴衣は湯帷子から
やんごとなき人たちは昔と言っても大昔だが「湯文字」(これもお湯を使うという女房詞)に入る時の衣服が湯帷子で下着が湯文字だった
湯帷子は麻なのでさどや涼しかったに違いない
宮下がり、城下がりのお女中たちが湯帷子を着る貴人たちの姿を人々に話、庶民は木綿を着てそれがお風呂上がりに羽織ることから浴衣という名前がついた
という教え 特に歌舞伎役者がそれぞれの柄を作ったので同じ柄を着たいご贔屓筋に浴衣は大人気 江戸浴衣の名店竺仙は浅草で歌舞伎浴衣を言ってに引き受け、粋な浴衣を染めていた
木綿は室町時代に一気に日本中のあちこちで作られるようになったので麻を着るより安価であった
それ以来浴衣は木綿という相場
当時の浴衣はコーマ織りという細い上等な糸を使っていて注染染め、中型染め長板染めという手仕事であった
色は藍染と決まっていた 白地の浴衣と藍染が主流で子供浴衣に金魚や朝顔の色浴衣があった
昼は藍、夜は白地と決めていたお屋敷家族もいた
お金に不自由のなお妾さんは「ちりめん浴衣」を着ていた・特に絽縮緬が人気
これは竺仙の前社長から聞いた話
今でも残る藍染町は藍染職人がいた町だ。吉原の高尾太夫は藍染職人と恋に落ち身請けされ藍染屋の女房になった
浴衣に始まり浴衣に終わる
世の中の移り変わりとともに浴衣の姿も替っていく
それもまた人の意志だと思う
取材してきた知識を多くの方と共有したいと思う
#毎月第2、3,4火曜に18時から 会費3500円 #秋櫻舎
#浴衣 #藍染職人 #吉原の高尾大夫 #中谷比佐子 #ちりめん浴衣 #歌舞伎浴衣 #湯文字 #湯帷子 #木綿浴衣 #コーマ浴衣 #竺仙の前社長












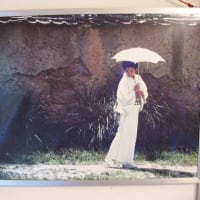












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます