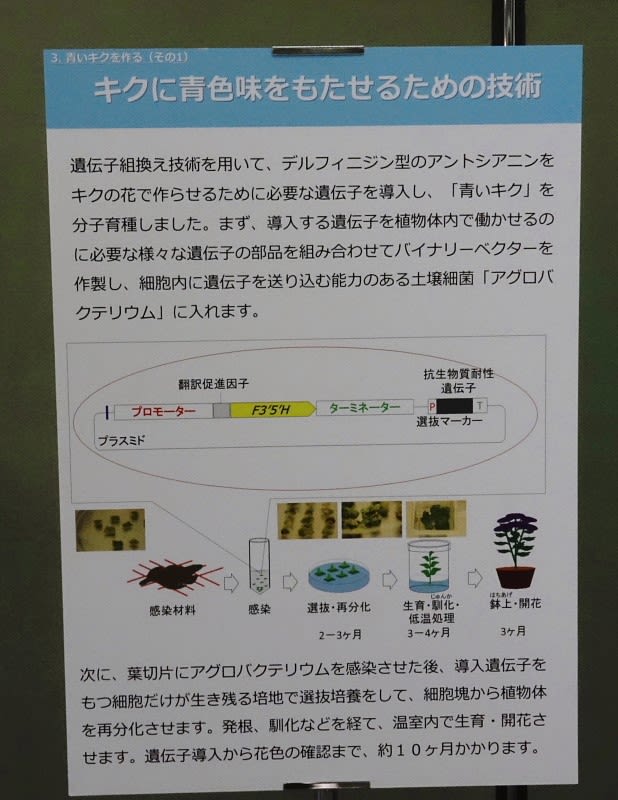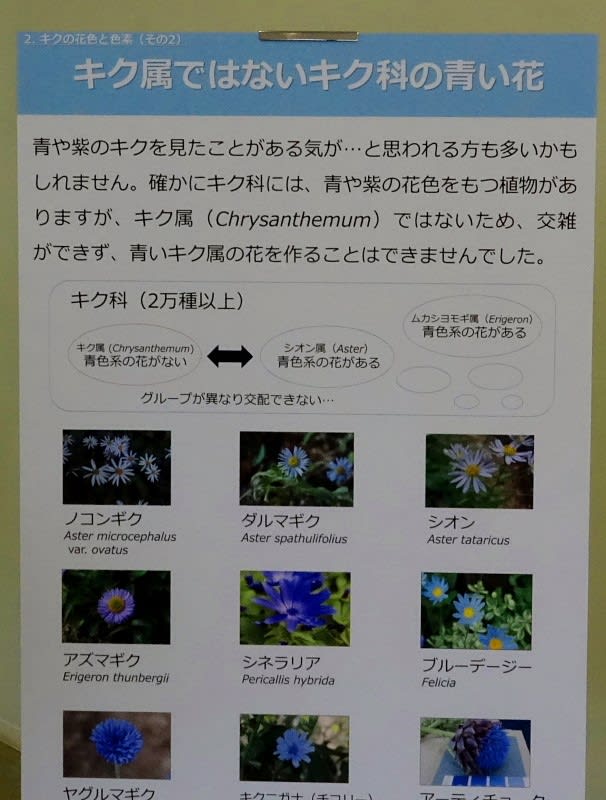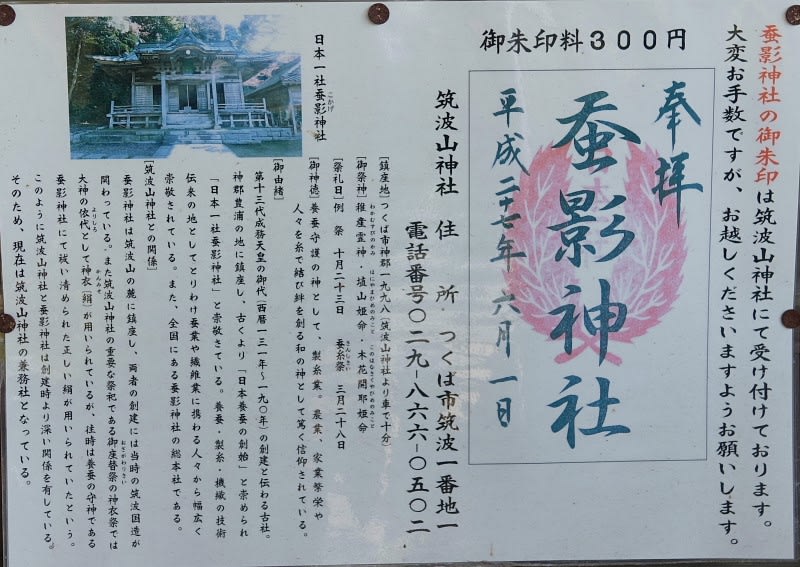3.11でどこかに行こうとしたが、屋根の雨音が激しいので断念した
そのかわり地元の山で撮影したコセリバオウレンの花の表情を掲載する。
昨日のオニシバリで、雌雄異株の花は懲りたので、コセリバオウレンも
雌雄異株と言われる花だが、はっきりとわかる花以外は決めつけないことにする

コセリバオウレンの両性花に花粉だらけのハナアブ?

上の写真をトリミング拡大した写真
早春の花の少ない時期なので、ハナアブにとってもコセリバは救いの神だし
コセリバにとっても、受粉を助けるハナアブは救いの神だろう。
撮影させてくれてありがとう。虫媒花の証明だね。

こちら向きのハナアブ

両性花の花のアップ

雄花が数本

雄花が2本

雄花

退化した雌蕊のようなものが見える花
先日落下して壊れた60ミリマクロが使えなくなり、銀塩時代のカビの生えた
レンズで撮影しているので、これ以上は追及しない(笑)

雌雄異株と言われるが、左の株は雄花と両性花をつけているようだ

杉林の群落1

群落2

群落1

4輪の花をつけている株、左上に退化したような雌蕊があるような

4輪の両性花
上の写真の中から、雄花をトリミングして、各部の名前を入れてみた写真
雄花だけは間違いないと思う(笑)

雨が上がったら種まきするかな
雨が多いので水まきしなくていいから助かる。
そのかわり地元の山で撮影したコセリバオウレンの花の表情を掲載する。
昨日のオニシバリで、雌雄異株の花は懲りたので、コセリバオウレンも
雌雄異株と言われる花だが、はっきりとわかる花以外は決めつけないことにする

コセリバオウレンの両性花に花粉だらけのハナアブ?

上の写真をトリミング拡大した写真
早春の花の少ない時期なので、ハナアブにとってもコセリバは救いの神だし
コセリバにとっても、受粉を助けるハナアブは救いの神だろう。
撮影させてくれてありがとう。虫媒花の証明だね。

こちら向きのハナアブ

両性花の花のアップ

雄花が数本

雄花が2本

雄花

退化した雌蕊のようなものが見える花
先日落下して壊れた60ミリマクロが使えなくなり、銀塩時代のカビの生えた
レンズで撮影しているので、これ以上は追及しない(笑)

雌雄異株と言われるが、左の株は雄花と両性花をつけているようだ

杉林の群落1

群落2

群落1

4輪の花をつけている株、左上に退化したような雌蕊があるような

4輪の両性花
上の写真の中から、雄花をトリミングして、各部の名前を入れてみた写真
雄花だけは間違いないと思う(笑)

雨が上がったら種まきするかな
雨が多いので水まきしなくていいから助かる。