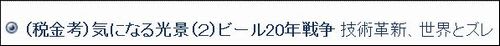長野県諏訪市と諏訪郡下諏訪町にまたがる霧ヶ峰高原の八島湿原では、高原を好むホオアカが元気に飛び回っています。
八島湿原の南側の木道を進みました。遠くに、そびえている車山(標高1925メートル)の麓に近づきます。
八島湿原の東側にある御射山遺跡(みさやまいせき)近くでは、一面の草原が広がっています。霧ヶ峰高原らしさを感じさせる地域です。

この草原の主役は、濃い黄色い花のマルバダケブキ(丸葉岳蕗)です。キク科メタカラコウ属の多年草です。

タテハチョウ系のチョウがマルバダケブの花に群がっています。
タテハチョウ系のチョウが、ハクサンフウロの花に留まっています。

タテハチョウ系のウラギンスジヒョウモンかミドリヒョウモンではないかと推測しています。
森の中にいたチョウです。ルリタテハではないかと推定していますが、少し違う感じもしています。

八島湿原の南側の木道を進むと、ヤナギランなどが咲いている草原部分に、ホオアカが元気に飛び回っています。
レンゲツツジの木の枝に留まっているホオアカの番です。オスのホオアカは活動的です。

枯れ木の枝の上で、たぶん縄張りを主張して鳴いているホオアカです。


秋の七草の一つのオミナエシの黄色い花がもう草陰で咲いています。

八島湿原の草原では、短い夏の中で、高山植物が次々と花を咲かせています。ホオアカなどの野鳥も元気に飛び回っています。
八島湿原の南側の木道を進みました。遠くに、そびえている車山(標高1925メートル)の麓に近づきます。
八島湿原の東側にある御射山遺跡(みさやまいせき)近くでは、一面の草原が広がっています。霧ヶ峰高原らしさを感じさせる地域です。

この草原の主役は、濃い黄色い花のマルバダケブキ(丸葉岳蕗)です。キク科メタカラコウ属の多年草です。

タテハチョウ系のチョウがマルバダケブの花に群がっています。
タテハチョウ系のチョウが、ハクサンフウロの花に留まっています。

タテハチョウ系のウラギンスジヒョウモンかミドリヒョウモンではないかと推測しています。
森の中にいたチョウです。ルリタテハではないかと推定していますが、少し違う感じもしています。

八島湿原の南側の木道を進むと、ヤナギランなどが咲いている草原部分に、ホオアカが元気に飛び回っています。
レンゲツツジの木の枝に留まっているホオアカの番です。オスのホオアカは活動的です。

枯れ木の枝の上で、たぶん縄張りを主張して鳴いているホオアカです。


秋の七草の一つのオミナエシの黄色い花がもう草陰で咲いています。

八島湿原の草原では、短い夏の中で、高山植物が次々と花を咲かせています。ホオアカなどの野鳥も元気に飛び回っています。