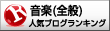津田清氏
6月26日。一昨年までのこの日は、一年365日のうちの、なんの変哲もない一日だった。
昨年6月26日の朝、「その方」が亡くなった、という知らせが入った。
たしか二度目にお会いした時である。
あるバンドの一員として、一年ぶりにその方のバックを務めさせてもらった時のことだ。日本有数のテナー・サックス奏者であるその方の熱演で、客席は盛り上がっていた。
ある曲で自分のソロが終わるや否や、その方はいきなり後ろを振り返った。まだまだ未熟だったぼくは、「何か拙いことを弾いてしまったか」と一瞬首をすくめたが、次の瞬間、沸き上がってきた喜びで体中がいっぱいになってしまった。その方は目を細めて一言だけ、こう言ってくれたからだ。
「良うなってるでぇ!」
その方にほめられたから嬉しくなったのではない。地方の、どこの誰ともわからない名も無いベース弾きの音を覚えていてくれたことに感激したのだ。
その翌月か、翌々月だったと思う。所用で大阪に行ったぼくは、その方に挨拶がてら電話を入れた。あいにく留守だったので、メッセージだけ残しておいた。
翌日に帰ってから解ったのだが、その方は留守電を聞いて、すぐあちこち心当たりに電話して、ぼくをつかまえようとしてくれたらしい。ぼくはその人柄にすっかり参ってしまった。
その方は、プロデューサー業、プロモーター業のほうが多忙になっていたため、サックスを吹く機会は減っていたそうだが、それでも時々大阪に行ってはその方の音を聴かせて頂いていた。
音楽のこと、ミュージシャンとしてあるべき姿、人間として大事にしなければならないこと、はてはぼくの家族への気遣いに及ぶ、実にいろんな話をして頂いた。
「みんなに可愛がって貰える人間にならな、あかん」
「お客の心に響くような音を出さな、あかん」
これらの言葉は、ぼくにとっての宝物だ。
「お前、加古川へ行け」
こう言われたのはある年の12月だ。「加古川にはな、前にわしのバンドにおった、ごっつええピアノ弾きがおんねん。お前、そこへ行け」
聴いた瞬間、背筋に電流が走るような素晴らしい音を出すピアニストだった。まるで、自分の身を削って音を出しているような、そんな音だ。その後、もしぼくが成長しているとするなら、そのピアニスト有末佳弘氏に負うところは非常に大きい。
音楽についての悩みは尽きることがなく、落ち込んでもがくたびに、おこがましくもその方に電話をして話を聞いて頂いていた。
ある日のことだ。
「お前の住んでいる町で一番のベース弾きになるとか、西日本で一番のベース弾きになるとか、そんな小さいこと言うてたらあかん!相手はなあ、世界やぞ。世界が相手なんや!」
苦しい時、煮詰まった時には必ずこの言葉を思い出す。
「Flamingo」という曲が好きなんや、と伺ったことがある。しかしぼくはそれよりは、その方の吹く「What A Wonderful World」が大好きだった。
その方がテナー・サックスで歌う「Wonderful World」には、本当に「お前なあ、ほんまにこの世界は素晴らしいもんなんやで」と語りかけられている気がしてならなかったからだ。
訃報を聞いたのが26日。翌27日は、なんという縁なのだろう、加古川在住の有末佳弘さんのライブにベーシストとして参加させて頂くことになっていたのだ。その方は、ぼくと話すたびに、必ず「お前な、有末のこと頼むで」と言っていたものだ。まるで息子の心配をするように。
ライヴ終了後、有末夫妻とともに大阪へお通夜に伺った。
有末さんの落胆はぼくの何倍もの大きさだったろう。
ぼくはお別れをしながら、ふと、その方はなんとか26日まで頑張っていてくれたのではないだろうか、と思った。ぼくが加古川に向かう足で、そのまま大阪へ行くことができるように。そして有末さんとぼくが揃ってお通夜に来られるように。普段からそういう気遣いをして下さる方だったから。
ミュージシャンとしても人間としても、まだまだぼくは未熟である。未だにつまづき、悩み続けている。
しかしその方は、そんなぼくをあの世とやらから見ながら、
「お前なあ、世界が相手やぞ、世界が」と、もどかしそうに言っているに違いない。
「その方」こと、テナー・サックスの名手、津田清氏は2004年6月26日に69歳で亡くなられた。

津田清さん。右はぼくです。