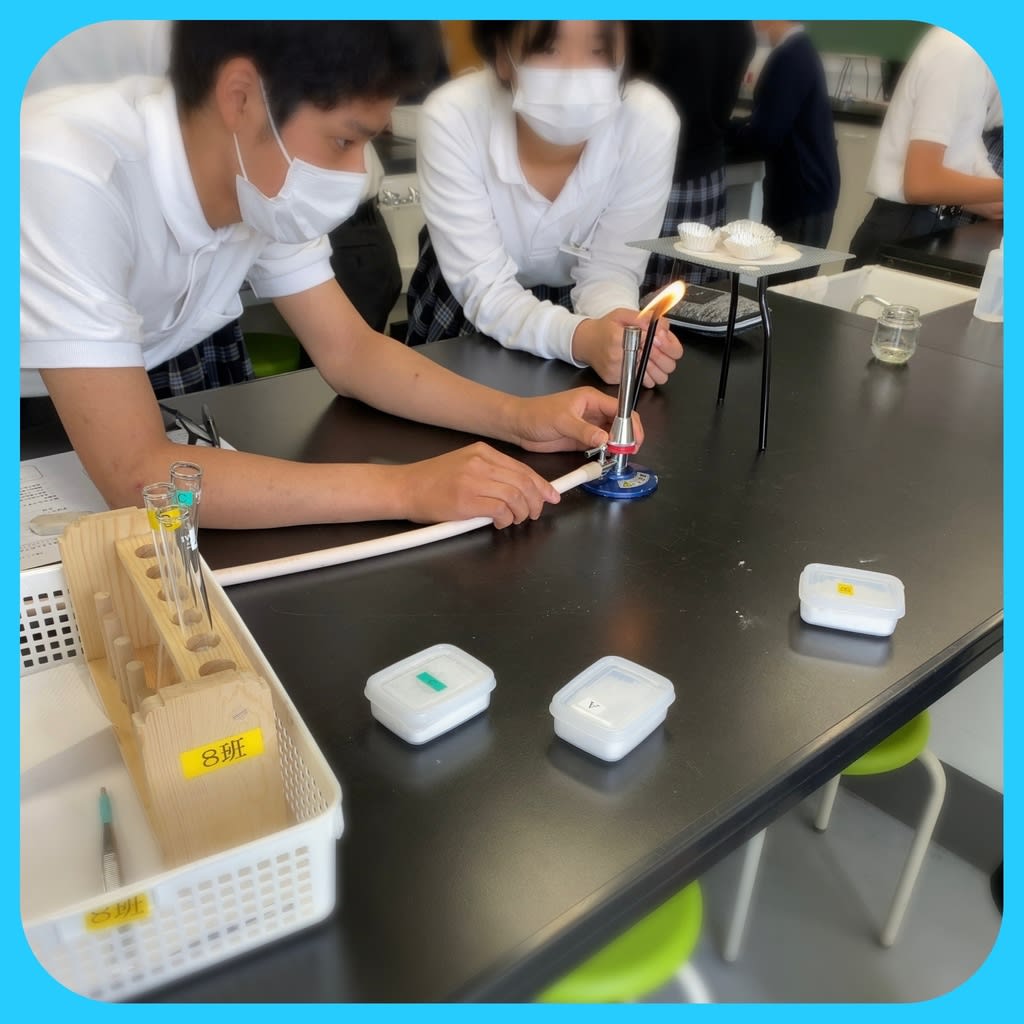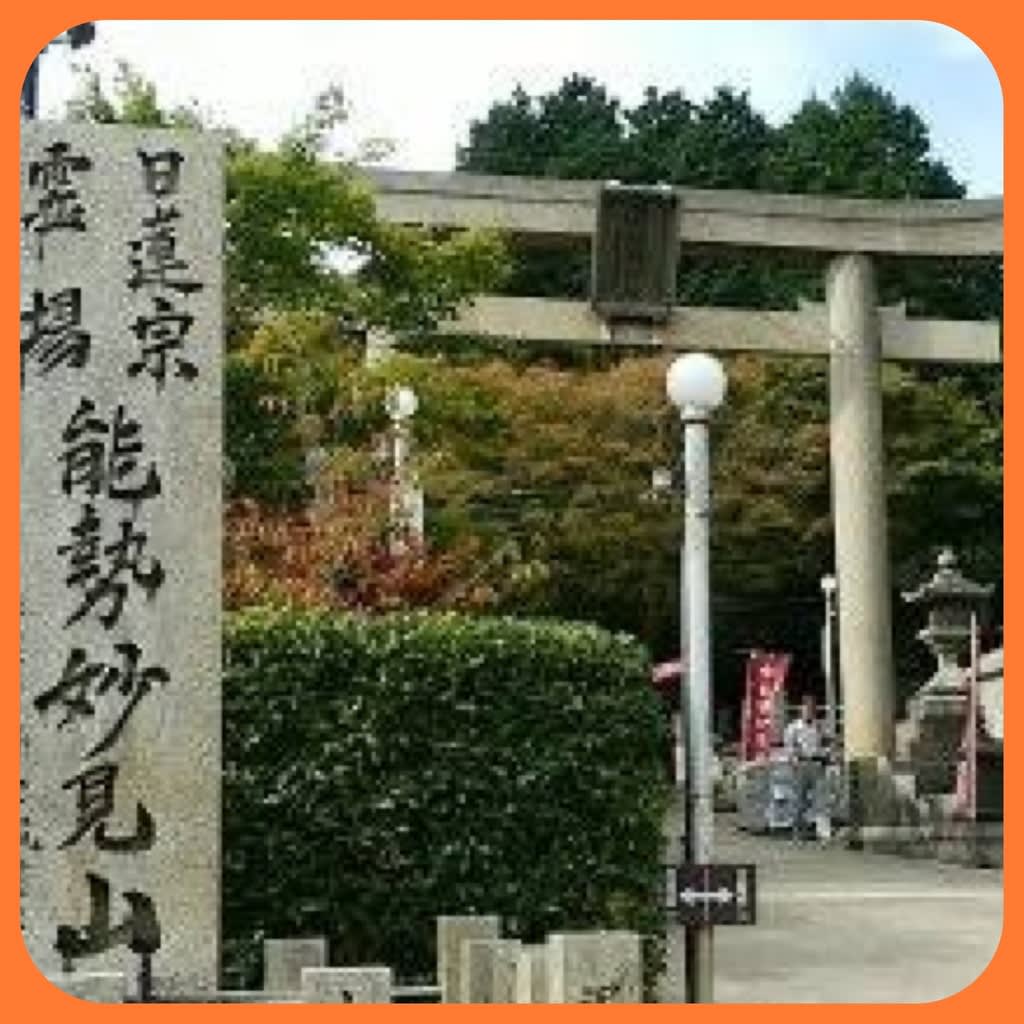このブログでは、中学校の部活動の地域への移行を何度かとりあけています。
そこでは、地域の移行に関わっていくつかの課題があり、一つは土日の活動を指導してくれる人が確保できるかです。
もう一つは自治体がその事業を運営していく財政的な問題です。
そこで、今回は財政的な問題をもう少し掘り下げて考えます。
そもそも、中学校の部活動は、教育課程には含まれてはいないが、「教育活動の一環」として、学校の教員のほぼ無償の勤務により長年にわたり維持されてきたのです。
ほぼ無償というのは、平日の部活指導には勤務時間が過ぎても、時間外手当はゼロです。
土日の部活指導には、わずかな手当が時間に応じて出ます。
つまり、今までは、日本の中学生のスポーツ技術の向上やスポーツに親しむ機会提供は、中学校の教員(顧問)のボランティア的・「献身的」なほぼ無償の活動で支えられていたのです。
「費用・手当」を低く抑えることで、青少年に運動に親しむ時間を保障し、そこからオリンピックに出る選手も育つこともある、「安上がり」の育成方法だったのです。
しかし、今回の地域移行で、地域のスポーツクラブ等にお願いするのなら、これまでの報酬の水準では制度が成り立ちません。
地域移行を先行実施している自治体の場合、いま土日の指導には、コーチに1000円から2000円の時給が支払われています。
そうすると、クラブに何人の生徒が来るかにもよりますが、月にすると15万円程度になるのではないでしょうか。
これでは低すぎて、コーチのなり手が確保できないかもしれません。
地域への移行が言われる前から、たとえば大阪府では「外部コーチ」の制度がありました。
これは、学校の教員が顧問を務め指導して、責任をもつ、試合を引率するという確固たる旧来の制度の枠組みの中で、専門の外部コーチが生徒の技術向上のため、お手伝いで部活に来てくれるというものでした。
そこでは、ボランティア活動的な意味合いでしたので、わずかながらの謝金が自治体から支払われていました。
外部コーチも、「生徒さんの役に立つのなら」と無償で協力したいという気持ちで、学校に直接申し込まれる人もいました。
しかし、今進める地域移行は、それとは性質が違います。
土日に指導すれば、きっちりとお金が支払わなければなりません。
当然ながら、保護者が月謝を払わなければなりません。
自治体の財政が厳しくて十分な報酬が確保できないなら、保護者負担は増えるでしょう。
地域移行が制度破綻しないためには、国は大枠だけをきめて、あとは自治体に丸投げするのでなく、財政の乏しい自治体に十分な補助金が出せる財源を確保しなければなりません。
この制度改革に失敗は許されません。