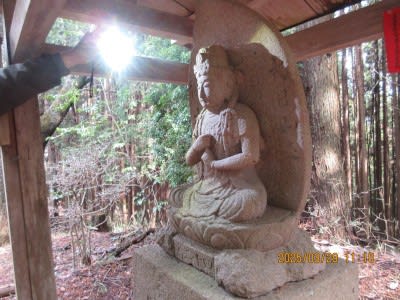長居公園
一気に春色に染まった公園
ジャカランダは落葉した。たくさんの果実が見える。
ベニバナトキワマンサク あざやかなピンク
ハルニレは果実
ベニバスモモ 
ロドレイア あでやかな花
トラックの縁のイチョウも芽吹いて来た。
枝は高いが、望遠で撮ってトリミング 雄花(つぼみ)が見える(赤の矢印)
サクラは満開、散歩したり、シートに座ったり・・
騒ぐ人もいないので静か。
イスノキ 赤い葯が出てきれい。 先端の花には2本の雌しべが見える。
もうすぐ開花するが、一番きれいなのはつぼみの今の時期だ。
コブクザクラ 冬もずっと咲き続けていたが、今が一番花が多い。
少し葉が見えてきた。
長居植物園
公園内にも雑草が生えている。
アオオニタビラコ 普通、株元から花茎がたくさん出る。
茎葉はつかない(少数つくことも)
アカオニタビラコ 花茎は普通1本、毛が多い。 茎葉がつく。
ロゼット葉は赤みを帯びる。
雑種もできるらしい。
ツバキは満開
玉之浦
大輪で咲き分けのツバキ 白と赤が混じった花
同じ木に 濃い赤一色の花もある。
この大輪ツバキは中心部が虫に食害されているものが多い。
つぼみを割ってみたら、イモムシがでてきた。
幼虫がツバキを食害するスギタニモンキリガの仲間らしい。
きれいなツバキが台無しだ。
マグノリアの仲間も見頃。
コブシ・サラサモクレン・シデコブシなど。
モクレンの仲間は雌性先熟 この花は雄しべが花粉を出している。
冬から咲き続くジュウガツザクラ 今が満開だ。
春は花数が多く、花も八重っぽくなり華やかになる。
ヒメリュウキンカ キクザキリュウキンカと分けることもあるらしいが、図鑑によっては別名とされたり・・はっきりしない。
ただ、リュウキンカとは全く違うのに、混乱している。
公園の中にもリュウキンカの名札があったりする。
生育場所や果実の形など全く別ものだ。
雑草の中に見慣れない草があった。
キュウリグサに似るが、全体に大きく、葉も毛が多くふわふわ。
ノハラムラサキという帰化植物のようだ。
いろんなものが入ってくるなあ。