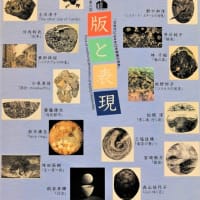絵画や版画作品を制作するときには必ずBGMを聴いている。音楽は僕にとっては耳と脳の栄養となる食物に近い感覚として存在している。自慢ではないがコテコテの演歌以外はクラッシック、ポップス、ロック、ブルース、ジャズ、レゲエ、ファド、フォルクローレ、津軽三味線など、たくさんの種類の音楽を聴いてきた。長い時間流すので一つのジャンルだけではすぐに飽きてしまうのだ。譜面もろくすっぽ読めず、楽器も弾けない音痴なのだが、聞くことには妙なこだわりがあって、以前はよく季節によって聴くジャンルを替えていた。たとえば、春から夏の昼間はロックやレゲエを聴き、夜間はジャズを聴く。秋から冬にかけてはクラッシック音楽を中心に聴いていた。それから状況によってもジャンルを替えた。絵画を描いている時、版画の細かい彫りの作業の時には、バロック系の音楽を聴いて集中力を高め、版画の摺りの労働の時には、ワークソングとしてシカゴ・ブルースを聴いていたりした。その延々と続くディスクの交換が面倒くさくなってくるとラジオのFMの音楽番組に替える。そして本当に制作に集中してくると何もかけなくなる。
今年になって突然クラッシックのブルックナーに目覚めた。中でも交響曲を集中的に聴いている。20代に友人に勧められて初めて聴いた時には、その演奏時間の長さと同じようなメロディーの繰り返しに閉口し、LPレコードの再生途中に居眠りをしてしまった記憶がある。それから至極難解なイメージを持ってしまった。つまり一度挫折したのである。
アントン・ブルックナー(Anton Bruckner 1824-1896) と言えば、対位法を駆使した交響曲と崇高な宗教曲を数多く生み出した19世紀オーストリアを代表する偉大な作曲家であり、孤高の生涯を送ったことでも知られている。クラッシック音楽ファン、中でも交響曲ファンにはベートーヴェン、ブラームスと並び、頭文字のBをとって『交響曲の3大B』と呼ばれ人気が高い。大きなCDショップに行くと大きな棚に数多くのアルバムが揃っている。
それにしても音楽の嗜好というものは年齢によって変わってくるものだ。以前は難解で退屈に聞こえていた曲が、今は雄大で宇宙的な広がりを持ち、奥行きがあるヨーロッパの深い森林がイメージされ、聴こえてくる。そしてなによりも心地いい響きを持っている。交響曲は生涯に11曲が書かれている。0番~9番、そしてスコアがない未完のものが1曲ある。一般的な人気は4番・ロマンティックと7・8・9番だが、その他のものも魅力があり、どれも捨てがたい。現在まで一応すべての番号を聴いてみた。演奏も巨匠カラヤン指揮+ベルリンフィルの緻密で完全主義的な盤、ヨッフム指揮+バイエルン放送フィルの模範的演奏とされる盤、ベーム指揮+ウィーンフィルの情感あふれる名演盤、旧東独のブロムシュテット指揮+ドレスデン国立歌劇場オケの燻し銀の盤などなど…。そして最近気に入っているのは我が国が誇るブルックナー演奏の巨匠、朝比奈隆が大阪フィル、新日本フィル、N響を指揮した名演盤の数々である。自ら古典主義を名乗り、スコアどおりの演奏にこだわる。そして一つの曲を何回も繰り返し指揮する姿勢はまさにマエストロ(職人)の域である。たとえばブルックナーの交響曲9番のような未完の曲を生涯に6回も演奏し録音したのは史上空前であると言われている。
先月、聴いて感動したアルバムは2000年に録音されたN響との9番の演奏盤だった。 この時、マエストロ朝比奈氏は御年なんと、92才。まさに神の域に達した歴史に残る名演である。圧倒的な激しさと巨大さを持つ第1楽章から始まり、魔性の力を持つと呼ばれる第2楽章。そして彼岸的な崇高さを感じさせる第3楽章により感動的に演奏されるこの曲は第4楽章を未完成のままにして終わる。そしてこの翌年、朝比奈隆氏も93年の生涯を閉じるのである。未完成の9番と老巨匠最晩年の演奏。なんともドラマチックな組み合わせである。
猛暑の中、変わらずに絵画や版画を制作する日々。しばらくはブルックナー狂いが続きそうな予感がしている。画像はトップが朝比奈+N響のブルックナー・交響曲第9番のCDジャケ。下が左から各種ブルックナーのCD盤と最近読み始めた伝記本。