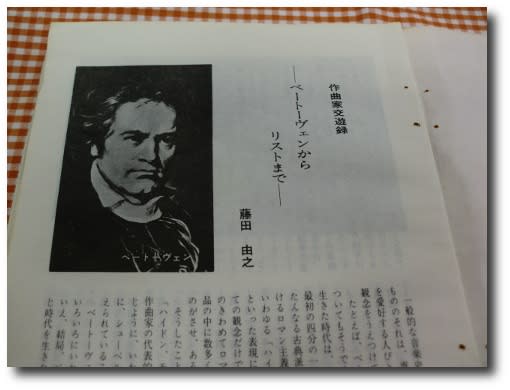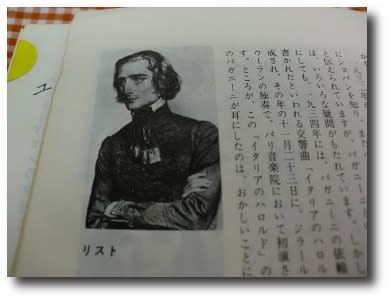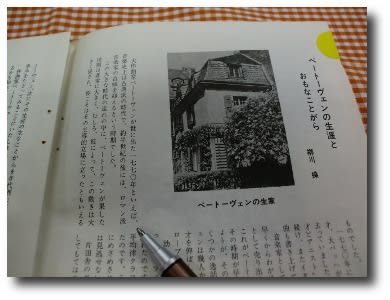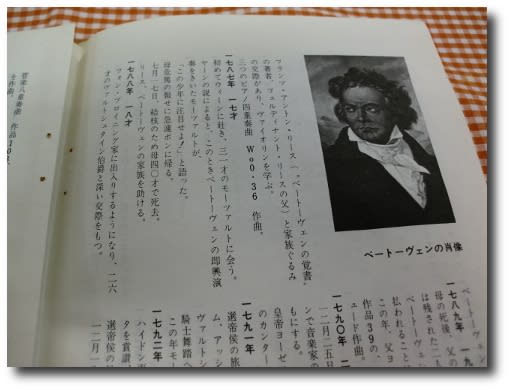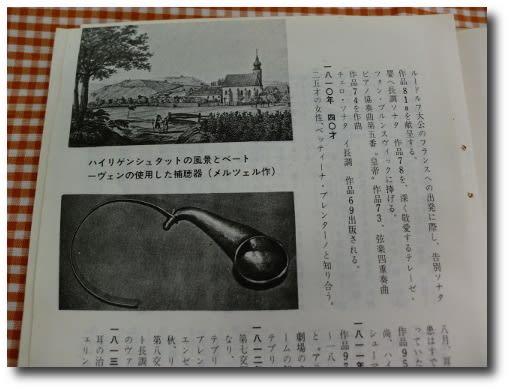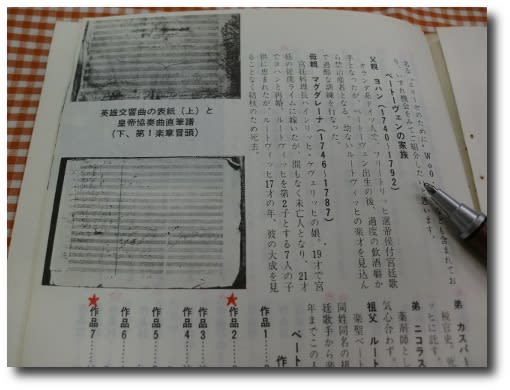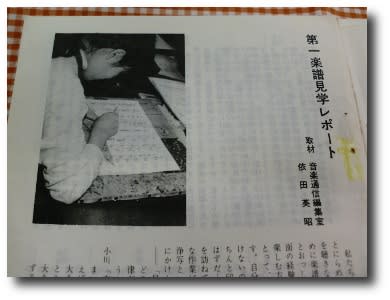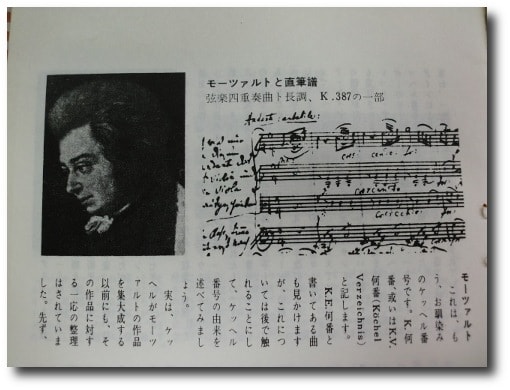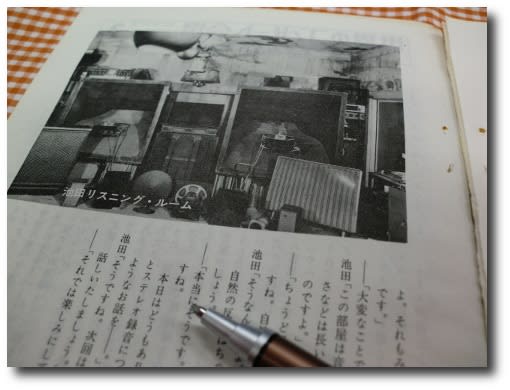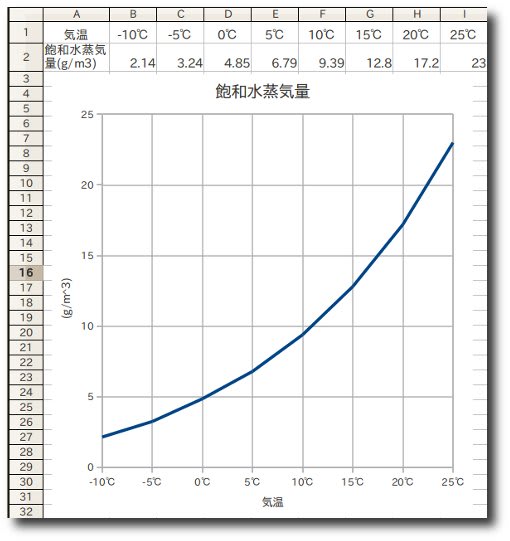確定申告を終えてほっとしたところで、タイミングよく山響第235回定期演奏会がありました。日曜日、午後のお天気にも誘われて山形テルサホールに向かいました。

今回のプログラムは、
ラヴェル「マ・メール・ロワ」
サン=サーンス「ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調Op.61」
茂木宏文「Violin Concerto -波の記憶- 」山響作曲賞21受賞作品(助成:育芸会)
ブリテン 歌劇「ピーター・グライムズ」より組曲「4つの海の間奏曲」Op.33a
というものです。

開演前の音楽監督・飯森範親さんのプレトークで、「山響作曲賞21」受賞作品以外の三曲についての解説を聞いたあと、あらためてステージ上を眺めると、今回の楽器編成の多様さ・大きさがわかります。ぎっしりという感じです。例えば最初の曲目のラヴェルでは、
フルート(2:うち1はピッコロ持ち替え)、オーボエ(2:うち1はイングリッシュホルン持ち替え)、クラリネット(2)、ファゴット(2:うち1はコントラファゴット持ち替え)、ホルン(2)、ティンパニ、パーカッション(シンバル、トライアングル、バスドラム、シロフォン、あと不明なものあり)、ハープ、チェレスタ、弦5部(10-8-6-6-4)
という具合です。楽器の配置は、向かって左から、第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、右奥にコントラバスというものです。正面奥には木管楽器が、その奥にはホルン、向かって左奥にチェレスタとハープ、さらに奥にパーカッションとティンパニが陣取ります。
これらの楽器をフルに鳴らすことは、ラヴェルはあまりやりません。むしろ、いろいろな楽器を組み合わせて、音色の変化を楽しむようなやり方です。解説によれば、「マ・メール・ロワ」とはフランス語で「がちょうのお母さん」、つまり童話の「マザーグース」のことだそうですが、ほんとにそんな感じ。近代のフランス音楽の特徴でもあるのかも。それでも第5曲:「妖精の園」では、オーケストラがフルに盛り上がります。にもかかわらず山響の響きは透明感を保ち、ラヴェルの音楽を満喫することができました。
続いて二曲目は、サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番です。ステージ上では、ハープやチェレスタのほか、ティンパニを除くパーカッションも退きますが、代わってトランペット(2)にトロンボーン(3)が加わります。楽器編成上は、見慣れた二管編成です。ここに登場するのが、本日のソリスト、松本蘭さん。スラリとした長身に真っ赤なドレスがお似合いで、情熱的な曲目に合わせた衣装でしょうか。
第1楽章:アレグロ・ノン・トロッポ。情熱的でダイナミックな出だしです。表情豊かで起伏のある音楽が、見事に展開されて行きます。第2楽章:アンダンティーノ・クワジ・アレグレット。穏やかな舟唄ですが、情熱を秘めています。佐藤麻咲さんのオーボエがとてもいい味を出していますし、川上一道さんのクラリネットと絡む松本さんのフラジオレット(でいいのかな?)が気持ちいい。あ~、これはヴァイオリンの「裏声」だな~(^o^;)と思いながら聴いていました。そして第3楽章:モルト・モデラート・エ・マエストーソ~アレグロ・ノン・トロッポ。今まで、この曲が情熱的でロマンティックな音楽であることは承知していました。けれども、ヘンな言い方ですが、今回の演奏会で、この曲が「大きな音楽である」ことを初めて認識しました。ソロではサラサーテに献呈されたということも納得のヴィルトゥオジティ満載、山響も低弦が頑張り重い力強い音を表現します。さらに、弦楽アンサンブルの透明感は見事ですし、金管パートが張り切って、ノリノリで思わず興奮しました。
いや~、良かった!
ここで15分の休憩です。(当記事も、例によって夜まで休憩です。)
(そして、ここから夜に追加した内容です。)
後半の最初は、山響作曲賞21を受賞した、茂木宏文さんの作品「ヴァイオリン協奏曲 ー波の記憶ー 」です。楽器編成は、弦5部にフルート(2,ピッコロ持ち替え2)、オーボエ(2)、クラリネット(2)、ファゴット(2)、ホルン(4)、トランペット(2)、トロンボーン(3)、チューバ、そしてバスドラム、シロフォン、木の板(?)などかなり多数のパーカッションが加わります。
ヴァイオリン独奏の松本蘭さんは、こんどは青いドレスで登場です。おそらくは、「波の記憶」というイメージで、水=青という連想なのでしょう。
二枚の木の板をたたきつけるピシッという音から音楽は始まります。多くのパーカッションが次々に登場するなど、けっこう鳴り物の印象が強いのですが、でも基調は現代的だが刺激的ではない弦楽の音。何か大きな力や不安などを感じながら、ソリストの松本さんも、ヘンな言い方ですが、中国の二胡のように音と音とを切らずにつなげて奏するように注意しているのでしょうか。彼女の演奏スタイルに、よく合っている音楽と感じました。うーむ、これはもう一度聴きたいぞ。
そして最後は、B.B.ことベンジャミン・ブリテン。ブリジッド・バルドーでもビーチボーイズでもありません(^o^)/
歌劇「ピーター・グライムズ」は、たしか救いのない悲劇を描いた作品だったと記憶していますが、この「4つの海の間奏曲」は、このオペラ中の間奏曲を選び、組曲としたものだそうです。3.11を前に、偶然にも後半のプログラムは海に関わるテーマを持つ作品が並びました。
第1曲:「夜明け」。FlとVnから。木管の音が、まろやかで深い響きです。いい音です。第2曲:「日曜の朝」。Hrnをバックに木管、次いでVn。TimpやFlが跳ね回ります。金管が加わり、オーケストラ全体が響きます。Flは小鳥の囀り、チューブラーベルは教会の鐘の音? 第3曲:「月光」。始まりの響きは、Hrn,Fg,ContraFg,Vla,Vc,Cbによるものでしたか。こういうのは、実演を聴く醍醐味です。HrpとFlが加わり、繰り返しの中で徐々にエネルギーが高まっていきます。私たちにとって月はお月見の対象ですが、英国あたりでは月光で狼男が変身するように、狂気をもたらすものとして見るらしい。第4曲:「嵐」。Timp.の強打で始まります。リズムの強い、迫力の音楽ですが、Tpはミュートを付けたり外したり、けっこう細かく音色を変えています。このあたりも、実演に接することで初めてわかることでしょう。あ~良かった!ブリテンの渋い音楽を、充分に満喫できました。

演奏会の後のファン交流会で、松本蘭さんが語った山響の印象:「楽団員の方たちが、それぞれ意見を出し合っている様子が、とてもアットホームな雰囲気で、素晴らしいオーケストラです。」うーむ、ミス日本とかミス着物とか外見の印象で語られることが多いであろうソリストが、初めてのオーケストラに感じた温かさというのは、たぶん協奏曲や初演といった不安ドキドキの中にいるときに、とくに強く感じるものだろうと思います。

作曲者の茂木宏文さんは、インタビューにも意外に落ち着いていました。若い作曲家にとって、自分の曲をプロのオーケストラに演奏してもらえる機会というのは、コンクールくらいしかないのが現実であり、作曲のモチベーションを維持するためにも、コンクールに応募した、と語ります。師匠の池辺晋一郎さんのように、劇伴や映画音楽などと自分の作曲を両立させていってね、という飯森さんのアドバイスに、にっこりと頷く茂木さんでした。

音楽監督の飯森さんは、山響の「アマデウスへの旅」が八年かかってようやく完結することを取り上げ、さらに支持を訴えました。ほんとに、あっという間の七年でした。私も、何回か抜けてしまいましたけど、まず九割がた聴いているはず。残る三回のモーツァルト定期は、なんとしても聴きに行きたいものです。

インタビュー終了後、当方は本日のソリスト松本蘭さんのファーストアルバム「蘭ing」を購入、ご本人にサインをしてもらいました。また、プログラムには茂木宏文さんにサインしてもらい、大喜び。ほんとにミーハーですね~(^o^)/
でも、いいのです。我が家のアホ猫にバカにされても(*1)、こういう演奏会通いはやめられません(^o^)/
(*1):当ブログの「アホ猫」カテゴリー参照(^o^)/