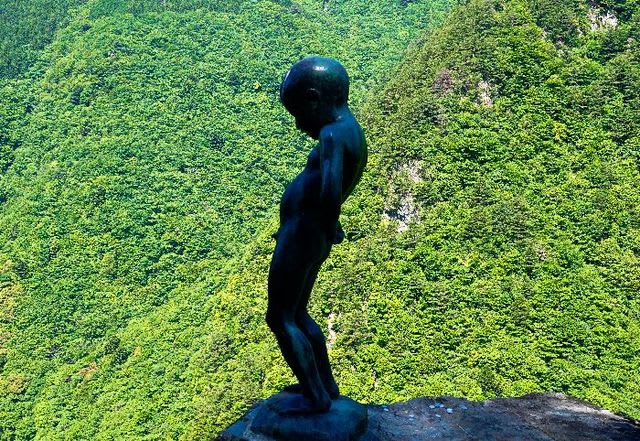190526洛西ニュータウン他
西京区の西の盆地に広がるニュータウンには、自宅からも近いので、しばしば行く方だ。
私が京都に居を移した初め頃は、まだまだ開発されていない場所だった。
東海道新幹線建設のための土砂を採集するために小高い丘などを崩したりしたと
いうが、すでに記憶は曖昧模糊としている。
ともあれニュータウン建設のために更地にしていた土地で、日曜日には
会社の人たちとしばしば草野球をしていた。
以後、タウンが建設されたのだが、今ではすでにオールドタウンともいえる。
5月26日、タウン内の街路樹の並木を中心に見て回る。
サワグルミがちょうど花を付けてはいるが、人目を引くような花ではないので、
人気はないのかもしれない。
トチノキは詳しくはセイヨウトチノキだとは思うが、すでに花は過ぎていた。
実ができても食品に加工する人は絶無なのだろう。
ユリノキは盛りを過ぎてはいたが、まだまだたくさんの花が残っている。
高木になり高い位置に花をつける傾向の植物なのだが、まれに手を伸ばせば
花に届く低い位置に咲いているのもある。
ハクサンボク・ホウ・エゴノキ・ヒトツバタゴなどはすでに花は終わった。
画像は上からブラシノキ・キショウブ・スイレン・ユリノキ。




ニュータウンから天鏡院その他をみて回る。
この季節の花や実に触れるのも一興である。時には八重ドクダミのように
珍しい花にも出会える。
画像は上からナツグミの実・ジューンベリー・八重ドクダミ・ウメモドキ。
この時の画像は下にあります。