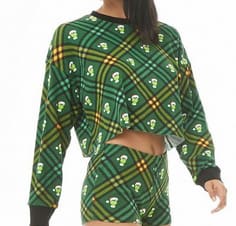ベネディクト・カンバーバッチ主演、2018年年末に日本で放送されたこのドラマをやっと見ることができました。
イギリス上流階級が舞台、ベネさんは酒とドラッグに溺れるプレイボーイ
・・・という設定を読んでこれはベネさんにふさわしい久しぶりにスリリングな作品!と期待していたので、
親切な知人が録画して貸してくれた円盤の第1話を早速見てみました
が、
あれ?確かに上流階級の若き青年らしきイギリス人が細身のスーツでNYの高級ホテルに駆け付けている、父親がその地で亡くなったため位牌を引き取りに来たと・・・
しかし青年パトリックは酒&ドラッグ漬けのジャンキーなためまともにカッコイイ姿が映らない。ムムム。
そして第2話、パトリックの幼少時代の回想シーン。フランス/プロヴァンスでの家族と友人たちとの田舎ライフに移ると、
パトリック少年は遊び友達もなし、異常なまでに威圧感のある没落貴族の父、富裕なアメリカ人の母、お手伝いさんと父の取り巻き同類のゲストたちとのミニミニ社交界で父親に怯えながら過ごしている。
長じたパトリック青年は、NYのホテルの部屋で父の遺骨が入った頑丈な箱をたたき割ろうとパニクったくらい父親を憎んでいるのだが、
幼少時代の数年間、実の父親によってレイプし続けられていたのだった。
ここで私が思い出したのは萩尾望都の「残酷な神が支配する」。あれの父親も不気味で怖かったけれど、親に性虐待を受ける程こそ恐ろしいものはない。親は生活の糧だから逃げ出せないし、外部に助けを求めようとも誰も子供の言うことは信用しないし。
母親は一見優しかったけれど、子供より自分が可愛いく他の男と家を出てしまった。
パトリックの酒とドラッグは父親の恐怖から逃避するため正気を失う手段だった。
前半は、かっこいいベネディクトさんは見られないし、上流階級の連中は男も女も特権意識ばかり強くて悪魔な性格、豪華なお屋敷もちっともステキに見えないし、何にも見たいものを見せてもらえなく「このドラマ最後まで見れないかも」という気持ちがよぎった。
何よりも上流階級の憎らしさっぷりが半端なく、「ライオット・クラブ」(オックスフォード大学の有産階級の自堕落ダメダメ兄ちゃん達のいじめっ子クラブ)の長じた姿を見たという感じ。ダウントンアビーのように民を大切にして領地に責任感を持つような人間は残っておらず、もう資産も残り少なく生活をアメリカ人の妻に頼ってるのに平民を見下している。
私は今までなんだかんだ言って王室ドラマを初めとして上流階級が出てくるクリスティものとか、イギリスちょっと昔の話が大好きだった。
しかしこのドラマを見てそういう気持ちが生まれてはじめて吹っ飛んでしまいました。

アメリカ人妻たち
しかし中後半に、パトリックの薬物アルコール依存が、虐待した父と助けてくれなかった母の呪いであるとわかってからドラマとしての面白さが倍速に!!!
ネタバレしますが、
結局何度も失敗しながら、パトリックは
呪いを解きます。ずっと言えなかった父親への言葉を、自分が虐待された年齢の自分の子供を持つようになってからという長い長い年月をかけて。
とても良かったです。
子供と親の関係って、親が親であるだけで圧倒的に強いので、反抗はとても難しいんです。子供が大人になっても親との関係はただスライドしていくだけで、子供は親と喧嘩したくないから自分の言葉は飲み込んでしまう。
私自身もそうで、自分の本当の安堵は親がいなくなるまでないのでは?と思ったことが何度もありそしてそのことで罪悪感に苛まされる。
でもパトリックの子供時代の姿が、穏やかに本当の自分の気持ちを父親に聞かせたラストシーンが、こんな方法があったのか?!と救われたような安堵感をもたらしてくれました。
立場をかえて、私自身も親なのですが、自分が子供の頃に大人を冷静に見ていた子供だったので、子供を育てるのになるべく子供を「小さな大人」として接するようにしました。
つまり子供だましは通用しないという前提で。
それでも折に触れて子供に「こう言うことを言われて嫌だった」と私の発言に傷ついたことを聞かされたこともあります。子供って大人の深く考えてない一言で傷つくんです。
子供に呪いをかけないために、親は子供を否定せず言いたいことは自分がお手本となって示すしかないんじゃないかな、あとはその子供を大切に思っていることを伝えて自己肯定感をしっかりと身につけさせれば、あとはその子が自力でやっていけるのでは・・・
とパトリックを見てつらつら考えたのでした。