
2つ以上の障害がある子どもたちが通う重度重複学級。
共産党都議団は、都立特別支援学校の在籍者数が増え、重複障害児が増えているのに重度重複学級がまったく増えていないという問題をくり返し指摘しました。
昨年の都議会予算特別委員会で、里吉ゆみ議員がこの問題を取り上げました。(全文はコチラ)
重度重複学級の部分について、少し長いですが引用します。
○里吉委員 障害の重い子の教育を支えているのが、少人数で手厚い教育を行える重度重複学級です。ところが、この重度重複学級が足りないのです。全国の重複学級の在籍率と、東京の在籍率を比べると、その差は歴然です。
平成二十八年度、全国の特別支援学校の小中学校で、全ての児童生徒のうち、どれだけ重複学級に通っているか、文部科学省の調査で見てみますと、全国は三六・五%、都立特別支援学校では一三%、肢体不自由校だけで見ますと、全国は五五%、東京では二七%です。
東京では特別支援学校に通う児童生徒が、障害の軽い子供が多いのかというと、そんなことはありません。例えば、肢体不自由学校では、障害の重さにより、教育内容が分かれていますが、その中で一番重い、先ほど紹介したO君のようなお子さんや、知事のおっしゃった、体や目のわずかな動きだけで意思や感情を表現する子供のための自立活動を主とする教育課程というのがあります。
この自立活動を主とする教育課程を受けている児童生徒の数はどれくらいなのか伺います。
○中井教育長 平成二十九年度、都立肢体不自由特別支援学校十八校に在籍し、自宅等から通学している児童生徒は、千八百二十九人でございます。そのうち自立活動を主とした教育課程により指導を受けている児童生徒は、千百五十四人でありまして、これは全体の六三・一%に当たります。
○里吉委員 全体の六三・一%、六割以上の子供が、一番重い自立活動を主とする教育課程を受けているとのことです。これはすごい数字だと思います。以前の文教委員会の質疑で、都教育委員会は、重度重複学級は自立活動を主とした指導がより適切な児童生徒を対象に学級編制すると答弁をしています。
現在、重度重複学級に在籍している児童生徒は、全体の三割に満たないけれども、重度重複学級の対象となる児童生徒は、その二倍もいるということではないでしょうか。全国と比較しても、また自立活動を主とする教育課程の子供の割合から見ても、東京の重度重複学級は少な過ぎると思いますが、見解を伺います。
○中井教育長 自立活動を行う、自立活動を主として教育課程の対象となっている児童生徒は、主に学習内容に対する理解の程度、そこを考慮して、対象にしているということでございまして、一方で、重度重複学級の対象となる児童生徒については、発達や行動、疾病などの側面から総合的に判断しているというものでございます。
このように、両者を対象とするところには違いがあるわけでございまして、二つの数字を関連づけて議論するということには、やや問題があるんではないかと、そのように考えております。全国に比べてということについては、先ほど申し上げましたとおり、介護職員等、外部の専門人材を多く入れているというようなことも影響しているかと、そのように考えます。
○里吉委員 パネルを用意していただきたいと思います。実際、私が一月に視察した特別支援学校では、小学校二年生、普通学級の子供十一人のうち四人は、重重学級の子供たちと一緒のグループで自立活動を主とする教育課程で学んでいました。子供たちの実態に応じて適切に学級編制を決めれば、当然、重重学級に入る子供なのではないかと思います。
このやりとりから見えてくるのは、重度重複学級で学ぶべき子どもたちが入れていないということです。
山下議員の質問で明らかになったのは、知的障害を併有する子どもは1167人いるのに、都は文科省に重複障害児は594人と「過小報告」しているという事実です。
山下議員は、子どもの実態と学びの質に関わるとして、この問題を取り上げましたが、本当に重要な指摘だと思います。
これに対して、文部科学大臣は「重複障害のある児童・生徒を単一障害と認定し、適切な指導や必要な支援が行われない場合があるとすれば問題」と答弁しました。
国政と都政の連携プレーで、抜本的な改善をはかれるように全力を尽くしていきます。
東京の大問題!
— 池川友一🏳️🌈 (@u1_ikegawa) 2019年5月22日
2つ以上の障害がある子どもが通う重度重複学級。知的障害を併有する子どもは1167人いるのに、都は文科省に重複障害児は594人と報告。文科省は「都に確認している」と。
都、重複障害児を過少報告/教員配置手厚い学級 減らす/参院文科委 山下議員が独自調査 https://t.co/4goNxQqPLr
にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。












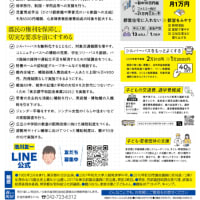
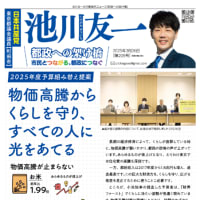



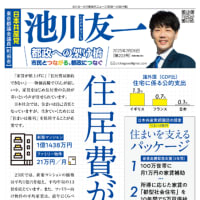


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます