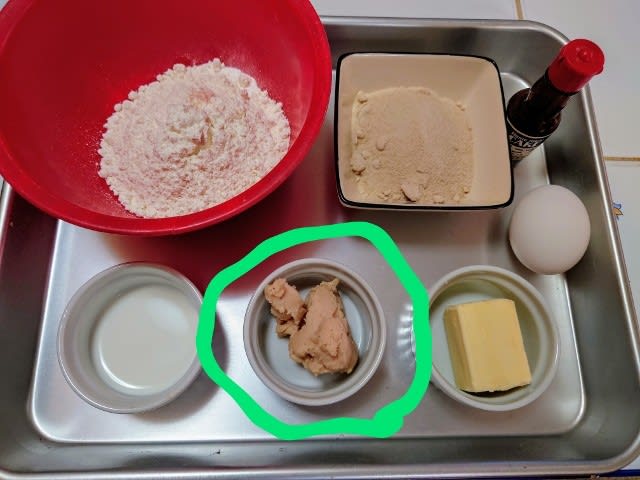1週間前に仕込んだ塩麹。
塩麹の仕込みの様子は、こちら。
使用した生麹については、こちら。
毎日毎日かきまぜ、ついに完成しました~!! ヽ(^o^)丿

【完成した塩麹)
1週間前のものと比べると、
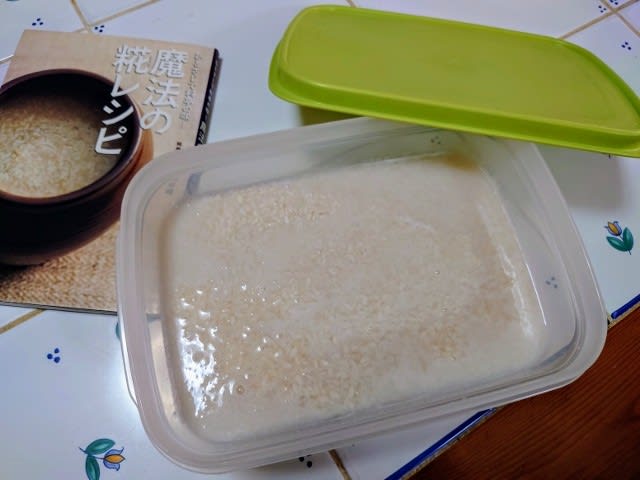
【1週間前の仕込んだばかりの塩麹】
完成したものは、麹と水分が一体化してとろみが出ているのがわかります。
生麹でうまく作れたことがないので、よかった!!
早速、出来立て塩麹でお料理を作りました。

・ドライトマトとプチベールの塩麹ご飯
ちぎったドライトマトと塩麹でご飯を炊き、炊き上がってから茹でたプチベールを加えました。
お米1合に付き、小さじ1の塩麹を入れて、普通の水加減で炊きました。
・青大豆の塩麹サラダ
青大豆、セルリー、パプリカを塩麹ドレッシングで和え、イタリアンパセリを散らしました。
ドレッシングの分量は
塩麹 大さじ2
りんご酢 大さじ1 (お酢はお好みのものを)
オリーブオイル 大さじ2
こしょう 少々
・塩麹でロールキャベツ
包んだ挽き肉も塩麹で味付けしています。
ロールキャベツは、かつおだし、塩麹、トマトで煮込んでいます。
どのお料理も塩麹を使うことで、甘みが強くなっていることが驚きでした。
保存容器いっぱいの塩麹、ワクワクしますね。
色々なお料理に使っていきます。(^-^)