https://www.zenchin.com/news/post-5045.php
居住用賃貸の家賃支払いを国が補助する「住居確保給付金」の相談・申請件数が急増し、各自治体が住民対応に追われている。新型コロナによる休業者増加を受けて、厚労省が4月20日、支給対象に減収世帯を含めるよう要件緩和したことで、制度の認知が急速に広まっているからだ。ただし、あまりの増加ぶりに、対応能力が限界に近づいてきている自治体もある。今後も雇用情勢の悪化で利用増加が考えられる中、自治体の体制強化が課題に浮かび上がってきている。
「電話つながらず」体制強化が課題
「住居確保給付金」は居住用賃貸の家賃支払いを補助する唯一の制度。元々は生活困窮者を自立支援するために国が5年前につくっ
た制度だが、4月20日、新型コロナ感染対策に伴う臨時休業で収入が減った世帯も支給対象となるよう要件緩和した。20日を境に、窓
口となる各自治体に問い合わせが殺到している。「20日以降、1日100件前後の相談があって対応に追われている」 こう答えるのは、東京都板橋区の窓口職員。相談者のうち、すでに約20人が申請を済ませた。1日あたりの相談件数が2~3件だった平時と比べると、20日以降は約50倍に跳ね上がったことになる。窓口の職員は、相談者の多くが「店舗従業員かフリーランス」と感じている。5月末の家賃支払い相談が多いという。世田谷区の保健福祉政策部生活福祉課の高橋陽子主任は「ひっきりなしに電話がかかってきていて、相談ごとに細部まで話を聞けていないが」と前置きした上で「多いと感じている相談が、申請したいけれどもどうしたらいいのか、自分は該当するのか、という内容だ」と明かす。
世田谷区での2019年の年間新規申請件数は約100件。それが20年4月だけで約900件の相談があり、そのうちほとんどが申請につなが
ると見ている。それ以上の情報は「忙しくて分析が追いつかない」という。新宿区では、4月1~27日時点の相談件数が約580件。2月の約20件、3月の約30件から3ケタに倍増した。4月の問い合わせのうち申請者は約2割に上ると予想する。
福祉部生活福祉課の片岡丈人課長は「職業・年齢はバラバラだが、フリーランス、飲食業、水商売関係者からの相談が目立つ」と語
る。 相談者が制度を知った経緯はさまざま。「家主から制度の紹介を受けた人、家賃支払いに困ってウェブ検索でたどり着いた人、SNSで知った人などだ」(片岡課長) 相談内容で多かったのが「自分は該当するのかどうか」「申請方法は」など基本的なものだ。
各自治体で対応に追われている様子も目立った。足立区の窓口では、4月27日時点の4月単月の相談件数は650件、申請件数が34件に
至った。なお前年同月の申請件数はたったの1件だった。 足立区の職員は「申請を受け付けてから精査するケースもあり、詳しい給付の時期は、通常のサイクルより少し時間がかかる可能性がある」と語った。大阪市北区では、「電話対応が追いつかない」という理由で取材自体が断られた。同市中央区では、電話が一度もつながらなかった。今後コロナで雇用情勢がさらに悪化すれば、制度の利用ニーズはさらに拡大する。自治体の体制強化も課題となるだろう。
家賃支払いを小口融資で支援
新型コロナウイルスによる賃貸住宅入居者の収入減に対する国の支援制度は「住居確保給付金」が知られるようになってきた。
「生活福祉資金貸付制度」も滞納対策に
もうひとつ、個人に無利子・保証人不要で生活資金を融資する「生活福祉資金貸付制度」(厚生労働省)もある。従来の「低所得世
帯」に限定した貸付要件を、新型コロナウイルスによる休業や失業で、生活維持が困難になった人にまで対象を広げている。 同制度は次の2種類に分かれる。主に休業者を対象とする「緊急小口資金」と、失業者が主要対象の「総合支援資金」だ。 休業者が対象の「緊急小口資金」では、上限額は10万~20万円。据置期間は1年以内、償還期限は2年以内としている。一方、失業者が対象の「総合支援資金」では、貸付上限額は2人以上世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内とする。貸付期間は原則3カ月以内。据置期間は1年以内で、償還期限は10年以内としている。申し込み先は、各市区町村の社会福祉協議会。3月25日から受け付けを開始している。家賃支払い支援につながるとして、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京都千代田区)は、「賃貸不動産経営管理士」の有資格者に対し、対応策の一環として利用を呼び掛けている。
居住用賃貸の家賃支払いを国が補助する「住居確保給付金」の相談・申請件数が急増し、各自治体が住民対応に追われている。新型コロナによる休業者増加を受けて、厚労省が4月20日、支給対象に減収世帯を含めるよう要件緩和したことで、制度の認知が急速に広まっているからだ。ただし、あまりの増加ぶりに、対応能力が限界に近づいてきている自治体もある。今後も雇用情勢の悪化で利用増加が考えられる中、自治体の体制強化が課題に浮かび上がってきている。
「電話つながらず」体制強化が課題
「住居確保給付金」は居住用賃貸の家賃支払いを補助する唯一の制度。元々は生活困窮者を自立支援するために国が5年前につくっ
た制度だが、4月20日、新型コロナ感染対策に伴う臨時休業で収入が減った世帯も支給対象となるよう要件緩和した。20日を境に、窓
口となる各自治体に問い合わせが殺到している。「20日以降、1日100件前後の相談があって対応に追われている」 こう答えるのは、東京都板橋区の窓口職員。相談者のうち、すでに約20人が申請を済ませた。1日あたりの相談件数が2~3件だった平時と比べると、20日以降は約50倍に跳ね上がったことになる。窓口の職員は、相談者の多くが「店舗従業員かフリーランス」と感じている。5月末の家賃支払い相談が多いという。世田谷区の保健福祉政策部生活福祉課の高橋陽子主任は「ひっきりなしに電話がかかってきていて、相談ごとに細部まで話を聞けていないが」と前置きした上で「多いと感じている相談が、申請したいけれどもどうしたらいいのか、自分は該当するのか、という内容だ」と明かす。
世田谷区での2019年の年間新規申請件数は約100件。それが20年4月だけで約900件の相談があり、そのうちほとんどが申請につなが
ると見ている。それ以上の情報は「忙しくて分析が追いつかない」という。新宿区では、4月1~27日時点の相談件数が約580件。2月の約20件、3月の約30件から3ケタに倍増した。4月の問い合わせのうち申請者は約2割に上ると予想する。
福祉部生活福祉課の片岡丈人課長は「職業・年齢はバラバラだが、フリーランス、飲食業、水商売関係者からの相談が目立つ」と語
る。 相談者が制度を知った経緯はさまざま。「家主から制度の紹介を受けた人、家賃支払いに困ってウェブ検索でたどり着いた人、SNSで知った人などだ」(片岡課長) 相談内容で多かったのが「自分は該当するのかどうか」「申請方法は」など基本的なものだ。
各自治体で対応に追われている様子も目立った。足立区の窓口では、4月27日時点の4月単月の相談件数は650件、申請件数が34件に
至った。なお前年同月の申請件数はたったの1件だった。 足立区の職員は「申請を受け付けてから精査するケースもあり、詳しい給付の時期は、通常のサイクルより少し時間がかかる可能性がある」と語った。大阪市北区では、「電話対応が追いつかない」という理由で取材自体が断られた。同市中央区では、電話が一度もつながらなかった。今後コロナで雇用情勢がさらに悪化すれば、制度の利用ニーズはさらに拡大する。自治体の体制強化も課題となるだろう。
家賃支払いを小口融資で支援
新型コロナウイルスによる賃貸住宅入居者の収入減に対する国の支援制度は「住居確保給付金」が知られるようになってきた。
「生活福祉資金貸付制度」も滞納対策に
もうひとつ、個人に無利子・保証人不要で生活資金を融資する「生活福祉資金貸付制度」(厚生労働省)もある。従来の「低所得世
帯」に限定した貸付要件を、新型コロナウイルスによる休業や失業で、生活維持が困難になった人にまで対象を広げている。 同制度は次の2種類に分かれる。主に休業者を対象とする「緊急小口資金」と、失業者が主要対象の「総合支援資金」だ。 休業者が対象の「緊急小口資金」では、上限額は10万~20万円。据置期間は1年以内、償還期限は2年以内としている。一方、失業者が対象の「総合支援資金」では、貸付上限額は2人以上世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内とする。貸付期間は原則3カ月以内。据置期間は1年以内で、償還期限は10年以内としている。申し込み先は、各市区町村の社会福祉協議会。3月25日から受け付けを開始している。家賃支払い支援につながるとして、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京都千代田区)は、「賃貸不動産経営管理士」の有資格者に対し、対応策の一環として利用を呼び掛けている。



















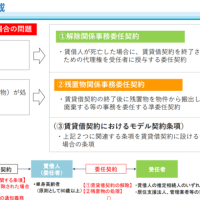






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます