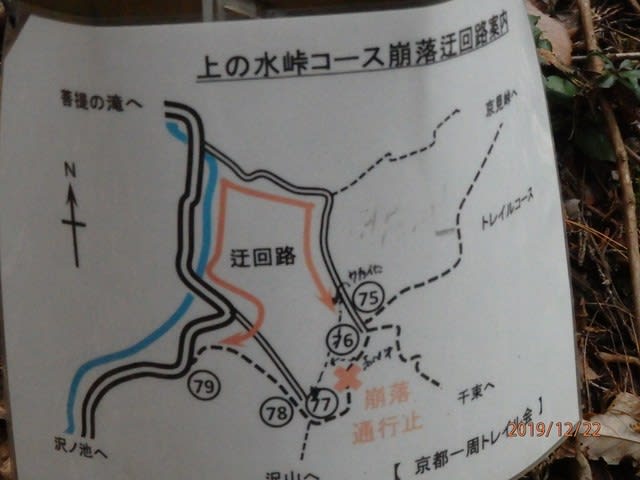2020年10月31日(土)
『山の会』
<ダイヤモンドトレールⅦ>
■参加者:安部ちゃん、梅安さん、聖子さん、東さん、ゆうさん
[コースタイム]
[JR山中渓(たに)駅] 8:46 → 9:29 [第一パノラマ展望台への分岐]→ 11:06 [雲山峰] 11:16 → 12:05 [井関峠] → 12:30 [懴法(せんぽう)ヶ岳・西峰] → 12:57 [大福山] 13:17 → 13:39 [奥辺峠] → 14:33 [札立山] → 15:41 [飯盛山] → 17:25 [岬公園駅]
<JR山中渓駅から岬公園駅へと歩く>
今日の山の会山行について、参加するとは皆に伝えていなかった。
初めて購入したスマホが上手く使えなくて、
なかでも、山の会の連絡手段となっているLINEも上手く使えなくて、
ここのところ、スマホを触るのが面倒だと感じていたからで、
集合時刻であるJR山中渓駅に、8時28分に行けば皆に会えるだろうとの判断であった。
ところが、情けないことが理由で、乗らなければならない電車に乗りそこない、
JR山中渓駅に到着したのが、集合時刻よりも15分くらい後になってしまう。
当然のことながら、僕がやって来るとは思っていない皆は、既に出立した後であった。
仕方ないよなと思い、地図を拡げ、県道64号線を歩き始める。
ハイキングコースへと入る入口を、その道を見落とさないようにと注視して200㍍ほど進むと、
首尾よく道標を見付ける。後は、道と道標が僕を導いてくれた。
前回と前々回の二度、山の会の例会山行に出席していなかった。
それは、我が足の靴擦れと腰痛などが原因だった。
それゆえ今日は、皆と一緒に歩きたいと思っていたのだが、また、独り山行になってしまったよなと思いつつ歩いていた。
スタート地点である山中渓駅を、皆より10分あまり遅れて歩き始めたので、
皆よりも歩くのが遅い僕の脚では、その10分はあまりにも大きく、
追いつく筈もないし、諦めて、我がペースでゆっくりと歩き続けた。
皆に追いつけるなんてことは、毛頭考えていなかった。
それゆえ、日没を迎えてからは、歩いたことがない見知らぬ山道を、
ヘッドランプの灯で足下を点しつつ、独りで歩かねばならないよな、
道は分かるのだろうか、道を間違わないようにしなければならないよななんて考えて歩いていた。
先月の霊仙山における二度にわたる道迷いを思い出しながら。
しかし、到着地点がバス亭ではなく鉄道の駅ゆえ、
バスの最終時刻を気にして、焦って歩き続ける必要がないことが嬉しいことであった。
電車だと22時が廻っても動いているだろうからと、
のんびりとした心根で、脚に痙攣が生じないように、我がペースでゆっくり歩みを進めた。
井関峠の手前くらいからだったと思うのだが、
高校生によるワンゲルの大会が行なわれているらしく、30名以上の若人が僕を追い抜いて行った。
リュックサックには、田辺、松陰などと学校名が書かれたゼッケンが貼ってあった。
その高校生達の一部が集う大福山で僕もお昼にした。
ハイキング道より数段階段を上ったところに大福山の頂があり、ちょっとした広場になっていて、幾つかのベンチが用意されていた。
ベンチにザックを置き、立った儘の姿勢で菓子パンを頬張るときに、後方より僕の名前を呼ぶ声があった。振り返ると其処に皆が居た。
それは信じられないことで、皆も信じられないという様子であった。
「連絡が無いから来るような気がしていた」と安部ちゃんが言った。
皆は僕の後方を歩いていたのだ。しかしそれには理由があった。
それは、暗くなるまでに岬公園駅に着くようだというリーダーである梅安さんの判断で、
俎石山(マナイタイシヤマ)を往復してきたのだという。
昭文社の案内によると、その往復には40分は掛かるようだから、皆は僕よりも30分ほど前を歩いていたことになる。
出会ってからはいつもの順番で歩き続けた。
先頭はリーダーの梅安さん、次は東さん、三人目は聖子さん、そして僕、最後は、僕の見守り役の安部ちゃんであった。
併しだ、皆と出会ったことで心配ごとが一つ持ち上がった。
それは、我がペースではなく、皆のペースで歩かねばならなかったことだった。
このペースだと“こむら返り”が生じるに違いないと思い、小休止を取るときに、用心のために芍薬甘草湯を一袋服用した。
飯盛山だったと思うのだが、小休止するときに、一頭のアカタテハが眼前に舞い降りた。
羽化してまだ間が無いのかも知れないと思うほどに、鮮やかな色彩の翅を有していた。
しかし、間も無くやって来たもう一頭のアカタテハと一緒に舞い上がり、我が視界から姿を消してしまう。
華やかな蝶の色彩を愉しんだのは瞬時のことであった。
秋の花も我が眼を愉しませてくれた。
春や夏の花と違って、落ち着いた色彩の花達なのだが、我が眼に留まった花の名前を順番に挙げると、
ヤクシソウ、センブリ、アキノキリンソウ、ヒヨドリバナ、ヤマシロギク、ヤマハッカ、ツリガネニンジン、シラヤマギクだ。
併しだ、岬公園駅までもう30分ばかりという所でカメラに収めた、二種類の黄花の名前が残念ながら分からない。
また、花ではないのだが、久し振りにサンショウに出合った。
それは、もう其処が井関峠という処であった。道の真ん中に、50cmくらいの高さまで伸び上がっていたのだ。
触るとサンショウ独特の芳しい香があった。


(写真上・名前がわからない黄花)

『山の会』
<ダイヤモンドトレールⅦ>
■参加者:安部ちゃん、梅安さん、聖子さん、東さん、ゆうさん
[コースタイム]
[JR山中渓(たに)駅] 8:46 → 9:29 [第一パノラマ展望台への分岐]→ 11:06 [雲山峰] 11:16 → 12:05 [井関峠] → 12:30 [懴法(せんぽう)ヶ岳・西峰] → 12:57 [大福山] 13:17 → 13:39 [奥辺峠] → 14:33 [札立山] → 15:41 [飯盛山] → 17:25 [岬公園駅]
<JR山中渓駅から岬公園駅へと歩く>
今日の山の会山行について、参加するとは皆に伝えていなかった。
初めて購入したスマホが上手く使えなくて、
なかでも、山の会の連絡手段となっているLINEも上手く使えなくて、
ここのところ、スマホを触るのが面倒だと感じていたからで、
集合時刻であるJR山中渓駅に、8時28分に行けば皆に会えるだろうとの判断であった。
ところが、情けないことが理由で、乗らなければならない電車に乗りそこない、
JR山中渓駅に到着したのが、集合時刻よりも15分くらい後になってしまう。
当然のことながら、僕がやって来るとは思っていない皆は、既に出立した後であった。
仕方ないよなと思い、地図を拡げ、県道64号線を歩き始める。
ハイキングコースへと入る入口を、その道を見落とさないようにと注視して200㍍ほど進むと、
首尾よく道標を見付ける。後は、道と道標が僕を導いてくれた。
前回と前々回の二度、山の会の例会山行に出席していなかった。
それは、我が足の靴擦れと腰痛などが原因だった。
それゆえ今日は、皆と一緒に歩きたいと思っていたのだが、また、独り山行になってしまったよなと思いつつ歩いていた。
スタート地点である山中渓駅を、皆より10分あまり遅れて歩き始めたので、
皆よりも歩くのが遅い僕の脚では、その10分はあまりにも大きく、
追いつく筈もないし、諦めて、我がペースでゆっくりと歩き続けた。
皆に追いつけるなんてことは、毛頭考えていなかった。
それゆえ、日没を迎えてからは、歩いたことがない見知らぬ山道を、
ヘッドランプの灯で足下を点しつつ、独りで歩かねばならないよな、
道は分かるのだろうか、道を間違わないようにしなければならないよななんて考えて歩いていた。
先月の霊仙山における二度にわたる道迷いを思い出しながら。
しかし、到着地点がバス亭ではなく鉄道の駅ゆえ、
バスの最終時刻を気にして、焦って歩き続ける必要がないことが嬉しいことであった。
電車だと22時が廻っても動いているだろうからと、
のんびりとした心根で、脚に痙攣が生じないように、我がペースでゆっくり歩みを進めた。
井関峠の手前くらいからだったと思うのだが、
高校生によるワンゲルの大会が行なわれているらしく、30名以上の若人が僕を追い抜いて行った。
リュックサックには、田辺、松陰などと学校名が書かれたゼッケンが貼ってあった。
その高校生達の一部が集う大福山で僕もお昼にした。
ハイキング道より数段階段を上ったところに大福山の頂があり、ちょっとした広場になっていて、幾つかのベンチが用意されていた。
ベンチにザックを置き、立った儘の姿勢で菓子パンを頬張るときに、後方より僕の名前を呼ぶ声があった。振り返ると其処に皆が居た。
それは信じられないことで、皆も信じられないという様子であった。
「連絡が無いから来るような気がしていた」と安部ちゃんが言った。
皆は僕の後方を歩いていたのだ。しかしそれには理由があった。
それは、暗くなるまでに岬公園駅に着くようだというリーダーである梅安さんの判断で、
俎石山(マナイタイシヤマ)を往復してきたのだという。
昭文社の案内によると、その往復には40分は掛かるようだから、皆は僕よりも30分ほど前を歩いていたことになる。
出会ってからはいつもの順番で歩き続けた。
先頭はリーダーの梅安さん、次は東さん、三人目は聖子さん、そして僕、最後は、僕の見守り役の安部ちゃんであった。
併しだ、皆と出会ったことで心配ごとが一つ持ち上がった。
それは、我がペースではなく、皆のペースで歩かねばならなかったことだった。
このペースだと“こむら返り”が生じるに違いないと思い、小休止を取るときに、用心のために芍薬甘草湯を一袋服用した。
飯盛山だったと思うのだが、小休止するときに、一頭のアカタテハが眼前に舞い降りた。
羽化してまだ間が無いのかも知れないと思うほどに、鮮やかな色彩の翅を有していた。
しかし、間も無くやって来たもう一頭のアカタテハと一緒に舞い上がり、我が視界から姿を消してしまう。
華やかな蝶の色彩を愉しんだのは瞬時のことであった。
秋の花も我が眼を愉しませてくれた。
春や夏の花と違って、落ち着いた色彩の花達なのだが、我が眼に留まった花の名前を順番に挙げると、
ヤクシソウ、センブリ、アキノキリンソウ、ヒヨドリバナ、ヤマシロギク、ヤマハッカ、ツリガネニンジン、シラヤマギクだ。
併しだ、岬公園駅までもう30分ばかりという所でカメラに収めた、二種類の黄花の名前が残念ながら分からない。
また、花ではないのだが、久し振りにサンショウに出合った。
それは、もう其処が井関峠という処であった。道の真ん中に、50cmくらいの高さまで伸び上がっていたのだ。
触るとサンショウ独特の芳しい香があった。


(写真上・名前がわからない黄花)