今までにない針路を取る台風12号。
いつもと真逆の東から西へ日本列島を縦断しようとしている。
28日には東海に上陸かとなって、夏休みに入ったばかりでいろいろな行事が目白押しの週末は大混乱に。
瑞穂陸上競技場で実施予定のグランパスの試合は早々と中止。
隅田川の花火は延期。
各地の祭りも中止とか延期に。我が地元の雁道の夏祭りも28日は中止に。
28日は16時30分から瑞穗公園テニスコートの予約が入っているのですが、これは無理と早々と戦闘態勢を解除したのですが…
28日朝起きると曇り 。時折雨が降り出すのですが、弱い雨。
。時折雨が降り出すのですが、弱い雨。
10時過ぎる頃には、雨もやみ晴れ間 も出てきた。
も出てきた。
一向に降り出す気配もなくて台風はどこへ行った?
雲の動きの予報を見てみると名古屋は18時くらいまでは雨雲がかからず雨は降らない?
11時ごろにはヤッターマンからやるのかと問い合わせのメールが入ったのですが、台風は夜には接近してくるのだし、風も強くなって雨も降りだすのも必定。こんな天気なのでドタキャンしても誰も怒らないだろうし、そもそも参加者が誰も来ないのでは。まあ、中止でしょうと返事しておきました。
結局家でダラダラとテレビを見て過ごしたのですが、雨は雨雲の予報通り17時過ぎまでは一向に降らない。この天気ならばメンバーさえ集まればやってやれないこともなかったかも。多分コートではやる人はやっていたのでしょう。
でも交通機関もJRとかは早々と21時には運休とかでテニスをやってもいつものようにしげ寿司でダラダラ飲んでいては帰れなくなっていたので、これでいいのだ。
我が家では台風接近に備え暗くなる前にベランダの鉢植えとかゴミ箱などを片付けました。

これで残念ながら7月のテニスは桑名遠征の1回だけしかできませんでしたし、あの時も危険な暑さで下手したら倒れたかもしれないということで1時間しかやらなかったし、ほぼ休養の7月になってしまいました。
まあ、凶器のような暑さなので、年寄りは体と相談しつつボチボチやるしかないですね。
いつもと真逆の東から西へ日本列島を縦断しようとしている。
28日には東海に上陸かとなって、夏休みに入ったばかりでいろいろな行事が目白押しの週末は大混乱に。
瑞穂陸上競技場で実施予定のグランパスの試合は早々と中止。
隅田川の花火は延期。
各地の祭りも中止とか延期に。我が地元の雁道の夏祭りも28日は中止に。
28日は16時30分から瑞穗公園テニスコートの予約が入っているのですが、これは無理と早々と戦闘態勢を解除したのですが…
28日朝起きると曇り
 。時折雨が降り出すのですが、弱い雨。
。時折雨が降り出すのですが、弱い雨。10時過ぎる頃には、雨もやみ晴れ間
 も出てきた。
も出てきた。一向に降り出す気配もなくて台風はどこへ行った?
雲の動きの予報を見てみると名古屋は18時くらいまでは雨雲がかからず雨は降らない?
11時ごろにはヤッターマンからやるのかと問い合わせのメールが入ったのですが、台風は夜には接近してくるのだし、風も強くなって雨も降りだすのも必定。こんな天気なのでドタキャンしても誰も怒らないだろうし、そもそも参加者が誰も来ないのでは。まあ、中止でしょうと返事しておきました。
結局家でダラダラとテレビを見て過ごしたのですが、雨は雨雲の予報通り17時過ぎまでは一向に降らない。この天気ならばメンバーさえ集まればやってやれないこともなかったかも。多分コートではやる人はやっていたのでしょう。
でも交通機関もJRとかは早々と21時には運休とかでテニスをやってもいつものようにしげ寿司でダラダラ飲んでいては帰れなくなっていたので、これでいいのだ。
我が家では台風接近に備え暗くなる前にベランダの鉢植えとかゴミ箱などを片付けました。

これで残念ながら7月のテニスは桑名遠征の1回だけしかできませんでしたし、あの時も危険な暑さで下手したら倒れたかもしれないということで1時間しかやらなかったし、ほぼ休養の7月になってしまいました。
まあ、凶器のような暑さなので、年寄りは体と相談しつつボチボチやるしかないですね。










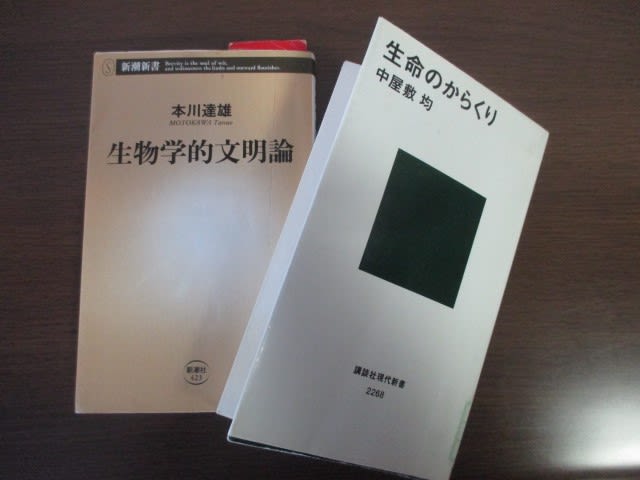


 で乾杯。
で乾杯。



 そうです。仕方ないので11時までやって早々に引き上げたとか。4人集まらなかったので、コート代は基金からわくちゃんに商品券で送っておきます。
そうです。仕方ないので11時までやって早々に引き上げたとか。4人集まらなかったので、コート代は基金からわくちゃんに商品券で送っておきます。 びっしょり。やっとの思いで名古屋駅の関西線のホームにたどり着くと既に列車はホームに入っている。乗り込んで探すも誰もいない。次の車両へ移動するとヨイショを発見。ヨイショも指定された列車に乗り込んでも誰もいなかったので不安だったみたい。そのまま二人はいないまま列車が発車
びっしょり。やっとの思いで名古屋駅の関西線のホームにたどり着くと既に列車はホームに入っている。乗り込んで探すも誰もいない。次の車両へ移動するとヨイショを発見。ヨイショも指定された列車に乗り込んでも誰もいなかったので不安だったみたい。そのまま二人はいないまま列車が発車 してしまったので、はげ親父にメールすると桑名で待っているとか。どうやら1本前の列車で行ったみたいです。
してしまったので、はげ親父にメールすると桑名で待っているとか。どうやら1本前の列車で行ったみたいです。

 やりましょうか。
やりましょうか。

 して試合をします。
して試合をします。


 のですが、集まりが悪ければだれかからメールが来るだろうと思ったのですが、それもない。
のですが、集まりが悪ければだれかからメールが来るだろうと思ったのですが、それもない。 に行く予定で宿を手配して、切符も予約しておいたのですが、西日本各地は連日の梅雨末期の豪雨
に行く予定で宿を手配して、切符も予約しておいたのですが、西日本各地は連日の梅雨末期の豪雨 。
。 にかけないといけない。ところが何回かけても話し中でなかなか繋がらない。朝から何回も試して昼過ぎにやっと繋がった。でもそこでも順番に対応しますのでしばらくお待ちくださいということで30分近く待たされる(この電話は有料なので待っている時間も電話代がかかっています)。ホームページから見るとやたらと運休区間があって危険地域には旅行は取りやめてください、その場合は全額払い戻しますとなっていたので、問い合わせの電話が殺到しているんでしょう。
にかけないといけない。ところが何回かけても話し中でなかなか繋がらない。朝から何回も試して昼過ぎにやっと繋がった。でもそこでも順番に対応しますのでしばらくお待ちくださいということで30分近く待たされる(この電話は有料なので待っている時間も電話代がかかっています)。ホームページから見るとやたらと運休区間があって危険地域には旅行は取りやめてください、その場合は全額払い戻しますとなっていたので、問い合わせの電話が殺到しているんでしょう。 は京都までは動いているし、西日本の「特急きのさき」が運休でもJR東海には関係ない。半分キャンセル料を覚悟しながら対応したお姉さんに、京都から乗る予定の特急が運休で行く意味ないので、キャンセル料は西日本が持つべきではと一応主張したのですが、調べてみますとのこと。いろいろ問い合わせてもらい待たされたのですが、キャンセル料なしでキャンセルできました。
は京都までは動いているし、西日本の「特急きのさき」が運休でもJR東海には関係ない。半分キャンセル料を覚悟しながら対応したお姉さんに、京都から乗る予定の特急が運休で行く意味ないので、キャンセル料は西日本が持つべきではと一応主張したのですが、調べてみますとのこと。いろいろ問い合わせてもらい待たされたのですが、キャンセル料なしでキャンセルできました。 で乾杯。
で乾杯。













