終わって、どうするかと聞くとはげ親父はこのところ孫の相手で欠席。まあ、今日はまっすぐ帰ろうかと思っていたのですが、コートの出口にタケちゃんマンと1059さんが待っていて行きましょうとのこと。それならば嫌いではないので行くか。
瑞穂は近くに飲食店が少なく、みんな敬老パスを持っていることもあって八事まで地下鉄に行くことに。
途中玉よし寿司の前を通ったのですが、以前確か工事中でこのコロナ禍で閉店したかと思ったのですが、準備中になっていたので営業は継続しているみたいです。

でもここは17時にならないと開店しないので店の前で時間をつぶすよりは八事に行くことに。
八事には17時少し前に着いたのですが、この日は以前行った「串揚げ酒場なごみ家」へ。

ここも開店は17時。あと2~3分の待ちでまだ準備中だったんですが、開店準備をしていたお姉さんと目があったら扉を開けてくれ、席に案内してくれました。
ところが隣の席には開店前なのにすでに宴会している人たちが。早くに予約していた人たちなのか?
とりあえず乾杯なのですが、私はハイボール、1059さんは生中、タケちゃんマンは日本酒で「奈良萬」とバラバラ。

ちなみに時間割引なのか税別でハイボールは200円、生ビールは250円です。
お通しはキャベツ。

お替りは自由と言うことで後でお替りしました。
高齢の男3人集まって話すことは最早色気もなく、かみさんの悪口と言うか家庭の愚痴話ばかり。それで家庭の平和と心の平安が保てるのなら貴重な機会なのです。
串揚げ酒場と言うので串揚げの盛り合わせを2人前。1人前5種5本です。
どうせ串が揚がるのには時間がかかるだろうと枝豆と冷奴も。
ところが枝豆はすぐに出てきたのですが、冷奴はなかなか出てこない。
串揚げの方が速く出てきました。

海老と豚ひれと豚バラと玉ねぎとウズラだったかな?どうも串揚げは揚がった後は形状からは推測できないものが多くて困ります。ウズラと玉ねぎは分かりましたけどね。
ハイボールを飲んでしまったので、今度は私もお酒にして「月不見の池」にします。この店日本酒は結構そろっています。

お酒は冷で一升瓶から直接銚子に注いでくれます。正味1合なんでしょうけど大きめのおちょこ3杯でちょうどなくなります。
その頃冷奴がやっと出てきました。

これを出すのになんでそんなに時間がかかるのか?
串揚げの追加は牛串にアスパラになす、チーズベーコンとカマンベールとそれぞれ各自好みを注文。

一応出てきた時に店員さんがこれは何と教えてくれます。
次のお酒は「八海山」。ところで一緒にホッケを頼んだのですが、なかなか来ない。
しびれを切らして催促したらすぐに出てくると言うのはなんじゃろな~

昔の居酒屋で食べたホッケはもっと大きかったとは、老人の繰り言。
一通り飲み食いしたので1時間半ほどの滞在のここで終了。
お勘定は7691円。191円は基金から出して一人2500円でした。
瑞穂は近くに飲食店が少なく、みんな敬老パスを持っていることもあって八事まで地下鉄に行くことに。
途中玉よし寿司の前を通ったのですが、以前確か工事中でこのコロナ禍で閉店したかと思ったのですが、準備中になっていたので営業は継続しているみたいです。

でもここは17時にならないと開店しないので店の前で時間をつぶすよりは八事に行くことに。
八事には17時少し前に着いたのですが、この日は以前行った「串揚げ酒場なごみ家」へ。

ここも開店は17時。あと2~3分の待ちでまだ準備中だったんですが、開店準備をしていたお姉さんと目があったら扉を開けてくれ、席に案内してくれました。
ところが隣の席には開店前なのにすでに宴会している人たちが。早くに予約していた人たちなのか?
とりあえず乾杯なのですが、私はハイボール、1059さんは生中、タケちゃんマンは日本酒で「奈良萬」とバラバラ。

ちなみに時間割引なのか税別でハイボールは200円、生ビールは250円です。
お通しはキャベツ。

お替りは自由と言うことで後でお替りしました。
高齢の男3人集まって話すことは最早色気もなく、かみさんの悪口と言うか家庭の愚痴話ばかり。それで家庭の平和と心の平安が保てるのなら貴重な機会なのです。
串揚げ酒場と言うので串揚げの盛り合わせを2人前。1人前5種5本です。
どうせ串が揚がるのには時間がかかるだろうと枝豆と冷奴も。
ところが枝豆はすぐに出てきたのですが、冷奴はなかなか出てこない。
串揚げの方が速く出てきました。

海老と豚ひれと豚バラと玉ねぎとウズラだったかな?どうも串揚げは揚がった後は形状からは推測できないものが多くて困ります。ウズラと玉ねぎは分かりましたけどね。
ハイボールを飲んでしまったので、今度は私もお酒にして「月不見の池」にします。この店日本酒は結構そろっています。

お酒は冷で一升瓶から直接銚子に注いでくれます。正味1合なんでしょうけど大きめのおちょこ3杯でちょうどなくなります。
その頃冷奴がやっと出てきました。

これを出すのになんでそんなに時間がかかるのか?
串揚げの追加は牛串にアスパラになす、チーズベーコンとカマンベールとそれぞれ各自好みを注文。

一応出てきた時に店員さんがこれは何と教えてくれます。
次のお酒は「八海山」。ところで一緒にホッケを頼んだのですが、なかなか来ない。
しびれを切らして催促したらすぐに出てくると言うのはなんじゃろな~

昔の居酒屋で食べたホッケはもっと大きかったとは、老人の繰り言。
一通り飲み食いしたので1時間半ほどの滞在のここで終了。
お勘定は7691円。191円は基金から出して一人2500円でした。











 瑞穂公園テニスコートへ行くことに。
瑞穂公園テニスコートへ行くことに。

 。コートに出て行くと丁度前の人が終わってコート整備をしているところでした。
。コートに出て行くと丁度前の人が終わってコート整備をしているところでした。 。なんでもコストコが出来て以来、ゆとりーとは遅れることが多いとか。
。なんでもコストコが出来て以来、ゆとりーとは遅れることが多いとか。 に。
に。

 して試合にします。なかなかじゃんけんが決まらなくて、自分が勝ったか負けたかもよく分からないまま私は5番でしたが、かなり判断力が混乱していたみたい。
して試合にします。なかなかじゃんけんが決まらなくて、自分が勝ったか負けたかもよく分からないまま私は5番でしたが、かなり判断力が混乱していたみたい。 。
。 。
。



 風もないので徘徊にはちょうどいい。暫く歩いて行くと尚古荘を過ぎ櫓が見えてきた。この櫓は地図には書いてなくて最近復元されたものみたい。
風もないので徘徊にはちょうどいい。暫く歩いて行くと尚古荘を過ぎ櫓が見えてきた。この櫓は地図には書いてなくて最近復元されたものみたい。















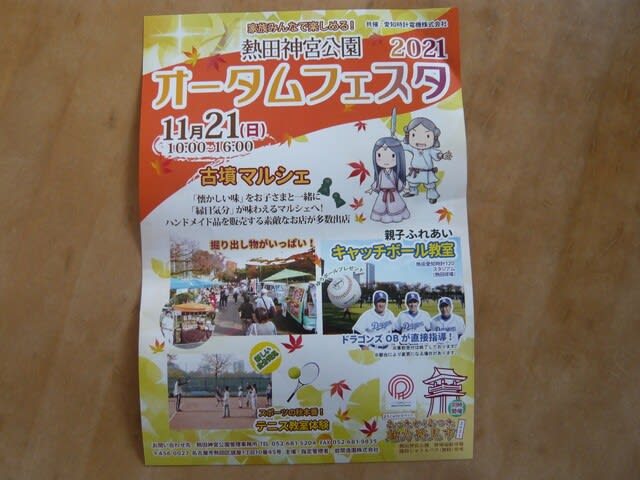


















 で八事日赤へ。
で八事日赤へ。

 をしてから乱打
をしてから乱打 に。
に。 でした。ひょっとしたら相性が悪い?
でした。ひょっとしたら相性が悪い?













