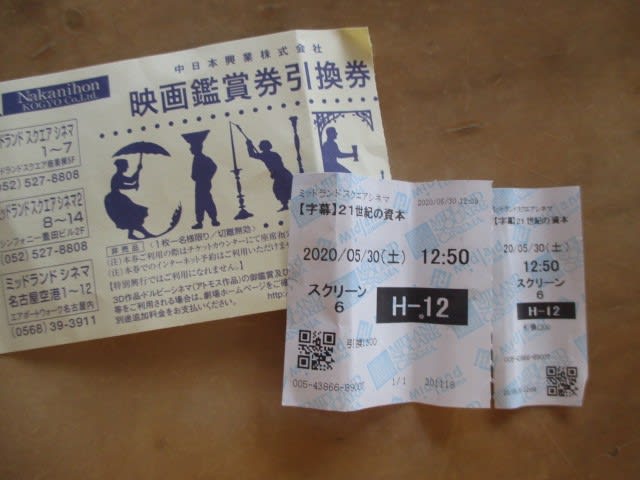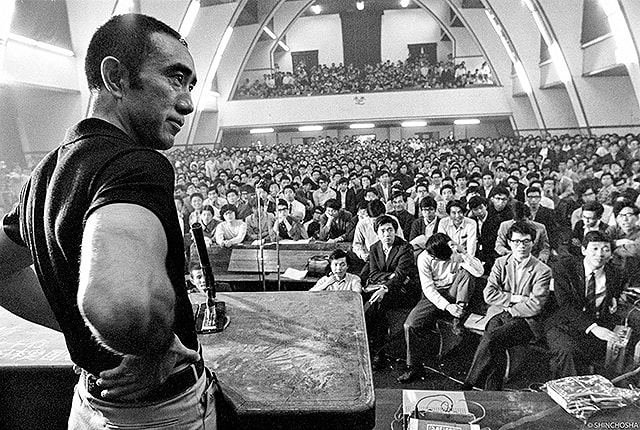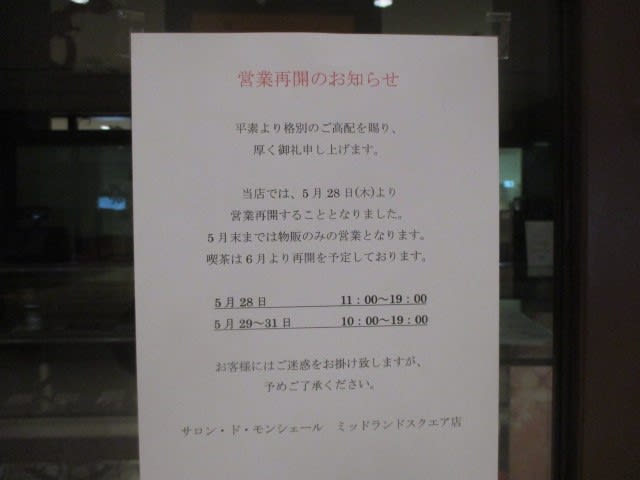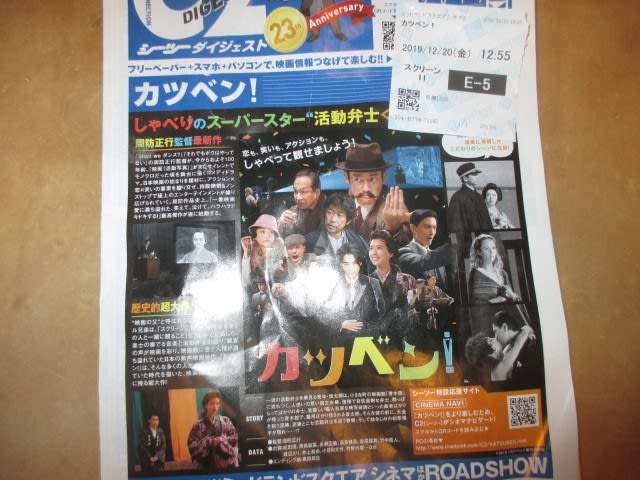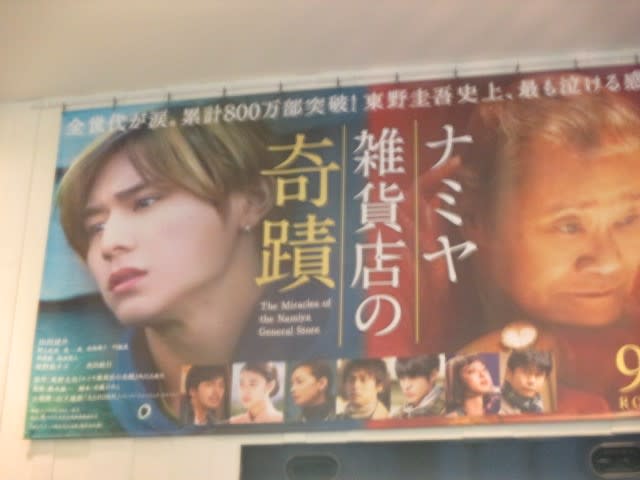NHKのBSで昼間に昔の映画をやっていますが、この日は「小さな恋のメロディ」
1971年の作品なので私が高校生のころ。映画館で見て映画音楽のbee zeesの曲とともに記憶の残っていました。
で齢68歳になって観てみたのですが、懐かしさもあるのですが途中でやめられなくてエンドロール迄しっかり観てしまいました。ノーカットでCМなしで見れるのはさすが天下のNHK、うれしいですね。
主演のマーク・レスターとトレーシー・ハイド、どちらも可愛いですけど、トレーシーはすぐに、マーク・レスターも成人してから映画界を去り、堅気?の仕事をしているような記憶です。友人役のジャック・ワイルドがいい味出しているのですけど同級生には無理がある…
パブリックスクールがもともとそうなのか知りませんが、同級生と言っても体格、人種がばらばらで、あまり年齢は関係ないのが普通なのでしょうか。
イギリスは今でもそうみたいですが、階級社会で主人公のダニエルは父親は会計士で母親は女性会活動に熱心と明らかに中産階級以上。メロディは労働者階級で他の同級生もそんな感じ。ふつうは学校を選ぶような気もしますけど、その面でちょっと場違いな感じが漂います。
それにしてもパブリックスクールに通う主人公の年齢設定は11歳。その恋愛話を高校生が見て感心していたとはどんだけ奥手だったのか。

ダニエルとトレーシー、最初はお互いにチラ見するだけだったのが、だんだん意識しあうようになり、音楽室で二人きりになると一緒に演奏して気持ちが通う。まるで日本の当時の高校生の恋愛じゃん。この映画、本国イギリスではあまりヒットしなくて日本でヒットしたというのも分かる様な気がします。
走り出すと止まらなくて二人で学校を休んで海に行く。

当然学校、家族に知れ大目玉を食らうのですが、そこから怒涛のラストに。
最後はお決まりのドタバタ劇で、同級生たちが結婚式をやってくれるのだが、そこに先生の一団が駆け付け、みんな入り乱れての乱闘に。爆弾作りが趣味の生徒の手製爆弾が爆発して先生たちが逃げ出す中、二人はトロッコに乗って去っていく。

bee zeesの曲が本当に画面とうまくシンクロしていて気分は高校生。
ところで、当たり前ですけど、教室に貼ってある世界地図はイギリスが真ん中になっている。教師はいつも紅茶を飲んでいる。いかにもイギリスのダウンタウンという街並みの風景も日本人の私にはへ~でした。60年代。70年代といかにも没落しつつある老大国の雰囲気が文化の厚みとともに出ています。
雨 が降り出し、家で蟄居している時には、懐かしの映画は最高の暇つぶし。
が降り出し、家で蟄居している時には、懐かしの映画は最高の暇つぶし。
映画って本当にいいですね。
1971年の作品なので私が高校生のころ。映画館で見て映画音楽のbee zeesの曲とともに記憶の残っていました。
で齢68歳になって観てみたのですが、懐かしさもあるのですが途中でやめられなくてエンドロール迄しっかり観てしまいました。ノーカットでCМなしで見れるのはさすが天下のNHK、うれしいですね。
主演のマーク・レスターとトレーシー・ハイド、どちらも可愛いですけど、トレーシーはすぐに、マーク・レスターも成人してから映画界を去り、堅気?の仕事をしているような記憶です。友人役のジャック・ワイルドがいい味出しているのですけど同級生には無理がある…
パブリックスクールがもともとそうなのか知りませんが、同級生と言っても体格、人種がばらばらで、あまり年齢は関係ないのが普通なのでしょうか。
イギリスは今でもそうみたいですが、階級社会で主人公のダニエルは父親は会計士で母親は女性会活動に熱心と明らかに中産階級以上。メロディは労働者階級で他の同級生もそんな感じ。ふつうは学校を選ぶような気もしますけど、その面でちょっと場違いな感じが漂います。
それにしてもパブリックスクールに通う主人公の年齢設定は11歳。その恋愛話を高校生が見て感心していたとはどんだけ奥手だったのか。

ダニエルとトレーシー、最初はお互いにチラ見するだけだったのが、だんだん意識しあうようになり、音楽室で二人きりになると一緒に演奏して気持ちが通う。まるで日本の当時の高校生の恋愛じゃん。この映画、本国イギリスではあまりヒットしなくて日本でヒットしたというのも分かる様な気がします。
走り出すと止まらなくて二人で学校を休んで海に行く。

当然学校、家族に知れ大目玉を食らうのですが、そこから怒涛のラストに。
最後はお決まりのドタバタ劇で、同級生たちが結婚式をやってくれるのだが、そこに先生の一団が駆け付け、みんな入り乱れての乱闘に。爆弾作りが趣味の生徒の手製爆弾が爆発して先生たちが逃げ出す中、二人はトロッコに乗って去っていく。

bee zeesの曲が本当に画面とうまくシンクロしていて気分は高校生。
ところで、当たり前ですけど、教室に貼ってある世界地図はイギリスが真ん中になっている。教師はいつも紅茶を飲んでいる。いかにもイギリスのダウンタウンという街並みの風景も日本人の私にはへ~でした。60年代。70年代といかにも没落しつつある老大国の雰囲気が文化の厚みとともに出ています。
雨
 が降り出し、家で蟄居している時には、懐かしの映画は最高の暇つぶし。
が降り出し、家で蟄居している時には、懐かしの映画は最高の暇つぶし。映画って本当にいいですね。












 しながら付き添いを務めてから、雁道からバス
しながら付き添いを務めてから、雁道からバス で名古屋駅に。
で名古屋駅に。