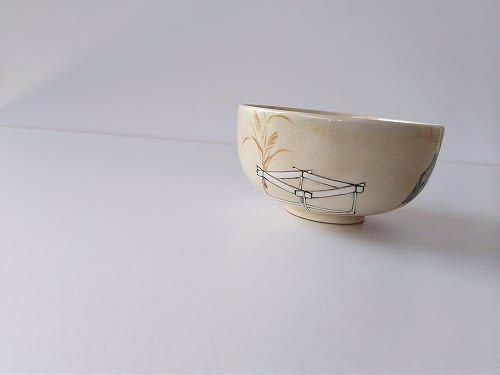松平定敬、松平容保、一橋茂栄、徳川慶勝
高須4兄弟と言われる、幕末に活躍した4人です。
高須藩は、関ヶ原以来、美濃高須(現、海津市)を中心に領国をもち、3万石の小藩ながら、尾張藩の支藩として、明治まで続きました。そして、10代義建の子、4人が、有力大名の養子となり、幕末動乱期にそれぞれ大きな役割を果たしたのです。
彼らは能をこよなく愛したと言われ、それにちなんでこのフロアには、立派な能舞台が設けられています。
隣の部屋では、地元の人たちによる抹茶とお菓子のサービスがなされています。
私が着いたときには、すでにもう満員。
やむなく、一番前の場所に。
いわゆるかぶりつき。舞台との距離は1mもありません。
おまけに、舞台の高さは50cmほど。座った目の先が舞台です。
立派なチラシが出来上がっていたのですが、事前配布は全く無し。
海津市さん、もう少し、セールスマインドをもったら。
一方、手作り感いっぱいの説明チラシも。
井筒という能
洗舟筆 『能楽 井筒』
井筒の作者は、能を大成した世阿弥です。
井筒は、砧とともに、世阿弥、渾身の作です。
井筒は、伊勢物語を典拠とした夢幻能で、幽玄の美を特色とする能にとって、最も能らしい能と言えるでしょう。
在原業平と紀有常の娘、幼なじみのふたりは成長して結ばれる。が、浮き名を流し、自分のもとから離れがちな業平への想いは募るばかり。女は、業平が纏っていた直衣を身につけて、幼い頃を回想し、二人で遊んだ井筒のもとで、静かに舞を舞い、狂おしい恋慕の情を表す。そして、井戸の水に写った自分の姿に業平の面影を見て、懐かしさに嘆息する。
やがて、夜が明け、在原寺の鐘がなる時には、女の姿は消えていた・・・・・・・すべては、寺に仮寝した旅僧の夢であった。
井筒は、伊勢物語を典拠としています。
業平の歌:
「筒井筒 井筒にかけし まろがたけ 生いにけりしな 妹見ざるまに」
昔あなたと遊んでいた幼い日に、井筒と背比べした私の背丈はずっと高くなりましたよ。あなたと会わずに過ごしているうちに。
- 女の返歌:
- 「くらべこし 振分髪も 肩すぎぬ 君ならずして 誰かあぐべき」
あなたと比べあった振り分け髪も、肩を過ぎてすっかり長くなりました。その髪を妻として結い上げるのはあなたをおいてはありえません。このようにして二人は結ばれたのです。
この部分、能・井筒の中では、
「筒井筒 井筒にかけし まろがたけ 生いにけりしな 老いにけるぞな」
となっています。
能・井筒は、年を経たその後の二人という設定です。
地謡いが「生いにけりしな」と謡いかけ、
シテは「老いにけるぞや」とこたえるのです。
井筒で背比べをして遊んでいた私たちは、成長し結ばれました。あれから月日がながれたのですね。私も年を重ねました。
女は、「老いにけらしな」の言葉から、自分の老いに気づき、過ぎた時間を回顧するのです。
子供の頃、二人で遊んだ井筒のもとへ歩み行き、男の形見の直衣を身につけたまま、子供の頃そうしたように、井戸の水に貌を写します。
そこには、業平の面影が・・・・・一瞬の静寂・・・・・
なんと懐かしいことか、女は深く嘆息し、やがて
萎んで匂いだけを残す花のように、消えていく
・・・・・・・・・・
過去と現在、夢と現実が交錯し、しみじみとした情感が漂い、夢幻の中に能は終わります。
今日の観能
当日の番組は、井筒の後場(半能)です。
が、そこは、小回りのきく地方の能。
盛りだくさんのメニューです。
1.装束レクチャー
2.作り物レクチャー
3.囃子レクチャー
4.能「井筒」
5.能楽器体験
まず、シテの観世喜正による装束レクチャー。
装束のレクチャーにとどまらず、能の起源、特徴、世阿弥、そして井筒まで、立て板に水を流すように流ちょうな説明です。
饒舌ながら、話しの勘所を押さえた説明はさすが。
後で何人かの人に聞いたのですが、皆、よくわかったと言ってました。
次は、作り物のレクチャーです。
能、井筒では、舞台上の作り物は、井筒(井戸の周りの柵)です。そして、この品は、能、井筒を象徴する重要な物です。
井筒は、台の四隅に竹を立て、その上部を杉板で井桁に組んだものが使われます。
角には、ススキが付けられます。
この会の趣旨として、単なる説明にとどまらず、体験を、ということでした。
で、会場から希望者をつのり、竹の部分にサラシ布を巻きました。
一人は70代の老人、もう一人は小学生でした。
二人とも、見事に巻き終えました。
さらに、ススキを左右どちらの角につけるか、会場の意向を聞きました。多数決で右側に決定。ススキの位置によって、シテの扇使いが変わるそうです。
これら2つのレクチャーでかなり時間をオーバーしたので、次の囃子レクチャーは、残念ながらはしょりです。
能管、小鼓、大鼓の簡単な説明に続き、井筒での舞い、序の舞の説明と部分演奏。
私としては、もう少し聞きたかったのに、残念。
実は、私、5年前に、伊勢神宮奉納能で、今回の出しものと同じ、井筒(後場、半能)の小鼓を打ちました。もう、冷や汗の連続でした。特に、序の舞は危なかった。
井筒の序の舞は、太鼓が入らない、大鼓、小鼓、笛だけの大小序の舞と言われる舞いです。曲の序の部分が特に難物です。
能の曲は、厳密な8拍子で構成されているのですが、この序の部に限り、拍子があるような、無いような、とらえどころのないリズムなのです。太鼓が入る序の場合は、太鼓がリードして、リズムをつくっていくのですが、大小序の舞いの場合は、大鼓と小鼓の阿吽の呼吸で曲をつくらねばなりません。素人には、とても手ごわい曲です。
海津の能・井筒
簡素な能です。
出演者は、シテ、観世喜正、笛、竹市学、小鼓、後藤嘉津幸。地謡は、わずかに3人。ワキは無し。
シテと囃子方3人の4人は、能楽グループ「能の旅人」を結成し、年一回、公演を行っています。呼吸はピッタリです。いずれも若く、活きの良い能が楽しめます。
シテ、観世喜正師、謡には定評があります。声量と声の艶は十分。
私の席は、舞台のすぐ下。
シテの息づかいが聞こえてきます。
こんな近くで能を見たことはありません。
目の前には、シテの白い足袋が。
せっかくの機会です。
シテの足の運びをずっと追いながら、井筒の能を鑑賞しました。
さらに、能が終わってから、能楽器体験会がもありました。
能管、小鼓、大鼓、それぞれの楽器を、希望者は鳴らしてみることができるのです。老若男女、多くの人が、普段触ったこともない能楽器に興味津々。特に、子供たちが我先にとチャレンジしているのが印象的でした。
とにかく、サービス満点の海津能、皆十分に楽しめたようです。
能の旅人の今年の公演チラシの方は、もうできあがっていました。 いつも、実験的な能にチャレンジしている彼らです。「古式 望月」、どんな舞台になるのか楽しみです。宣伝を兼ねて、写真をアップしておきます。
手づくり能の感想
今回の能、能楽堂での通常の能とはずいぶん異なります。
こじんまりした、手作り感満載の能もなかなか良いものです。
観客のほどんどは普段着。
客層は、老いも若きもいろいろ。特に、5,6才の子供づれのお母さんや小中学生がめだちました。
大丈夫かなあという気もしましたが、観能の邪魔になるような子はいませんでした。
それどころか、作り物体験に積極的に参加し(希望したけれど外れた子も多くいた)、
我先にと笛や小鼓を鳴らす様子は頼もしい限りです。
彼らの内の何人かが、将来、能を嗜んでくれることでしょう。
今、能は危機に瀕していると私は思います。
能楽堂にはそこそこの人が集まるし、海外公演も盛ん ・・・・・・ さすが、世界遺産。
しかし、能は歌舞伎と根本的に異なります。
あらゆるものをギリギリまでそぎ落とした能は、鑑賞者の中で完成されるのです。そのためには、感覚をとぎすまし、自己の中にイメージをつくっていかねばなりません。演じられる能は、そのための触媒でしかありません。幽玄の世界は、舞台上ではなく、私たちの脳の中につくられるのです。ですから、能は究極の参加型演劇なのです。
最も良い参加法は、自分で能を演じることです。特に,謡が重要です。江戸時代からずっと、多くの人々が謡を嗜み、能の世界を自分なりにつくり出してきたのです。
ところが近年、謡い人口は激減しています。人々が参加しない能は、本来の能とはかけ離れた演劇、世界で最も退屈な舞台劇になってしまうのではないでしょうか。
今回のような手作りの能は、能の新しい可能性を示唆しているように思えるのです。
水との闘いと智恵
能が終わって外に出ると、現実に戻されます。
ここは、濃尾平野中の水が集まるところ。
しかも、ゼロメートル地帯。
水害のないときでも、水は留まったままで、ひいてはくれません。
そこで、排水機を使って、水を堤外へ排出する必要があります。
また、水はけの悪い場所でも稲作ができるように、堀田がつくられました。
土を掘り上げて盛り、高くした細長い田をつくるのです。
クリークと細長い田が交互に連なります。
移動は船。
現在は、排水機が完備し、堀田はなくなりました。