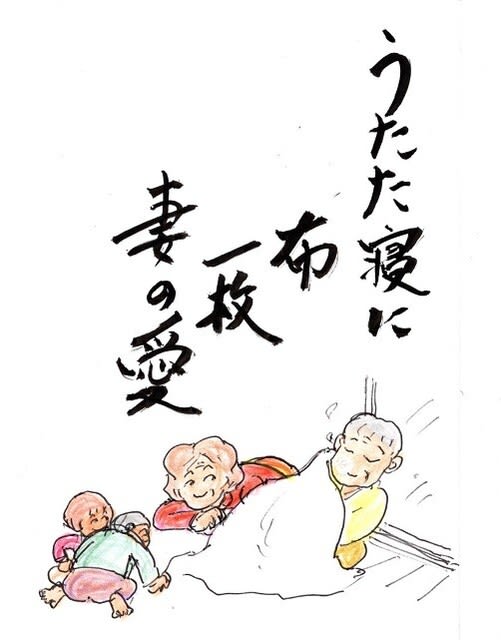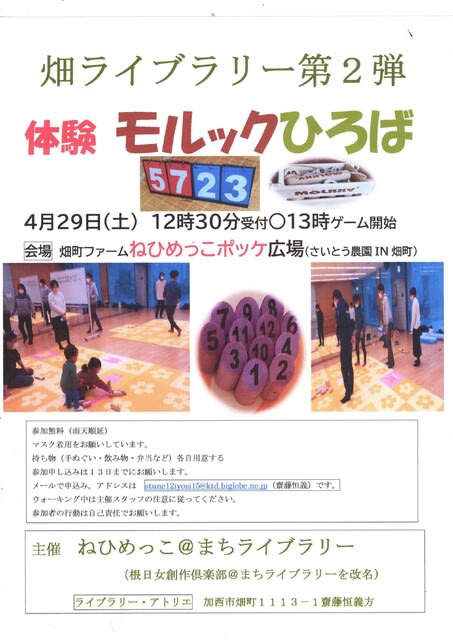雨。どんより気持ちで家に引き籠もっています。
こんな状況ではロクなことを考えない。
頭も働かないので無理せず、
昔の原稿を引っ張り出します。
そして「ふるさと川柳公募」の3作品をアップ。
「ジャズセッション」
「彼女、どうだった?いい子でしょ」
単刀直入である。彼女は、いつもそうだった。あっけらかんとした気性で、しょっちゅう戸惑う。
「…なにバカ言ってるんや、お前さんは」
口を尖らした。ひと回り以上も若いのに、お互いタメ口を叩く間柄である。といって恋人ではない。
彼女は卒業を控えた私立短大生。俊彦は既に三十を越した喫茶店のマスター。普通なら接点のない二人を引き合わせたのは、共通する趣味だった。
俊彦はあまり友人がいない。暇があっても誰彼と連れ立って何かを楽しむタイプではない。ひとり気の向いた場所を訪れてひとり淡々とと楽しむのだった。
ジャズ喫茶『らいら』は、三年前何となく街中を散策していて行き当たった。以来常連の客となる。『らいら』の薄暗い客席でジャズに聞き入っている学生服の女の子はえらく目立った。高校生の寿々美だった。
「見ない顔だねえ」
坊主頭で口ひげをたくわえた異様な風貌のオーナーがカウンターにいた。
「ジャズ喫茶は初めてなんやけど」
「それで、相席でええかな」
「はあ」
見知らぬ人間と相席、断りたいところだが、新参者にはその権利はない。オーナーの特異な顔がそう語っていた。
案内された席に、あの女子学生がいた。
「相席、してんか、寿々」
オーナーは砕けた口調で声を掛けた。
「うちは、ええよ」
彼女は笑っていた。反射的に俊彦はペコリと頭を下げた。
「えらい礼儀正しい人やね」
「はあ、それだけが取り柄ですねん」
顔を上げると、幼い少女の笑顔が目に飛び込んだ。それが寿々美との初対面だった。
二度目に『らいら』を覗いたときも彼女と相席で並んだ。初対面の緊張感は半減していて、それなりの会話が出来た。他人とそう簡単に打ち解ける性格じゃないのに、気さくな寿々美の対応で、俊彦はリラックスした。
その後も俊彦が『らいら』に顔を出すと、いつも寿々美はその席にいた。一年も経つと、年の差など関係なくざっくばらんに話せるようになる。あえてひとりぼっちを選びたがる俊彦には珍しいことだった。
三年後、俊彦が喫茶『七枚の画布(ななまいのきゃんばす)』をオープンさせると、寿々美はいの一番に常連客となった。
「沢尻さんみたいに生真面目で堅物じゃ、喫茶店のマスターになれないよ。もう心配で放っておけないから、うちがコーチしてあげる」
短大生の寿々美は、えらくお節介焼きだった。困った時の彼女頼みという格好である。
寿々美の意見を入れて、BGMはジャズに拘った。いい雰囲気が醸し出される。メニューも彼女の若い感性が生きる助言を取り入れた。パフェメニューは人気を呼んだ。
「マスター、口ひげが似合うわよ。少しは堅いイメージが柔らぐかもね」
「そうかな」
かなり多く寿々美の意見を取り入れた。俊彦はひげのマスターに変身である。
寿々美は時々短大の友達を連れて来店する。
「ななきゃん(七枚の画布)っていい感じのお店でしょ」
「うん。寿々美が話してた通りね。髭のマスターもスゴクかっこいいやん」
カウンター越しに聞こえる彼女らの会話に結構気分をよくした。
「マスター。どっか行きつけのスナックない?」
「まあね」
「そこ、呑みに連れて行ってよ」
隠れ家的に通っているスナックに寿々美を伴った。『女西郷隆盛』と客が呼ぶ容姿のママがひとりでやっている店である。
「あら。俊彦ちゃん、可愛い子、連れて来たのね」
「ジャズ愛好仲間の加茂寿々美さん。まだ短大生なんやねん」
「恋人?」
「バカ言わんといて、ママ。友達や、年の離れた友達なんや」
「あらら、ムキになってる。やっぱり怪しい」
「怪しくない。友達、ただの友達や!」
「そうなの。残念だ。お似合いやと思ったのに。でも、俊彦ちゃん、いい加減身を固めなさいよ。もう三十過ぎたんでしょ。うかうかしてたら、もう当たんないわよ」
「焦ったって、どうにもなりゃしないよー」
くだらない話題で盛り上がった。
「マスター、焦ってるんやね」
帰り道、何を思ったのか寿々美が茶化した。
「仕方ないさ。昔から女性との付き合いに縁がないんや。モテへんねん」
「うそー!マスターってイケてるのに」
「俺は初対面に弱いんや。特に女性を前にしたら何もいえなくなる、暗い性格なの。そんな俺でも適齢期やからな。そら若い嫁さんが欲しい!お見合いしたい!付き合いたい!」
少し酒が入ったせいで、妙に饒舌になっている。
「わかった。わたしに任せといて」
寿々美は自信満々に頷いた。
「あの子、マスターに一目惚れしたっていってたよ」
「ばかばかしい。大人をからかうんやないよ。もし本気になったら、どうすんや?」
「あら?本気になって貰わないと困るやん。独身のマスター、可愛そうやから、うちの友達と順番にお見合いさせてんじゃんか。マスター、あんなに見合いしたがってたから、これでも苦労してんのよ」
「あんな冗談、真に受けたのか」
「ひどい!冗談やったん?若い嫁さんが欲しい!女の子と付き合いたい!って言ってたよ」
俊彦は照れ隠しに頭を掻いた。ひと回り以上も年の離れた女の子と、自分の結婚問題をまともに議論している。苦笑するしかない。(俺って子どもやなあ)とはいえ、いくら大人になろうとも、寿々美が紹介する三人の友達は、幼な過ぎたし俊彦の好みとは違う。
「もうええ。いくら紹介されても無駄、無駄!大体初対面に弱いのを、どないすんねん」
「初対面が駄目やったんや…なんか、ええ方法が…?うーん、ならうちはどない?」
寿々美はあっさりいってのけた。俊彦は思わずドキッとした。顔を赤くしたのが分かった。(え?俺、どうしたんや?…まさか)。
「冗談、冗談や、いまのんは。あーあ、マスターったら赤くなってる。おかしいやん」
「バカ!からかうな、大人を」
俊彦はムキになって抗議した。しかし、ムキになればなるほど、寿々美の存在が気になる。これはどうしたんだろう?
「また連れて来るよ。今度の友達、もっと性格いいから。マスターにピッタリや」
「もうええ!」
強い口調になった。寿々美は驚いて目を丸くした。
「どうして?このチャンス逃したら生涯一人モンやんか」
「構わへん!」
不機嫌をモロ出しする俊彦に、寿々美は面喰った。表情が曇った。
「ごめん!俺のためにいろいろしてくれてんのに、きつい事いうてしもて」
俊彦は悔やんだ。大人げない自分の態度が寿々美を傷つけた。それだけではない。やけに胸が痛む。こんな経験は初めてだ。
「…悪いと思ってるんなら、明日呑みに連れて行ってよ」
「え?」
思わず見直した寿々美の顔は、いつもの笑顔…いや、なんだか大人びている。
翌夕。時間を見計らって店にあらわれた寿々美は、えらくめかし込んでいる。ちゃんと化粧まで整えて、普段は素面なのに。俊彦は見惚れた。胸が熱くなる。いかん!おいおい、どうしたんだ?
「…なんで…どういう風の吹き回しや?」
狼狽を隠すために冗談口調となった。
「なによ。何がおかしいん?」
寿々美はムキになった。あまり見つめると、こちらがおかしくなりそうだ。俊彦は無理に笑った。情けない、ぎごちなさを自覚する。
「あら、いらっしゃい!」
女西郷隆盛が甲高い声で迎えてくれた。
「また二人なんだ」
ママの言葉は意味深である。
「やっぱりお似合いよ、あなたたち」
「ママ。若い子を傷つけるようなこというたらあかん」
俊彦はウィスキーのロックを口にした。
「あらそう。おかしいな、わたしの勘よく当たんのに」
「ママさん。…マスターって鈍感なの?」
寿々美は直線的に訊いた。
「そんなことないわよ。ただ優しすぎんのよ。優しすぎる男は、いつだって優柔不断なの。そんな男には、あんたみたいな若い女の子が引っ張ったらコロリといっちゃうかもね」
ママは寿々美に片目をつぶって見せる。寿々美の目が、いきなり線になった。
「ええのええの、俺は生涯一人で生きるんや!」
顔を赤くした俊彦は天を仰いで宣言を繰り返した。相当酩酊している。
ジャズの生演奏は目を閉じて感じる。薄暗いホールにアルトサックスが郷愁の音色で心を揺さぶる。魂を揺さぶるというべきか。
「私は初対面じゃないでしょ。沢尻さんの嫁さんになったげる。うちしかおらんやろ…」
目を閉じた俊彦は、夢を見た。耳に心地よい寿々美のささやきが幸せを運んで来るー。

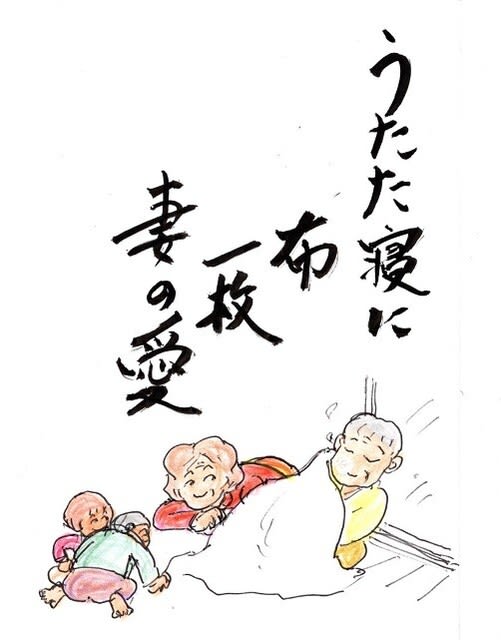

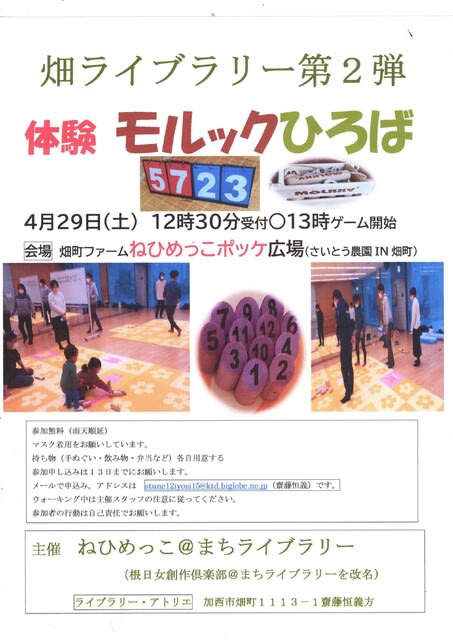
こんな状況ではロクなことを考えない。
頭も働かないので無理せず、
昔の原稿を引っ張り出します。
そして「ふるさと川柳公募」の3作品をアップ。
「ジャズセッション」
「彼女、どうだった?いい子でしょ」
単刀直入である。彼女は、いつもそうだった。あっけらかんとした気性で、しょっちゅう戸惑う。
「…なにバカ言ってるんや、お前さんは」
口を尖らした。ひと回り以上も若いのに、お互いタメ口を叩く間柄である。といって恋人ではない。
彼女は卒業を控えた私立短大生。俊彦は既に三十を越した喫茶店のマスター。普通なら接点のない二人を引き合わせたのは、共通する趣味だった。
俊彦はあまり友人がいない。暇があっても誰彼と連れ立って何かを楽しむタイプではない。ひとり気の向いた場所を訪れてひとり淡々とと楽しむのだった。
ジャズ喫茶『らいら』は、三年前何となく街中を散策していて行き当たった。以来常連の客となる。『らいら』の薄暗い客席でジャズに聞き入っている学生服の女の子はえらく目立った。高校生の寿々美だった。
「見ない顔だねえ」
坊主頭で口ひげをたくわえた異様な風貌のオーナーがカウンターにいた。
「ジャズ喫茶は初めてなんやけど」
「それで、相席でええかな」
「はあ」
見知らぬ人間と相席、断りたいところだが、新参者にはその権利はない。オーナーの特異な顔がそう語っていた。
案内された席に、あの女子学生がいた。
「相席、してんか、寿々」
オーナーは砕けた口調で声を掛けた。
「うちは、ええよ」
彼女は笑っていた。反射的に俊彦はペコリと頭を下げた。
「えらい礼儀正しい人やね」
「はあ、それだけが取り柄ですねん」
顔を上げると、幼い少女の笑顔が目に飛び込んだ。それが寿々美との初対面だった。
二度目に『らいら』を覗いたときも彼女と相席で並んだ。初対面の緊張感は半減していて、それなりの会話が出来た。他人とそう簡単に打ち解ける性格じゃないのに、気さくな寿々美の対応で、俊彦はリラックスした。
その後も俊彦が『らいら』に顔を出すと、いつも寿々美はその席にいた。一年も経つと、年の差など関係なくざっくばらんに話せるようになる。あえてひとりぼっちを選びたがる俊彦には珍しいことだった。
三年後、俊彦が喫茶『七枚の画布(ななまいのきゃんばす)』をオープンさせると、寿々美はいの一番に常連客となった。
「沢尻さんみたいに生真面目で堅物じゃ、喫茶店のマスターになれないよ。もう心配で放っておけないから、うちがコーチしてあげる」
短大生の寿々美は、えらくお節介焼きだった。困った時の彼女頼みという格好である。
寿々美の意見を入れて、BGMはジャズに拘った。いい雰囲気が醸し出される。メニューも彼女の若い感性が生きる助言を取り入れた。パフェメニューは人気を呼んだ。
「マスター、口ひげが似合うわよ。少しは堅いイメージが柔らぐかもね」
「そうかな」
かなり多く寿々美の意見を取り入れた。俊彦はひげのマスターに変身である。
寿々美は時々短大の友達を連れて来店する。
「ななきゃん(七枚の画布)っていい感じのお店でしょ」
「うん。寿々美が話してた通りね。髭のマスターもスゴクかっこいいやん」
カウンター越しに聞こえる彼女らの会話に結構気分をよくした。
「マスター。どっか行きつけのスナックない?」
「まあね」
「そこ、呑みに連れて行ってよ」
隠れ家的に通っているスナックに寿々美を伴った。『女西郷隆盛』と客が呼ぶ容姿のママがひとりでやっている店である。
「あら。俊彦ちゃん、可愛い子、連れて来たのね」
「ジャズ愛好仲間の加茂寿々美さん。まだ短大生なんやねん」
「恋人?」
「バカ言わんといて、ママ。友達や、年の離れた友達なんや」
「あらら、ムキになってる。やっぱり怪しい」
「怪しくない。友達、ただの友達や!」
「そうなの。残念だ。お似合いやと思ったのに。でも、俊彦ちゃん、いい加減身を固めなさいよ。もう三十過ぎたんでしょ。うかうかしてたら、もう当たんないわよ」
「焦ったって、どうにもなりゃしないよー」
くだらない話題で盛り上がった。
「マスター、焦ってるんやね」
帰り道、何を思ったのか寿々美が茶化した。
「仕方ないさ。昔から女性との付き合いに縁がないんや。モテへんねん」
「うそー!マスターってイケてるのに」
「俺は初対面に弱いんや。特に女性を前にしたら何もいえなくなる、暗い性格なの。そんな俺でも適齢期やからな。そら若い嫁さんが欲しい!お見合いしたい!付き合いたい!」
少し酒が入ったせいで、妙に饒舌になっている。
「わかった。わたしに任せといて」
寿々美は自信満々に頷いた。
「あの子、マスターに一目惚れしたっていってたよ」
「ばかばかしい。大人をからかうんやないよ。もし本気になったら、どうすんや?」
「あら?本気になって貰わないと困るやん。独身のマスター、可愛そうやから、うちの友達と順番にお見合いさせてんじゃんか。マスター、あんなに見合いしたがってたから、これでも苦労してんのよ」
「あんな冗談、真に受けたのか」
「ひどい!冗談やったん?若い嫁さんが欲しい!女の子と付き合いたい!って言ってたよ」
俊彦は照れ隠しに頭を掻いた。ひと回り以上も年の離れた女の子と、自分の結婚問題をまともに議論している。苦笑するしかない。(俺って子どもやなあ)とはいえ、いくら大人になろうとも、寿々美が紹介する三人の友達は、幼な過ぎたし俊彦の好みとは違う。
「もうええ。いくら紹介されても無駄、無駄!大体初対面に弱いのを、どないすんねん」
「初対面が駄目やったんや…なんか、ええ方法が…?うーん、ならうちはどない?」
寿々美はあっさりいってのけた。俊彦は思わずドキッとした。顔を赤くしたのが分かった。(え?俺、どうしたんや?…まさか)。
「冗談、冗談や、いまのんは。あーあ、マスターったら赤くなってる。おかしいやん」
「バカ!からかうな、大人を」
俊彦はムキになって抗議した。しかし、ムキになればなるほど、寿々美の存在が気になる。これはどうしたんだろう?
「また連れて来るよ。今度の友達、もっと性格いいから。マスターにピッタリや」
「もうええ!」
強い口調になった。寿々美は驚いて目を丸くした。
「どうして?このチャンス逃したら生涯一人モンやんか」
「構わへん!」
不機嫌をモロ出しする俊彦に、寿々美は面喰った。表情が曇った。
「ごめん!俺のためにいろいろしてくれてんのに、きつい事いうてしもて」
俊彦は悔やんだ。大人げない自分の態度が寿々美を傷つけた。それだけではない。やけに胸が痛む。こんな経験は初めてだ。
「…悪いと思ってるんなら、明日呑みに連れて行ってよ」
「え?」
思わず見直した寿々美の顔は、いつもの笑顔…いや、なんだか大人びている。
翌夕。時間を見計らって店にあらわれた寿々美は、えらくめかし込んでいる。ちゃんと化粧まで整えて、普段は素面なのに。俊彦は見惚れた。胸が熱くなる。いかん!おいおい、どうしたんだ?
「…なんで…どういう風の吹き回しや?」
狼狽を隠すために冗談口調となった。
「なによ。何がおかしいん?」
寿々美はムキになった。あまり見つめると、こちらがおかしくなりそうだ。俊彦は無理に笑った。情けない、ぎごちなさを自覚する。
「あら、いらっしゃい!」
女西郷隆盛が甲高い声で迎えてくれた。
「また二人なんだ」
ママの言葉は意味深である。
「やっぱりお似合いよ、あなたたち」
「ママ。若い子を傷つけるようなこというたらあかん」
俊彦はウィスキーのロックを口にした。
「あらそう。おかしいな、わたしの勘よく当たんのに」
「ママさん。…マスターって鈍感なの?」
寿々美は直線的に訊いた。
「そんなことないわよ。ただ優しすぎんのよ。優しすぎる男は、いつだって優柔不断なの。そんな男には、あんたみたいな若い女の子が引っ張ったらコロリといっちゃうかもね」
ママは寿々美に片目をつぶって見せる。寿々美の目が、いきなり線になった。
「ええのええの、俺は生涯一人で生きるんや!」
顔を赤くした俊彦は天を仰いで宣言を繰り返した。相当酩酊している。
ジャズの生演奏は目を閉じて感じる。薄暗いホールにアルトサックスが郷愁の音色で心を揺さぶる。魂を揺さぶるというべきか。
「私は初対面じゃないでしょ。沢尻さんの嫁さんになったげる。うちしかおらんやろ…」
目を閉じた俊彦は、夢を見た。耳に心地よい寿々美のささやきが幸せを運んで来るー。