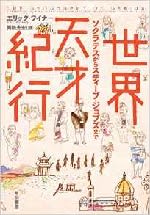(1)日本は軍縮会議(ワシントン平和会議)で米国に騙された。米国が、日英同盟を発展的に解消して地域の集団的安全保障をやろうと言って、それで全然関係のないフランスを形だけ持ってきて、4ヵ国で条約をつくるろうと持ちかけた。フランスは太平洋での海洋権益はないのに。この4ヵ国で互いに安全保障をすれば大丈夫だといって日英同盟を解消させた。それで米英が接近していった。となると日本は海洋国家であるにもかかわらず、同じ海洋国家である米国とイギリスの両方を敵に回すという選択を採った。それによって、あの無謀な戦争に飛び込んでいったわけだ。
(2)改めて戦争の整理をすると、日本の陸軍は地政学をちゃんと勉強していたから米国と戦を構える気はなかった。それに日本の陸軍の中で強いのは、常に英米可分論。ちなみに真珠湾奇襲よりも、イギリス領マーレ半島上陸のほうが数時間早かった。真珠湾の6時間ぐらい前にマレー半島に上陸している。つまりあの戦争は本質においてはイギリスとの戦争だ。それはイギリスが海洋覇権ではなくて、東南アジアの資源を握っていて、そこに日本は関心があったのだ。
だから、裏返すと、イギリスがアジアから手を引いて、それで折り合いがつくならあの戦争は避けることができた。だから基本的にはあの戦争を日本のほうから見ると、日英戦争だ。陸軍のほうは日英戦争ですあら二次的に考えていたぐらいで、日米戦争なんて全然考えていなかった。陸軍が第一義的に考えていたのは日ソ戦だ。日本が大陸国家として進出すべきと考えていたから。
(3)しかし、陸軍はある時期から極めて慎重になった。張鼓峰事件(1938年)と翌年のノモンハン事件(1939年)からだ。ちなみに、日本では「事件」という扱いだが、今、国際的にはノモンハン(ハルヒンゴル)事件の研究が進んでいて、ノモンハン「戦争」という言い方のほうが主流になっている。
第二次世界大戦でドイツ軍を破ったときのソ連の軍事最高司令官はゲオルギー・ジューコフだが、ジューコフはノモンハン事件のときのソ連軍の司令官でもあった。彼は回想録の中で、これまで最も苦しい戦いはどこだったかというと、ハルヒンゴル事件だったと言っている。「ハルヒンゴルでの日本との戦いは、今までの戦いの中では最も苦しかった」と。
それは日本にとっても同じだ。日本が地政学的に海洋国家の方針を採って大陸に出ていかなければ満州国なんかつくらなかったし、朝鮮半島も植民地支配しなかった。朝鮮半島は支配ではなく保護国みたいな形で、少なくとも神社参拝を強要して、そこでアトム的な価値観を押しつけるようなことはしなかったはずだ。
(4)朝鮮半島はもともと檀君信仰がある。今、北朝鮮は檀君信仰をそのまま金日成神話に転換している。ピョンヤンの郊外に、檀君の夫妻の骨が見つかったといって、それを祀ってあるピラミッドがある。もし日本がアマテラスではなく、檀君を祖神とする形での宗教をつくらせていたら、朝鮮半島に土着化できた可能性はある。しかし大東亜共栄圏の内部というのはモナドロジー的な発想を持たない、すごくアトム的で均質な、ベタな発想だったわけだ。それでものすごい軋轢が出てきてしまった
(5)軍事的に見れば、日本で近代戦をやったのは1905年の日露戦争が最後だ。ちなみに、日露戦争では、大量のコンクリートを使って、トーチカ(要塞)をつくって、そこに機関銃を据えて戦った。トーチカとはロシア語で「点」という意味だ。
機関銃から派生してできた、われわれが日常的に使っている文房具がある。ヒントはマックス。マックスは機関銃メーカーの名前だ。答えはホチキス。ホチキスのあの玉送りは、機関銃の弾送りの仕組みを使っている。弾をそのままホチキスの針に代えただけ。あの順番で弾を送っていくという技術を民間に転用するとホチキスになる。
そういうわけで日露戦争は大量の機関銃を使って物量戦をやったという、第一次世界大戦の先駆けとしての意味がある。でもその後の第一次世界大戦は、日本にとっては日英同盟を口実に、後から入ってきたという話だ。
□佐藤優「第一講 地政学とは何か」(『現代の地政学』、晶文社、2016)pp.59-61
↓クリック、プリーズ。↓



【参考】
「【佐藤優】トルキスタンの分割、変容する民族意識、ユーラシア主義の地政学」
「【佐藤優】地政学から見る第二次世界大戦前夜」
「【佐藤優】地政学とファシズムと難民」
「【佐藤優】最悪情勢分析 ~NPT体制の崩壊~」
(2)改めて戦争の整理をすると、日本の陸軍は地政学をちゃんと勉強していたから米国と戦を構える気はなかった。それに日本の陸軍の中で強いのは、常に英米可分論。ちなみに真珠湾奇襲よりも、イギリス領マーレ半島上陸のほうが数時間早かった。真珠湾の6時間ぐらい前にマレー半島に上陸している。つまりあの戦争は本質においてはイギリスとの戦争だ。それはイギリスが海洋覇権ではなくて、東南アジアの資源を握っていて、そこに日本は関心があったのだ。
だから、裏返すと、イギリスがアジアから手を引いて、それで折り合いがつくならあの戦争は避けることができた。だから基本的にはあの戦争を日本のほうから見ると、日英戦争だ。陸軍のほうは日英戦争ですあら二次的に考えていたぐらいで、日米戦争なんて全然考えていなかった。陸軍が第一義的に考えていたのは日ソ戦だ。日本が大陸国家として進出すべきと考えていたから。
(3)しかし、陸軍はある時期から極めて慎重になった。張鼓峰事件(1938年)と翌年のノモンハン事件(1939年)からだ。ちなみに、日本では「事件」という扱いだが、今、国際的にはノモンハン(ハルヒンゴル)事件の研究が進んでいて、ノモンハン「戦争」という言い方のほうが主流になっている。
第二次世界大戦でドイツ軍を破ったときのソ連の軍事最高司令官はゲオルギー・ジューコフだが、ジューコフはノモンハン事件のときのソ連軍の司令官でもあった。彼は回想録の中で、これまで最も苦しい戦いはどこだったかというと、ハルヒンゴル事件だったと言っている。「ハルヒンゴルでの日本との戦いは、今までの戦いの中では最も苦しかった」と。
それは日本にとっても同じだ。日本が地政学的に海洋国家の方針を採って大陸に出ていかなければ満州国なんかつくらなかったし、朝鮮半島も植民地支配しなかった。朝鮮半島は支配ではなく保護国みたいな形で、少なくとも神社参拝を強要して、そこでアトム的な価値観を押しつけるようなことはしなかったはずだ。
(4)朝鮮半島はもともと檀君信仰がある。今、北朝鮮は檀君信仰をそのまま金日成神話に転換している。ピョンヤンの郊外に、檀君の夫妻の骨が見つかったといって、それを祀ってあるピラミッドがある。もし日本がアマテラスではなく、檀君を祖神とする形での宗教をつくらせていたら、朝鮮半島に土着化できた可能性はある。しかし大東亜共栄圏の内部というのはモナドロジー的な発想を持たない、すごくアトム的で均質な、ベタな発想だったわけだ。それでものすごい軋轢が出てきてしまった
(5)軍事的に見れば、日本で近代戦をやったのは1905年の日露戦争が最後だ。ちなみに、日露戦争では、大量のコンクリートを使って、トーチカ(要塞)をつくって、そこに機関銃を据えて戦った。トーチカとはロシア語で「点」という意味だ。
機関銃から派生してできた、われわれが日常的に使っている文房具がある。ヒントはマックス。マックスは機関銃メーカーの名前だ。答えはホチキス。ホチキスのあの玉送りは、機関銃の弾送りの仕組みを使っている。弾をそのままホチキスの針に代えただけ。あの順番で弾を送っていくという技術を民間に転用するとホチキスになる。
そういうわけで日露戦争は大量の機関銃を使って物量戦をやったという、第一次世界大戦の先駆けとしての意味がある。でもその後の第一次世界大戦は、日本にとっては日英同盟を口実に、後から入ってきたという話だ。
□佐藤優「第一講 地政学とは何か」(『現代の地政学』、晶文社、2016)pp.59-61
↓クリック、プリーズ。↓
【参考】
「【佐藤優】トルキスタンの分割、変容する民族意識、ユーラシア主義の地政学」
「【佐藤優】地政学から見る第二次世界大戦前夜」
「【佐藤優】地政学とファシズムと難民」
「【佐藤優】最悪情勢分析 ~NPT体制の崩壊~」